

私の行動は目立つみたい。
出る杭になっても打たれずに仕事をする対処方法ある?
打たれる原因や打たれやすい人の特徴も知りたいな。
そんな疑問に答えます。
組織の中で働くと”出る杭は打たれる”問題はついて回りますよね。
出る杭は打たれるの意味は広辞苑によると、
『優れて抜け出ている者は、とかく憎まれる。また、さしでてふるまう者は他から制裁されることの例え』
とあります。

周りから制裁されてうれしい人はいませんよね
しかし、これからの時代は出る杭にならないと周りに埋もれて沈没する恐れがあります。
大げさに聞こえるかもしれませんが事実です。とは言うものの打たれないようにしたいのが本音ですよね。
そこで本記事では、出る杭になろうとも、打たれないようにする方法について解説しています。
自分も周りも喜ぶような”出る杭”になって活躍するための記事です。
- この記事の主な内容です
- 出る杭になると打たれる3つの原因
- 出る杭になって打たれる人の特徴
- 出る杭になっても打たれない対処法
- 出る杭にならないとヤバ過ぎる件
- 出過ぎる杭になって活躍するコツ
- この記事の信頼性
※読み飛ばしOKです
この記事を書いている私は、表面的な自己分析では不可能な深い見極めや、真のキャリアの方向性を求める人たちに10年以上向き合い続けました。
“出る杭は打たれる”経験をした人を含む2000人以上を指導し、経験からの教えを伝えています。
日本経済新聞や日経WOMANなど、多数のメディアで取り上げられた経験もあります。
「私はこの仕事が好き!!自分の“強み”を活かして稼ぐ方法(大和出版)」というタイトルの書籍も出版しています。
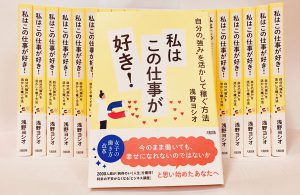
詳しい私のことはこちらです
出る杭になると打たれる3つの原因

出る杭になると打たれる原因を解説します。
主な原因は、
- 本能によるもの
- 嫉妬によるもの
- 日本の社会構造によるもの
以上の3つ。
これらを知っておくと打たれても気が楽になりますよ。わかりやすく解説しますね。
(1)本能による原因
 出る杭になると打たれる原因の1つ目は、本能によるもの。
出る杭になると打たれる原因の1つ目は、本能によるもの。
起源は原始時代にさかのぼります。
ヒトの周りに、どう猛な獣(けもの)がたくさんいました。そして男性が狩りに出かける間、女性は群れを作って身を守りました。
その群れの中に、出る杭になるような行動をする人がいると、秩序を保てないですよね。
そこで秩序を保つために、出る杭になる行為をすると、打たれるようになったわけです。つまり身を守る本能によるものですね。
(2)嫉妬による原因
 出る杭になると打たれる原因の2つ目は、嫉妬によるもの。
出る杭になると打たれる原因の2つ目は、嫉妬によるもの。
ある心理学者によると、自分より下もしくは同等レベルと思っていた人に対し、自分より優れていると認識したときに起こる感情が嫉妬となるそうです。
要は、優れた行為や目立つ行為は「おもしろくないヤツ」と周りに思われてしまううわけです。
嫉妬心は男女問わずヒトに備わるものですが、とかく女性は嫉妬の対象になりやすいですよね。

職場で優秀な女性でも、男性の同僚に嫌がらせを受けていたら嫉妬の可能性もありですよ。
(3)日本の社会構造による原因
 出る杭になると打たれる原因の3つ目は、日本の社会構造によるものです。
出る杭になると打たれる原因の3つ目は、日本の社会構造によるものです。
日本は、出る杭タイプの人が打たれやすい環境。島国なので外に出にくい。そのため群れをなして生きていたと言えます。前にも書いたように出る杭的な行動は打たれやすいのです。
また、これまでの日本は年功序列・終身雇用制により「誰かがいなくならないと自分は上がらない」社会構造になっていましたよね。つまり出る杭を叩けば自分が上るチャンスになるとも言えたのです。
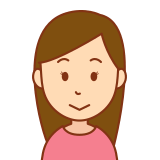
なるほど。打たれる原因はよくわかりました。ちなみにどのような人が打たれやすいのですか?
出る杭になって打たれやすい人の特徴

出る杭になって打たれる人の特徴は次のとおりです。
- 自分中心になっている
- 手柄を独り占めする
- 批判はするけれど代案がない
- 正義感に囚われている
少し補足します。
あらゆることが自分中心になっている人は打たれやすいです。周りへの配慮なくスタンドプレイに走るとか、自分がやらないで人にやらせてしまうとかですね。
また、手柄を独り占めするなんていうのも打たれまくります。周りからすれば迷惑な人ですから。
そして批判はするけれど代案がない、もしくは口だけで自ら率先してやろうとしないなんていうのも打たれますね。物ごとが前に進まないし、特に仕事であれば滞るだけですから。
自らの正義感に囚われている人も打たれやすいです。たとえば「会社のやり方は間違っている!」みたいな正義の主張ですね。仮に言っていることは間違っていなくとも上司から煙たがられる姿が目に浮かぶでしょう。
出る杭になっても打たれない対処法

出る杭になっても打たれない方法は、結論から先に言うと出過ぎた杭になることです。
ベタな回答ですいません。でもこれがベストの答えです。
繰り返しの解説になりますけど、打たれる原因として嫉妬によるものが大きいです。嫉妬は自分より下もしくは同等レベルと思っていた人に対し、自分より優れていると認識したとき湧く感情でしたよね。
たとえば、クセモノだけど仕事ができる上司とかいるじゃないですか。仕事ができる=出過ぎている状態だからクセも個性として周りから受け止められているのですよね。
即ち、周りよりも突き抜けた存在になることが、出る杭になっても打たれない対処法なのです。

ほかに打たれないように予防する方法ないかな?

確かに出過ぎるほど力をつけるには時間が必要ですものね。予防方法を次に解説します。
打たれないように予防する方法
 出る杭になっても打たれないように予防するためには、下記を意識するといいです。
出る杭になっても打たれないように予防するためには、下記を意識するといいです。
- 根回しをする
- 手柄をゆずる
- 自ら率先して行動する
- 目的は周りに合わせる
- 相手にメリットを与える
順に解説しますね。
(1)根回しをする
 出る杭になっても打たれないように予防する方法1つ目は、根回しをすることです。
出る杭になっても打たれないように予防する方法1つ目は、根回しをすることです。
根回しとは「ある目的を実現しやすいように、関係する方面にあらかじめ話をつけておくこと」を言います。
報・連・相という言葉がありますよね。報告・連絡・相談というヤツ。これは予防線に使えます。
私の塾の受講生にテレビ局に勤務していた女性がいましたけど、彼女は根回しが上手でこれまでにない企画を数々通していました。すべてのコツは「報・連・相」だったそうですよ。何も言わずに実行すると「出過ぎたマネしやがって」と受け取られそうですものね。
自分はどのような行動をするか、その進捗やどのような結果を得られたかまで、周りに報・連・相するといいですよ。

群れの空気をなるべく壊さないようにすることですね
(2)手柄を譲る
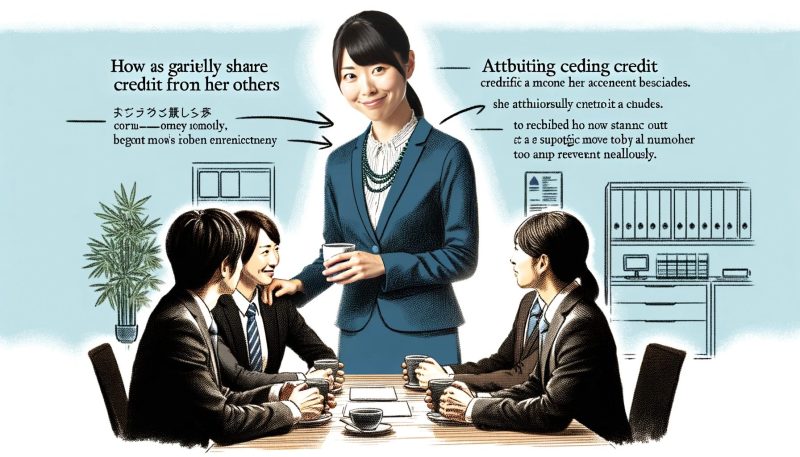
出る杭になっても打たれないように予防する方法2つ目は、手柄を譲ることです。
たとえ自分の力でやり抜いたとしても「○○さんのおかげです」と周りに伝える。
なんだか損している気になるかもしれませんけど、嫉妬されて足を引っ張られない予防線だと思えばいいですよ。周りの人の自尊心を満たし、嫉妬心は緩和されますから。
出過ぎた杭になるまでのガマンです。

とにかく腰を低くは鉄則ですね
(3)自ら率先して行動する
 出る杭になっても打たれないように予防する方法3つ目は、自ら率先して行動することです。
出る杭になっても打たれないように予防する方法3つ目は、自ら率先して行動することです。
出る杭になる言動は、最初は賛同してもらえないかもしれません。それでも実行していると周りの見る目も変わります。
自ら率先して行動することが大切ですね。
(4)目的を周りに合わせる
 出る杭になっても打たれないように予防する方法4つ目は、目的を周りに合わせることです。
出る杭になっても打たれないように予防する方法4つ目は、目的を周りに合わせることです。
目的は周りに合わせることは、打たれないようにする原則ですね。
メジャーリーグのあるチームは、個性的な選手ばかり集まっています。
- オール・出る杭ですよ。
しかし、みなが「優勝」を目的に集まっているため一丸となれる。
この例は、メジャーリーグだけのお話ではなく、どのような組織にも当てはまります。
組織で仕事をするならば、最後の目的だけは足並みそろえなければですよね。
(5)相手にメリットを与える
 出る杭になっても打たれないように予防する方法5つ目は、相手にメリットを与えることです。
出る杭になっても打たれないように予防する方法5つ目は、相手にメリットを与えることです。
下記の例を読んでくださいね。
- 女性経営者Bさんの例:
女性経営者Bさんは、美容関係の店舗をいくつか経営しています。
Bさんは店舗のある地域で生まれ育ったわけではありません。
それだけに商売をするとき、昔から住む地元の人達に大変な気遣いをしています。
商工会議所を始めとした、地域活動にも時間を割き、地元住民や経営者のために動いています。
つまりBさんは出る杭になりながらも、周りの人たちのメリットになることを続けているのです。
【結論】出る杭にならないと危険過ぎる件

これからの時代は出る杭にならないと、会社員としても働けなくなりそう。その理由は、今後ジョブ型雇用が増えていくからね。
ジュブ型雇用とは、職務を明確にして年齢・年次を問わない雇用方法です。そうなればプロ(専門性のある人)しか生き残れないでしょう。
この流れはやがて中小企業にも広まるのも目にみえている。なぜなら仕事できない人を雇い続ける余力(お金)は今の会社にないからです。
ともすると、周りに埋もれていたら仕事をもらえなくなりますよね。「あなたがいないと困る」と思われる人材になることが不可欠です。
即ち「出る杭にならねばならない」ということです。出過ぎる杭になる覚悟を決めなきゃですね。
出過ぎる杭になるためにやるべきこと

出過ぎる杭になるためにやるべきことがあります。自分の弱みも強みもきちんと棚卸ししなければなりません。
今以上に自分を使いこなす必要があるから。
- 強みを活かせる
- 弱みをカバーできる
- 長く続けても苦痛にならない
特別な才能がある人でない限り、以上の3点が揃う仕事をしないと出過ぎる杭になれません。
つまり、
- ハマる仕事をすることです。
下記の記事に、出過ぎる杭になるために大切なことを書いてますので参考にどうぞ。
▶強みを発見する自分の棚卸し20の要点完全ガイド|転職・起業の武器に役立つ最新ツール公開
また、専門家の適切なサポートを受けて、自分の強みやその価値を理解し、最適なキャリアの方向性を探りたい方はこちらの講座からスタートするといいでしょう。
ファンとアンチの両方が増える【体験談】

私の体験談をお話しますね。出る杭になるとファンとアンチの両方が増えますよ。
私が最初に出版したこちらの本↓
Amazonのレビューを見てください。星5&4が合わせて52%ありますが、星1&2つも32%に昇ります。
ファンとアンチが混在しているのです。この本は、出版した年、Amazonで2番目に売れた新書となり、5日間総合1位になりました。
いちおう証拠画像を↓
レビューの結果は、こちらの本を単純にこの本が良い・悪いと位置づけてしまえばそれまでですよね。でもこの本が売れた後に、厳しいことを言われる場面は増えた。その証拠に厳しいレビューの中に、本の内容と関係ないことも書かれていた。
また、こちらの本では私の本の評価は低いものと位置づけられています。
↓
もう廃刊になっているみたいですね。
このアンチ本が出版されたとき、感謝の気持ちでいっぱいでした。というのもアンチ本の著者にとって私は無視できない存在だったわけですから。
人から無関心でいられるほうがよっぽどつらいですよ。もちろん私も叩かれるのはイヤですし、ノミの心臓なのでかんべんしていただきたい。
しかしながら、出る杭にならないと稼げなくなるのは自らの体験から学んでいます。
この記事を読んでくださる方には、埋もれた人材になって欲しくないです。自分をじっくり見つめ直し、自分の力をもっと使いこなして出過ぎた杭になっていきましょう!
自分の見つめ直し完全マニュアル【無料】
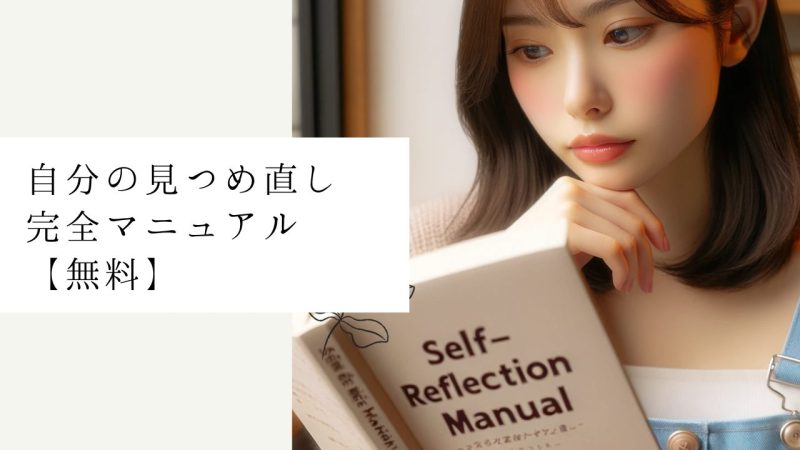
出る杭になってもブレずに行動するためには自分をより深く理解することが必要です。
自己理解が深まると、自分自身の真の強みや弱みを知ることができ、それにより自信を持って行動することが可能になります。
また、他人からの批判に直面しても、自分の核となる価値観や信念を保ち続けることができます。
そこで、本気で自分を理解しようとする人に役立つマニュアル「自分の見つめ直しマニュアル」が完成しました。
制作に10年の歳月をかけた逸品。以下、充実の内容です。
- 自分の棚卸しに使える100の質問シート:自己認識を深めるための質問が満載です。
- 自己肯定感を高めるための100の質問シート:自分自身の価値を認識し、自尊心を強化する質問を集めました。
- 今の仕事合う?合わないチェックリスト:現在の職業が自分に適しているかを評価するための具体的なポイントを提供します。
- やる気ペンタゴンチャート:モチベーションを高めるための要素を分析し、やる気を引き出すための戦略に役立ちます。
- ときめきのツボワークシート:情熱を見つけ、それを日々の生活や仕事に活かすためのシートです。
私の個人セッション(月々3万円)や講座の受講生たちを指導する際に使っているノウハウから厳選しました。配布を開始したその日、300人以上から申し込みがあったものです。
但し、無料配布をいつまで続けるかわからないです。すいません。必要な人は、今すぐ入手して保存をおすすめします。
下記フォームにお名前とメールを入力するだけで入手できます。
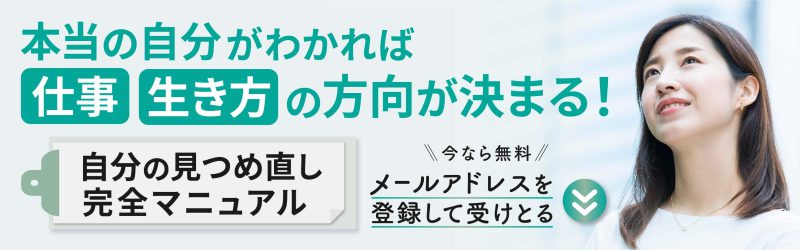
こちらにLINE登録していただくと、自分らしく生きるための耳寄りなお話も公開してます。ブログには書けないここだけの情報も配信しています。

私との直接のやりとりもできますよ
以上となります。
ではまた。







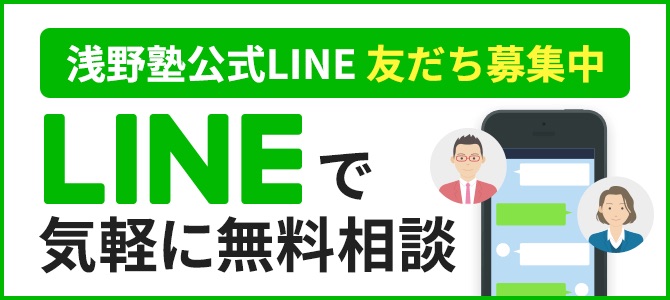



コメント