
キャリアプランが思いつかない女性は決して一人ではないのでご安心くださいね。
キャリアプランとは、自分の仕事人生の設計図のようなものです。今の仕事から将来どのような仕事をしたいか、そのために何を学び、どのようなスキルを身につけるかを考えることを言います。
この記事を書いている私は、現在まで15年間2000人余りの女性たちと共に、キャリアや生き方に関する問題を解決してきました。
この問題は、成功している多くの女性にも共通する深刻な悩みなのです。
何が難しいかと言えば、女性のキャリアは結婚、出産、育児といったライフイベントに直結していること。そして、「生活するためだけに働く」といった単純な働き方が、多くの女性にマッチしないことです。
最後まで読むと、行動プランを描くヒントをつかめます。さらに、効果的なツールも紹介していますので、ぜひ最後までお付き合いくださいね。
- 記事を書いている人の専門性と実績
経歴:
新卒8ヶ月での挫折退職から再出発。26年の会社員経験(10年は複業)を経て起業。現在は個性を活かす道を拓く会社を経営。
専門:
キャリアプランが思いつかない女性を含む、2000人超の女性指導実績。本当の強みを発見し、人生を新たな方向へ導くプロ。やりがいのある転職から起業まで、前職や年齢を超えた女性の夢実現に定評。
メディア/著書:
日本経済新聞、日経WOMAN他多数掲載。著書「私はこの仕事が好き!自分の”強み”を活かして稼ぐ方法(大和出版)」
キャリアプランが思いつかない女性が多い理由
 朝起きて、なんとなく会社に行き、なんとなく仕事をこなす。このままでいいのかモヤモヤするけど、じゃあどうしたいのかと聞かれても答えられない。
朝起きて、なんとなく会社に行き、なんとなく仕事をこなす。このままでいいのかモヤモヤするけど、じゃあどうしたいのかと聞かれても答えられない。
こうした悩みを抱える女性は想像以上に多いですよ。統計データから見えてくる現実を確認してみましょう。
出産後も働き続ける女性は約7割。でも3割が退職する現実
国立社会保障・人口問題研究所「第16回出生動向基本調査」(2021年)によると、2015~2019年に第1子を出産した女性の就業率は69.5%に達しました。
育児休業制度が普及していることもあって、出産後も働き続ける女性は増えていますね。過去数十年の中でも高い数値です。
とは言え、依然として約3割の女性が出産した後に退職しているのが現実。
いいですか?
この数字が物語るのは、働き続けたいけど続けられずに葛藤を抱える女性が多いということですよ。
キャリアを考えるとき、先が見えにくいことが大きな悩みになっています。
男性の育休取得率は40.5%に上昇。でも家事育児の負担は依然として女性に
さらに突っ込んだお話をします。
厚生労働省「令和6年度 雇用均等基本調査」(2025年7月公表)によると、男性の育休取得率は40.5%に達し、過去最高を記録しました。
前年の30.1%から10.4ポイントの大幅な上昇です。急速に増加していますね。
この背景には、2022年に施行された「産後パパ育休」制度の定着があります。育休を取得した男性のうち約6割(60.6%)が産後パパ育休を利用しているのです。

これで万事解決!⋯となってませんよね。
育休の取得率が上がっているとはいえ、依然として家事・育児の負担は女性に偏っているという指摘も多いでしょう。
共働きの夫婦でお子さんが熱を出したとき、大抵は女性が会社を休んで看病しています。このときの不平不満を私は何度聞いてきたか数え切れないほどです。
職場の文化や時間的な制約の改革は、今後の課題とされていますね。
数字が語る、家庭とキャリアの「転機」
これらの公式統計から見えてくるのは、男女ともに育児と仕事の両立が進みつつある一方で、制度の利用や職場支援の格差が残る現実です。
女性は約7割が出産後も働き続け、男性は4割が育休を取得する時代へと移行しました。
とはいえ「働きたくても働けない」「休みたくても休めない」といった構造的な制約が依然根強く残っています。
小さな会社では、育休を取られてしまうと会社がまわらなくなってしまい、退職をすすめられた話もよく耳にします。
今後のキャリア計画では、家庭支援のあり方を重く見る必要があるでしょうね。
むずかしい問題です。
ライフイベントがキャリアに与える影響の大きさ
結婚、妊娠、出産、育児。これらのライフイベントは人生を豊かにする一方で、キャリアの方向性を大きく左右します。
特に男性と比べて、女性のキャリアはライフイベントの影響を受けやすい傾向があります。
「このタイミングで転職していいのか?」
「スキルアップの勉強を始めても、妊娠したら無駄になるのでは?」
「昇進を目指すべきか、ワークライフバランスを優先すべきか?」
こうした迷いが、キャリアプランを思いつかない原因の一つとなっていますね。
ロールモデル不足が招くキャリアの迷い
「こんな風に働きたい」と思える女性が身近にいないことも、大きな問題です。
特に、仕事と家庭を両立しながら活躍している女性管理職が少ない職場では、自分の未来像を描きにくい。
見本となる先輩がいないということは、手探りで前に進まねばならないということ。
どこに向かって進めばいいのかわからず、立ち止まってしまうのも無理はありませんね。
キャリアプランが思いつかない5つの原因
 キャリアプランが思いつかない原因は、多くの人に共通する悩みと、特に女性がぶつかりやすい問題があります。
キャリアプランが思いつかない原因は、多くの人に共通する悩みと、特に女性がぶつかりやすい問題があります。
以下に5つの主な原因を解説しましょう。
原因1. 自分のやりたいことがわからない
キャリアプランが思いつかない原因の1つ目は、そもそも自分のやりたいことがわからないこと。
自分の趣味や好きなことが、具体的な仕事のイメージに結びつかない。また、自分の得意なことが何なのかわからず、迷ってしまうこともあるでしょう。
たとえば、音楽が好きでも、音楽関係の仕事にどのようなものがあるのか具体的にイメージできない。だから進路を決められないというように。
ここで気づいて欲しいことがあります。やりたいという感情は、過去に経験していることか、知っていることの中からしか湧かないということ。
パンを作ったことがない人はパン作りをしてみたいと思えない。パン屋さんの存在すら知らなかったらパン屋さんで働きたいと思えないということです。
実際に行動してみる中で見えてくることのほうが多いのは、そのためですね。
原因2. 将来への不安が大きい
キャリアプランが思いつかない原因の2つ目は、将来への不安が大きいこと。
社会や経済の変化が速く、将来の予測が難しい。今の仕事が将来もあるかどうかわからず、キャリアプランを立てにくくなっています。
たとえば、AI技術の発展により、自分の仕事が将来なくなるかもしれないと心配になることもあるでしょう。
特に事務職や士業の人たちは戦々恐々としています。
5年後、10年後に社会がどう変化しているか想像もつかなくなってしまいました。将来への不安が大きくなるのも自然なことですね。
原因3. 選択肢が多すぎて迷う
キャリアプランが思いつかない原因の3つ目は、選択肢が多すぎて迷うこと。
インターネットの普及により、情報があふれています。そのため、かえって判断が難しくなっている。
また、興味のある分野が複数あって、どれを選ぶべきか決められないこともあるでしょう。
たとえば、料理も好きだし、接客もやってみたい、プログラミングも面白いと感じて、どの道に進むべきか悩んでしまう。
食べたいものを決めたいのに豊富なメニューを差し出されるとわからなくなるように、選択肢が多くなると迷いも大きくなるものなんです。
また、「どれか一つに絞らなければならない」という思い込みも、選択を難しくしています。
たとえば、料理好きを活かして栄養士の資格を取り食育の仕事をする、接客経験とプログラミングスキルを組み合わせてWebサービスの顧客サポートを担当するなど、複数の興味を組み合わせる道もあるんですけどね。
原因4. 家庭と仕事の両立に不安がある(特に女性)
キャリアプランが思いつかない原因の4つ目は、家庭と仕事の両立に不安があること。
結婚や出産後のキャリアを具体的にイメージすることはむずかしいものです。
育児と仕事をどのように両立させればいいのか、具体的な方法がわからず悩むことがあるでしょう。
この問題は、何十年も前からある問題であり、不治の病と似たような問題です。私たちがいくら頭をひねったところでサクッと解決できるようなものでもないんですよね。
子育てをしながらフルタイムで働き続けられるかどうか心配になることも多いです。
先ほど紹介した統計データのとおり、出産を機に約3割が退職している現実があります。
この数字を知っているからこそ、不安が大きくなるのかもしれませんね。
原因5. 周りの期待やプレッシャーが強い
キャリアプランが思いつかない原因の5つ目は、周りの期待やプレッシャーが強いこと。
親や社会の期待に応えなければならないと感じて、自分の本当にやりたいことを見失うことがあります。
また、周りの人と比べて焦ってしまい、冷静な判断ができなくなることもありますね。
たとえば、友人が次々と昇進していくのを見たり、結婚や出産しているところを見たりすれば自分も早く決断しなければと焦ってしまうことがあるでしょう。
私の塾の門を叩く女性の中には、会社からリーダーになるよう求められ始めているが、全く興味が湧かずに悩んでいる女性がいたりもします。
大切なのは、周りからどう期待されるかではなく、自分がどう思うかをしっかり考えることですね。
キャリアプランが思いつかない時に今すぐできる7つの解決策
 現在まで15年間さまざまな業界・業種で働く人たちのキャリアプランニングに関わり続けてきましたが、効果的だったものを選びました。一つ一つ試してみるといいでしょう。
現在まで15年間さまざまな業界・業種で働く人たちのキャリアプランニングに関わり続けてきましたが、効果的だったものを選びました。一つ一つ試してみるといいでしょう。
解決策1「大切なもの」をはっきりさせる
キャリアプランが思いつかないときに、まずやってみることの1番目は、自分にとって大切なもの(価値観)をはっきりさせることです。
たとえば、もしも「家庭と仕事のバランスが大切」と気づいたなら、それを実現できる職種や企業を選ぶきっかけになります。
「ご自身にとっての本当の成功とは何か?」を考えてみてください。それが「家庭との時間を確保すること」であれば、この価値観に合わせてキャリアプランを描けます。
いいですか?
社会人になると、多くの人が与えられた役割をこなすことに必死になり、自分の本当の価値観がわからなくなっています。
すぐ思いつかないのであれば、一日10分でもいいので自分にとって大切なものを書き出してみましょう。重複したものが出てくるので、それがヒントになります。
意識的に自分を見つめ直す時間を持たないと、日々の忙しさに流されてキャリアプランは永遠にできません。
実践例をご紹介します。
Aさん(32歳・営業職)は寝る前の10分に「今日嬉しかったこと」をメモしました。
3ヶ月後、「人の成長に対しての喜び」が繰り返し出てきたことに気づき、人材育成に関わるキャリアへ方向転換しました。
他の部署で働いている人に手を差し伸べたり、壁にぶつかって伸び悩んでいる同僚を励ましたり⋯そんなエピソードが数多く出てきました。
このように、感情が動く瞬間の積み重ねこそが、自分が本当に大切にしたいもののヒントになります。
価値観がわからなくなっている人は、以下を参考にどうぞ。
参考記事▶価値観の見つけ方完全ガイド|プロ直伝70の質問と実践ワーク

自分の人生です。先ずは周りがどうのではなく、自分がどう思うかをしっかり考えましょうね。
解決策2. 自分の強みに焦点を絞る
キャリアプランが思いつかないときに、やってみることの2番目は、自分の強みに焦点を絞ることです。
ストレスも少なくなるはずですのでキャリアの起点として申し分ないはずです。
たとえば、人とのコミュニケーションが得意な人は、人事や営業の仕事が合うかもしれない。
転職を考えている場合は、このような自分の強みを活かせる職種を探すことが重要です。
強みは方向性を見つける上で適切なルートの一つになります。
アクションステップの一つとして、
- 時間がすぐに経ってしまうこと
- よく褒められること。
- 他人の行動を見てイライラすること
- 周りの人は嫌がるが自分は平気なこと
- 話が止まらなくなること
そんな偏った資質を書き出してみるといいでしょう。これらは自分の強みの一つでもあり、その要素を仕事に取り入れると、より充実したキャリアを築く可能性が高まります。
私の講座を受講していた40代・エンジニアのKさんの例ですが、彼女は旅行のプランを考えるのが大好きな人でした。
学生時代から、友人・知人と旅行に行くとき率先して飛行機やホテルなどの手配をすべて彼女が行っていました。
計画したり準備したりするのが、旅行自体よりも楽しいと言うんですよね。
彼女は現在、旅行代理店に転職し、「この仕事は天職です。ずっとやっていたい」と言ってましたね。
Kさんの例のように、自分の強みに焦点を絞ることで、仕事に対する満足度が高まり、長期的なキャリアプランを描きやすくなるのです。
きちんと書き出していくと強みのヒントをつかめます。以下に関連記事があるので気になる方は参考にどうぞ。
参考記事▶自分の棚卸しガイド|強み迷子を解決する20の質問と実践方法
解決策3. 自分の弱みから突破口をつかむ
キャリアプランが思いつかないときに、やってみることの3番目は、自分の弱みから突破口をつかむことです。
強みが見つからずに悩んでいるときは、一度視点を変えて「弱み」に焦点を当ててみる。
たとえば、数字に弱いと感じるなら、会計や経理といった仕事は避けた方が良いかもしれませんね。
その代わりに、人と接する機会の多い仕事や、クリエイティブな発想が活かせる仕事が、ご自身に合う可能性があるかもしれませんよ。
また、弱みを客観的に理解できると、それを補完するような役割で力を発揮できることもあります。
たとえば、大勢の人をぐいぐい引っ張っていくのは自信がないと感じるなら、チームを支えるサポート役や補佐的なポジションで、その慎重さや気配りの能力が活かせるかもしれません。
いいですか?
たとえば、「繊細で傷つきやすい」という点は、一見すると弱みという影かもしれません。
しかし、それを裏返せば「相手の気持ちを細やかに察することができる」「仕事が丁寧でミスが少ない」という光。つまりかけがえのない強みになるのです。
このように、ご自身の弱みを「避ける」「補完する」、そして「強みに転換する」というさまざまな視点で捉えること。
それが、最適なキャリアプランを描くための突破口となります。
以下の記事も参考になるかと思います。
▶弱みを強みに変える7つの実践ガイド【成功事例から学べます】
解決策4. 理想のあり方をイメージする
キャリアプランが思いつかないときに、やってみることの4番目は、理想のあり方(理想像)をイメージすることです。
理想像と言うと、「立派な夢がないとダメなのかな」と、プレッシャーを感じてしまうかもしれませんね。
でも安心してください。
ここで大切なのは、どんな仕事に就くかではなく、どんな状態で毎日を過ごしていたいかから考えることです。これが、キャリアプランを描く大きなヒントになります。
一度、「数年後の理想のある一日」を想像してみましょう。
- 朝、どんな気持ちで目覚めていますか?
- どんな人とどんな会話をしていますか?
- 仕事をしているとき、どんな感情が心にありますか?(「ワクワク」「穏やか」「集中」など)
- 仕事終わりや休日は、どんなふうに過ごしていますか?
このように、仕事内容といった「点」ではなく、感情や過ごし方といった「状態」で捉えてみることです。
そうすると、ご自身が本当に大切にしたい価値観が見えてきます。
たとえば、Dさん(30歳・販売職)の例ですが、 彼女の理想は、まず「場所や時間にとらわれず、穏やかな気持ちで働いている自分」という「状態」でした。
その理想の「状態」を実現するための手段として、Webデザインというスキルがいいかもと思い、デザインスクールに通い始めてリモートワークを実現しました。
つまり、理想の「状態」が、進むべき方向を教えてくれる役割を果たしてくれるのです。
ちなみに私の今の仕事は、自分が働くことで誰かに喜んでもらいたい。そして働く時間やペースは自分でコントロールしたいという理想の「状態」によりたどり着いた仕事です。
まず理想のあり方をイメージすることで、そこへ向かうための具体的なキャリアプランが、自然と見つけやすくなります。
解決策5. 「憧れの人」からヒントをもらう
キャリアプランが思いつかないときに、やってみることの5番目は、「憧れの人」からヒントをもらうことです。
視点を外に向けて、「素敵だな」「こんな風になれたらな」と憧れる人を参考にしてみることです。
ここで重要なのは、その人自身になるのが目的ではない、ということ。 大切なのは、「なぜその人に惹かれるのか?」を深く掘り下げてみることです。
これが、自分自身の中に隠れた願望を見つけ出すヒントになります。
たとえば、身近な先輩、SNSで見かける活動家、あるいは歴史上の人物でもかまいません。 その人について、少し考えてみてください。
- その人のどんな部分に、心を動かされますか?
- 仕事のスタイルや、成果の出し方は?
- 持っている専門スキルや知識の深さは?
- 大切にしている価値観は?そのライフスタイルは?
「いいな」と感じるその理由こそが、心の奥にある「なりたい自分」の輪郭を教えてくれる、貴重なヒントなのです。
Fさん(32歳・事務職)の例ですが、 彼女は、好きなことで活躍しているフードコーディネーターに漠然と憧れていました。
そこで「なぜ惹かれるのか?」を分析すると、料理そのものというよりは、好きなことを通じて、自分の世界観を美しく表現している姿に心惹かれているのだと気づきました。
彼女にとっての「好きなこと」はインテリアや整理収納。そこから、住空間のアドバイザーという具体的な目標を見つけ、学び始めることができました。
憧れの人は、理想を映し出す鏡のようなものです。 その鏡をじっと観察することで、ぼんやりとしていた進むべき道が、はっきりと見えてくるかもしれませんよ。
解決策6. 自己肯定感を高める
キャリアプランが思いつかないときに、やってみることの6番目は、自己肯定感を高めることです。
自己肯定感が低いと、自己評価も低くなり、自分を低く見積もってしまいがち。この状態ではキャリアプランを描くことなんてできません。
しかし、「自分に誇れるような成功体験なんてない」と思うかもしれませんね。
逆に、たった一度の失敗が、他のたくさんの成功体験を覆い隠してしまうこともあります。
たとえば、これまで9回のスピーチが上手くいっていても、たった一度のミスを悔やみ続けて、「自分はスピーチが苦手」と思い込んでしまうようなケースです。
いいですか?
多くの人は、そもそも自分の成功体験を自覚していなかったり、失敗体験によってその記憶が封印されてしまうことがあります。
これは「ネガティブ・バイアス」と呼ばれ、自己肯定感を高める作業の妨げになることも。
この問題を解決するには、さまざまな視点からの質問を用意し、自分に問いかけることが効果的です。
そこで、「自己肯定感を高める100の質問集」を作成しました。これを使えば、自分自身との対話をこれまでにないレベルで深められるでしょう。
※こちらは、読者さんが講座に持参された質問集の実際の画像です。ご自身の振り返りにしっかり活用されていました。
↓

有料にするか迷いましたが、悩まれている人が大変多いためひと先ず無料で配布します。
但し、いつまで無料で配布するかわかりません。必要と思う人は今すぐ入手して保存をおすすめします。
下記からどうぞ。
自己肯定感を高めることは、キャリアプランを考える上で重要な一歩。この質問集を活用して、自分自身をより深く理解し、自信を持ってキャリアを切り開いていきましょう。
解決策7. 冷静な自己分析をする
キャリアプランが思いつかないときに、やってみることの7番目は、感情や他人の意見に流されず、冷静に自己分析を行うことです。
一旦感情や周りの意見から離れて、冷静に「本当の自分」を分析することです。 今の自分と対話することで、次の一歩を決めるブレない土台を作りあげます。
私の講座にいらした、Bさん(40代・経理)の例をご紹介しますね。 彼女は、旦那さまが経営する農業法人で、経理や総務の仕事を手伝っていました。
自己分析を進める中で、彼女は一つの発見をします。
農業という分野は好き。でも、本当に心がワクワクするのは、帳簿の数字を合わせることよりも、自分たちの作ったもので、お客さまが喜ぶ顔を直接見ることだったのです。
この気づきが、彼女の転機となりました。 Bさんは、旦那さまの会社とは別に、自分で育てた有機野菜を使い、お客さまに直接届けられる加工品を作る、という新しい活動を始める決心をしました。
いいですか?
この例のよう、本当にやりたいことは、今担当している役割や業務のすぐ隣に隠れているのかもしれませんよ。
経理という役割の中に、「誰かの役に立ちたい」という本当の願いが隠れている。 営業という業務の中に、「人と深く信頼関係を築きたい」という本当の喜びが隠れている。
冷静な自己分析は、この隠れた本音を見つけ出すための、とても大切な時間です。
今の役割の奥にある、ご自身の本当の想いを探ることで、心から納得できるキャリアプランが見えてきます
下記に自己分析についてまとめた記事がありますので参考にどうぞ。
▶自分を知る方法|専門家が監修!自分を知り尽くす10のヒント
| 解決策 | 要点 |
|---|---|
| 1. 「大切なもの」をはっきりさせる | 自分の価値観を明確にし、キャリア選択のブレない軸を作る |
| 2. 自分の強みに焦点を絞る | 強みを活かせる仕事を選ぶことで、満足度が高まり、長期的なプランを描きやすくなる |
| 3. 自分の弱みから突破口をつかむ | 弱みを「避ける」「補完する」「強みに転換する」という視点でキャリアの突破口にする |
| 4. 理想のあり方をイメージする | 「どんな仕事か」ではなく「どんな状態で過ごしたいか」から考え、進むべき方向性を見つける |
| 5. 「憧れの人」からヒントをもらう | 「なぜその人に惹かれるのか」を分析し、自分の隠れた願望や「なりたい自分」を発見する |
| 6. 自己肯定感を高める | 自分の価値を再確認し、前向きなキャリアプランを描くための土台を整える |
| 7. 冷静な自己分析をする | 今の役割の奥にある「本当の想い」を見つけ出し、心から納得できるプランの土台を作る |
年代別に考えるキャリアプランのヒント
 キャリアプランの考え方は、年代によって少しずつ変化します。
キャリアプランの考え方は、年代によって少しずつ変化します。
それは、それぞれのステージで見える景色や、大切にしたいことが変わっていくからです。
ここでは、20代から50代まで、各年代に合わせたキャリアプランのヒントをお伝えしますね。
20代:可能性を広げる「自分データ」を収集する時期
20代は、これからのキャリアの土台を築く、とても大切な時期。
この頃、「自分は何者なのだろう」と、答えを探して焦りを感じることがあるかもしれませんね。
でも、心配しなくて大丈夫ですよ。
社会人としての経験がまだ浅いこの時期は、まだ何者でもなくて当たり前です。
だからこそ、この時期に大切なのは、内側で答えを探し続けることよりも、外の世界でひとつでも多くの「自分データ」を集めること。
いわば、「自分の取り扱い説明書」を作るための期間と捉える。
一つの仕事に絞り込むよりも、まずは幅広く経験してみるのがおすすめです。
さまざまな業務に挑戦する中で、「これは心地よいな」「これは少し苦手かも」と感じる、ご自身の心の動きを丁寧に観察してみてください。
その一つひとつが、30代以降のキャリアを支える、ご自身だけの基準になります。
また、基本的なマナー・ビジネススキルや専門知識など、どの道に進んでも役立つ力を磨いておくことも大切です。
20代は、未経験の分野にも挑戦しやすい貴重な時期。興味のアンテナが向くものがあれば、結果にこだわらずお試しの一歩を踏み出してみましょう。
30代:ライフプランと両立させる「優先順位」を決める時期
30代は、仕事での責任と、結婚や出産といったライフイベントが重なりやすい時期です。
これまで多くのご相談をお受けしてきて感じるのは、この時期の女性は「すべてひとりで完璧にこなさなければ」と、ご自身を追い詰めてしまいがちということです。
ここで大切なのは、完璧ではなく、納得を目指すという視点です。
「今は育児に集中する」「この2年間は専門性を高める」というように、人生の季節の移ろいごとに、しなやかに優先順位を変えていく。
そのメリハリが、長い目で見るとご自身を助けてくれますよ。
出産後も約7割の女性が働き続ける現代。
会社の制度や周りのサポートを上手に活用しながら、ご自身のペースでキャリアを築いていきましょう。
40代:専門性を深め「どう貢献するか」を確立する時期
40代は、20代、30代で積み重ねてきた経験やスキルが、一つの「かたち」になる時期です。
この時期に意識したいのは、自分ならではの貢献は何かをはっきりすること。
それは、管理職という「役職」だけを指すのではありません。
チームをまとめるリーダーシップかもしれませんし、特定の分野で誰にも負けない専門知識かもしれません。あるいは、後輩を温かく育てる力かもしれません。
要はなんでもいい。
大切なのは、役職や肩書きではなく、「自分は、どう周りに貢献し、喜んでもらいたいか」という視点です。
ご自身の価値観に合った貢献のスタイルを見つけることが、この先のキャリアを、より豊かで確かなものにしていきます。
営業事務のHさんの例ですが、「営業担当者がもっと働きやすくなればいいのに」と感じ、営業担当者同士の情報共有の仕組みを徹底的に改善しました。
役職は変わりませんが、彼女の貢献によって部署の残業時間が大幅に減り、今では「Hさんがいないと仕事が回らない」と言われるほどの信頼を得ていますよ。
また、親の介護といった問題も現実味を帯びてくる頃。早めに情報収集を始めるなど、備えておくことも大切です。
50代:経験を統合し「次の章」をデザインする時期
50代は、これまでの人生で得たすべての経験を統合し、キャリアの「次の章」をデザインする時期です。
子育てが一段落し、自分のために使える時間が増える方も多いでしょう。
ここで考えるべきは、「定年後どうするか」という守りの視点だけではありません。
むしろ、「ここから、どんな人生を創造していこうか」と、未来を描く視点を持つことが大切になります。
会社員として培った経験を活かしてコンサルタントになる。若い頃に夢見た資格の勉強を始める。地域活動で新しい役割を見つける。選択肢は、思っている以上にたくさんあります。
年齢を重ねたからこそ見える景色があり、できる貢献があります。
これまでの経験という財産を手に、ご自身が本当にやりたかったことに、もう一度挑戦してみませんか。
自分の理想のキャリア診断 – 5分でわかる仕事の価値観テスト
 これらの7つの方法を試してみる前に、まずは自分の価値観を知ることから始めてみましょう。以下の簡単な診断テストで、あなたの仕事に対する価値観を確認できます。
これらの7つの方法を試してみる前に、まずは自分の価値観を知ることから始めてみましょう。以下の簡単な診断テストで、あなたの仕事に対する価値観を確認できます。
自分の理想のキャリア診断 – 5分でわかる仕事の価値観テスト以下の質問に「はい」か「いいえ」で答えてください。全ての質問に回答後、「結果を見る」ボタンをクリックしてください。
この診断結果を参考に、上記の7つの方法を自分に合わせて実践していくことで、より効果的にキャリアプランを立てることができるでしょう。
一番最初に取るべきアクション【必読】

キャリアプランが思いつかない女性が一番最初に取るべきアクションは、何より先に「自分の強みを見つける」ことです。
このステップは、何を目指すべきかを明確にする第一歩ですが、注意が必要です。
過去の経験や成果、フィードバック、趣味や特技などを振り返り、自分が持っているスキルや特質をリストアップする作業は大切です。
しかし、この過程で失敗するケースが多発しているのが現状。
なぜなら、女性専門に行っている人が少なく、世の中には誤った情報や、実績のないカウンセラーや相談員が多く存在するからです。
そのため、情報の信憑性とそのソースをしっかり確認することが大切です。
自己分析で失敗する3つのパターン
多くの女性が自己分析で失敗してしまうパターンがあります。これを知っておくことで、無駄な時間を使わずに済むでしょう。
パターン1:一般的な自己分析ツールに頼りすぎる
市販の自己分析本やWebの診断ツールは便利ですが、それだけでは不十分です。なぜなら、これらのツールは万人向けに作られているから。
女性特有のライフイベントや、キャリアの中断と再開といった要素は、ほとんど考慮されていません。
パターン2:ネガティブ・バイアスに囚われる
先ほども触れましたが、人は失敗体験を強く記憶する傾向があります。
「あのとき失敗した」「うまくいかなかった」という記憶が強すぎて、成功体験が見えなくなってしまうのです。
これでは、自分の強みを見つけることはできません。
パターン3:一人で抱え込んでしまう
自己分析は一人でやるものだと思い込んでいませんか?
他者からのフィードバックがあってこそ、自分の本当の強みが見えてきます。一人で考え続けても、同じ思考パターンから抜け出せないのです。
なぜ専門家のサポートが必要なのか
ここで正直にお伝えします。
キャリアプランを一人で考えるのは、とても難しいことです。特に、女性のキャリアは変数が多く、一筋縄ではいきません。
専門家のサポートが必要な理由は、以下の3つです。
理由1:客観的な視点が得られる
自分では気づかない強みや可能性を、第三者の視点から指摘してもらえます。
「そんな見方があったのか」という発見が、キャリアの方向性を決める決め手になることも多いのです。
理由2:女性特有の課題に精通している
結婚、出産、育児、介護。これらのライフイベントを考慮したキャリアプランを立てるには、女性のキャリアに特化した専門家のアドバイスが効果的です。
男女混合のキャリア支援では、この部分が手薄になりがちです。
理由3:実例を知っている
「こういう状況から、こうやってキャリアを築いた人がいる」という実例を知っていることは、大きな力になります。
道しるべとなる事例があれば、自分の未来もイメージしやすくなるでしょう。
信頼できる専門家の選び方
では、どのような専門家を選べばいいのでしょうか。以下のポイントを参考にしてください。
チェックポイント1:女性専門の指導実績があるか
女性のキャリア支援を何年やっているか、何人の女性を支援してきたか。具体的な数字を確認しましょう。
曖昧な表現しかない場合は、実績が少ない可能性があります。
チェックポイント2:成功事例が具体的に示されているか
「多くの人が成功しています」という抽象的な表現ではなく、「〇〇さんは△△という状況から、□□というキャリアを実現しました」という具体例があるか。
実際の事例があるということは、ノウハウが蓄積されている証拠です。
チェックポイント3:一方的なアドバイスではなく、対話を重視しているか
「あなたはこうすべき」と決めつけるのではなく、対話の中からあなた自身が答えを見つけられるようサポートしてくれるか。
押し付けではなく、引き出してくれる専門家を選びましょう。
チェックポイント4:アフターフォローがあるか
一度の相談で終わりではなく、継続的にサポートしてくれる体制があるか。
キャリアは長期戦です。その時々の状況に応じたアドバイスをもらえる環境が理想的です。
手前みそで恐縮ですが、私の運営する浅野塾は多くの人に実績をもっており、確かな指導が受けられる場として知られています。
大きな宣伝はしていませんが、全国から受講生が集まっているのが特徴です。本質的なスキルや知識を身につけられる環境が整っているのです。
自分の強みを明確にしつつ、信頼できる情報と指導に基づいて行動することが、その後のキャリアプランを考える土台となります。
それが明確になれば、次に進む方向が見えてくる可能性が高くなり、不安や迷いも少なくなるでしょう。
キャリアプランを決めた女性の体験動画

キャリアプランを決めることができた女性たちの体験談をインタビューし、いくつかセレクトしました。
私の講座の修了生たちの感想ですが、自分のキャリアについてどのような迷いや不安があったか語られています。参考にどうぞ。
ロールモデルがいない時はどうする?3つの対処法
 「こんな風に働きたい」と思える女性が身近にいない。これは、多くの女性が抱える悩みの一つです。
「こんな風に働きたい」と思える女性が身近にいない。これは、多くの女性が抱える悩みの一つです。
特に、管理職の女性が少ない職場、育児と仕事を両立している先輩がいない環境では、自分の未来像を描くことが難しくなります。
しかし、ロールモデルがいないからといって、諦める必要はありません。ここでは、ロールモデルがいない時の3つの対処法を紹介します。
社内でロールモデルを探す3つのポイント
まずは、社内で探してみましょう。「理想の人がいない」と思っていても、見方を変えると見つかるかもしれません。
ポイント1:完璧なロールモデルを求めない
すべてが理想的な人はいません。「仕事の進め方は参考になる」「家庭との両立の仕方が素敵」というように、部分的に学べる人を探しましょう。
一人の人からすべてを学ぼうとするのではなく、複数の人のいいところを取り入れるのです。
ポイント2:直属の上司以外にも目を向ける
他部署の先輩、別拠点の社員、協力会社の人。視野を広げると、学べる人は意外と多いものです。
社内報や社内SNSをチェックして、活躍している女性社員を探してみるのもいいでしょう。
ポイント3:男性からも学ぶ
女性のロールモデルにこだわる必要はありません。仕事の進め方、時間管理術、コミュニケーション方法など、性別に関係なく学べることはたくさんあります。
「この人のこの部分は取り入れたい」という視点で見てみましょう。
SNSやコミュニティで理想の働き方を見つける方法
社内にロールモデルがいない場合は、外に目を向けましょう。今の時代、SNSやオンラインコミュニティを通じて、さまざまな働き方をしている女性と出会えます。
方法1:LinkedInやTwitterで情報収集
キャリアに関する発信をしている女性をフォローしてみましょう。彼女たちの日々の投稿から、働き方のヒントが得られます。
特に、自分と似た状況(同じ業界、同じ年代、同じライフステージ)の人を見つけると参考になるでしょう。
方法2:オンラインコミュニティに参加
女性のキャリアをテーマにしたコミュニティがたくさんあります。
そこでは、悩みを共有したり、先輩からアドバイスをもらったりできます。同じような悩みを持つ仲間がいるだけでも、心強いものです。
方法3:オンラインイベントやセミナーに参加
キャリアをテーマにしたイベントやセミナーには、多様な働き方をしている女性が集まります。
そこで出会った人と繋がりを持つことで、新しい視点が得られるでしょう。
複数のロールモデルから「いいとこ取り」する考え方
ここで大切な気づきをお伝えします。
ロールモデルは、一人である必要はありません。むしろ、複数のロールモデルを持つことのほうが効果的です。
一人の人の働き方をそっくりそのまま真似することは不可能だからです。
環境も、能力も、家庭の状況も、すべてが異なるのですからね。
それよりも、「Aさんの時間管理術」「Bさんの家事の工夫」「Cさんの専門性の高め方」というように、いいところを組み合わせるのです。
これを「ハイブリッド型ロールモデル」と呼んでいます。
自分なりの働き方を作り上げるには、このような柔軟な考え方が必要です。
画像を表示完璧なロールモデルを探すのではなく、いいとこ取りをする。これが、現実的なアプローチですよ。
キャリアプランはなくてもいい【朗報】

ここまで書いておきながらなんですが、キャリアプランはそこまでこだわる必要はないと思っています。
冒頭でも少し触れましたが、女性の場合は出産・育児・旦那さんの性格や経済状況、場合によっては親の介護問題など不確定要素が多く、計画どおりに進むことが少ないからです。
むしろ、明確にキャリアプランを決めてしまうとその通りにならなかったときの失望が大きい可能性も含んでいます。
計画どおりにいかないのが当たり前
私が2000人以上の女性を見てきて感じるのは、「計画どおりにキャリアを歩んだ人は、ほぼいない」ということです。
予期せぬ転勤、予想外の妊娠、突然の親の介護、会社の倒産、自分の病気。人生には、予測できない出来事がたくさん起こります。
だからこそ、ガチガチに計画を立てるよりも、変化に対応できる柔軟性を持つことのほうが大切なのです。
大切なのは「方向性」と「軸」
キャリアプランがなくてもいいと言いましたが、何も考えなくていいわけではありません。
必要なのは、細かい計画ではなく、「方向性」と「軸」です。
細かく「5年後にはこの役職」と決めるのではなく、「こんな風に働いていたい」という大きな方向性があればいいのです。
この軸がしっかりしていれば、予期せぬ出来事が起きたときも、判断に迷いません。
変化に対応できる力をつける
このため、あらかじめ緻密なキャリアプランを作るよりも、変化に柔軟に対応できるスキルを持つことが重要です。しかし、情報過多で複雑な現代では、一筋縄ではいきません。
おすすめするのは伴走者をつけることです。あなたの性格を熟知し、適切なカウンセリングやアドバイスを同時に行える専門家に依頼するといいでしょう。
私はセミナーを行うと同時に、アフターフォローとして希望者には個人顧問としてサポートしています。
5年以上このサービスを続けてわかったことがあります。それは、ガイドがあれば、その時々の状況に合わせて適切なプラン変更ができるということです。これにより、ムダな動きを最小限に抑えることができます。

一度じっくりどうすべきか考えてみるといいですよ。
何から始めればいいかわからない人へ

キャリアプランがまだ定まっていないけど、とりあえずできることを今すぐ始めたいという方は、自分の特性を正確につかんでおくといいでしょう。
自己理解が深まることで、将来の方向性が見えてくる可能性が高いからです。そのために必要なものをぎゅっと詰め込んだ「自分の見つめ直し完全マニュアル」をご用意しました。
このマニュアルは、これまでの人生を振り返り、自分の特性を体系的に整理して分かりやすく理解することができるのです。
制作に10年の歳月をかけた逸品。以下、充実の内容です。
- 自分の棚卸しに使える100の質問シート:自分自身を深く理解するための問いかけを提供し、長所や可能性を探るのに役立ちます。
- 自己肯定感を高めるための100の質問シート:自信を持って前向きに生きるための支援をします。
- 今の仕事合う?合わないチェックリスト:現在の職場環境が自分に合っているか評価するのに役立ちます。
- やる気ペンタゴンチャート:モチベーションを高め、行動を促すためのツールです。
- ときめきのツボワークシート:自分の情熱や興味が何にあるのかを探るのに役立ちます。
私の個人セッション(月々3万円)や講座の受講生たちを指導する際に使っているノウハウから厳選しました。配布を開始したその日、300人以上から申し込みがあったものです。
ただし、無料配布をいつまで続けるかわからないです。すいません。必要な人は、今すぐ入手して保存をおすすめします。
下記フォームにお名前とメールを入力するだけで入手できます。
こちらにLINE登録していただくと、自分らしく生きるための耳寄りなお話も公開してます。ブログには書けないここだけの情報も配信しています。

私との直接のやりとりもできますよ
最後に筆者からの大切なメッセージ

キャリアプランの先にある本当の自分を見つけませんか?

自分力活用講座
この記事で紹介した方法を試す中で、ご自身の大切なものや強みの輪郭が、少し見えてきたかもしれませんね。
しかし、キャリアプランとは、無理に作り出すものではなく、ご自身の核となる力、つまり「自分力」が明らかになることで、自然と見えてくるものです。
「自分力」とは、ただ「やりたいこと」を見つける力ではありません。 自分だけの価値を発見し、人の役に立ちながら、心からの情熱と安心できる収入を両立させていく力のことです。
もし、今、 「自分の中には、まだ気づいていない可能性がある気がする」 「表面的なノウハウではなく、もっと根本から自分を見つめ直したい」 そう感じているなら、一度、その「自分力」を引き出すための時間を作ってみませんか?
私が主宰する「自分力活用講座」の体験入門コースでは、女性に特化した独自のプログラムを通じ、AIや自己分析本では決して見つからない、自分だけの価値を発見するお手伝いをします。
「何がしたいかわからない」という霧が晴れ、「これが私の道かもしれない」という確かな一歩が見える。そんな体験をご用意しています。
ご縁があれば、共に、キャリアの道を探っていけたらと思います。最後までお読みいただきありがとうございます。
ではまた。
魂の女性成長支援・浅野塾代表 浅野ヨシオ

浅野ヨシオ:
女性成長支援コンサルタント。
魂の女性成長支援・浅野塾 代表。
2007年よりビジネスパーソンや出版希望者を対象とした、自分の強みを発見し唯一無二のブランドを作る講師として活動。ハイキャリアの女性たちでも自分の能力がわからず強い自信を持てずにいることを知る。
2011年、女性成長支援の講座を起ち上げ、幼少期から現在までの人生史を平均200時間以上かけて深掘りする指導に定評がある。
通算15年2000人超の女性専門指導の経験により、心を縛る足かせをはずし、自分にとっての幸せを追求する自己実現プログラムを多数構築する。
著書に「私はこの仕事が好き!自分の強みを活かして稼ぐ方法(大和出版)」がある。
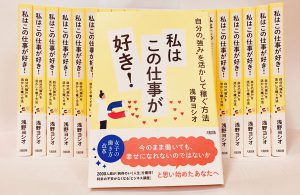
◎メディア実績:日本経済新聞/日経WOMAN/PRESIDENTほか多数
◎講演実績:横浜市経済観光局/多摩大学/NPO法人Woman’sサポート/自由大学/青森商工会連合会/天狼院書店/(株)スクー/ほか多数

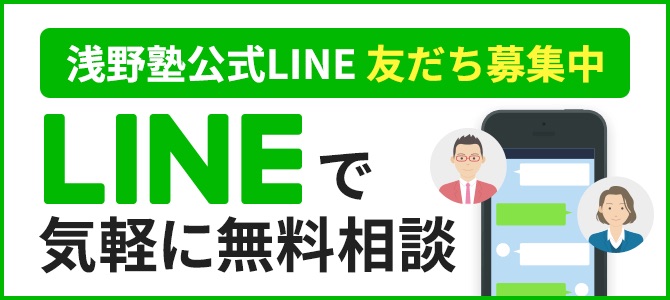


コメント