

毎回決意を新たにして始めるのに、いつの間にか挫折してしまう。これは多くの人が抱える共通の悩みです。
でも、安心してください。継続できないのは、意志が弱いからではありません。誰もが経験する理由があるのです。運動や勉強、資格の学習など、どんな分野でも同じことが言えます。
この記事では、継続できない人によくある特徴やその理由を解説し、誰でも実践できる具体的な改善法をお伝えします。
全ての内容は、実践的な方法ばかり。最後まで読むことで、自分に合う無理のない継続法が見つかるはずです。
追伸:本文の最後に素敵なマニュアルのプレゼントをご用意しています。
- 記事を書いている人の専門性と実績
経歴:
新卒8ヶ月での挫折退職から再出発。26年の会社員経験(10年は複業)を経て起業。現在は個性を活かす道を拓く会社を経営。
専門:
継続できないで悩む人を含む、2000人超の女性指導実績。本当の強みを発見し、人生を新たな方向へ導くプロ。やりがいのある転職から起業まで、前職や年齢を超えた女性の夢実現に定評。
メディア/著書:
日本経済新聞、日経WOMAN他多数掲載。著書「私はこの仕事が好き!自分の”強み”を活かして稼ぐ方法(大和出版)」
継続できない人の7つの特徴と理由
 継続できない人にはいくつか共通する特徴があり、知らなければ自分に合う改善法を選びにくくなります。そこで先ず、継続できない人に共通する7つの特徴とその理由を解説します。
継続できない人にはいくつか共通する特徴があり、知らなければ自分に合う改善法を選びにくくなります。そこで先ず、継続できない人に共通する7つの特徴とその理由を解説します。
1. 「やる気」頼みになっている
継続できない人の1つ目の特徴は、やる気頼みになっていて、続けられずに失敗しやすいことです。続かなくなる理由はやる気は気分によって変動しやすく、一定ではないからです。
「やる気があるときにやる」という考え方だと、少し気分が乗らないだけで手をつけられず、次第に先延ばしになり、気づけば続けられなくなってしまいます。
2. 完璧を求めすぎる
継続できない人の2つ目の特徴は、完璧を目指しすぎて挫折することです。
続かなくなる理由は「完璧にできなければ意味がない」と思い込み、小さな失敗やミスがあると、それだけで一気にやる気を失ってしまうからです。
完璧を求めることでプレッシャーが大きくなり、途中で「もうダメだ」と諦めてしまいやすくなります。
3. 目的が曖昧でゴールがわからない
継続できない人の3つ目の特徴は、目的・目標がはっきりしないことです。
続かなくなる理由は具体的なゴールが決まっていないと、何をどこまでやればいいのか分からなくなり、行動の指針がなくなるからです。
「とりあえず始める」という形では、途中で目的を見失い、「このまま続けても意味があるのか」と疑問に思ってしまいやすくなります。
4. 継続できる環境を整えていない
継続できない人の4つ目の特徴は、続けやすい環境を作れていないことです。
続かなくなる理由は環境の影響を強く受けることで、自分の意志だけで行動をコントロールするのが難しくなるからです。
たとえば、集中したいのに周囲が騒がしかったり、誘惑の多い環境だったりすると、やるべきことを後回しにしてしまい、継続が困難になります。
5. やる気を保ち続ける工夫がない
継続できない人の5つ目の特徴は、続ける工夫をしていないことです。
続かなくなる理由は、単調な作業を繰り返すだけでは飽きてしまい、やる気を保てなくなるからです。
最初は新鮮な気持ちで取り組めても、次第に「つまらない」「面倒くさい」と感じるようになり、続けることが苦痛に思えてしまいます。
6. 生理的なブレーキに負けてしまう
継続できない人の6つ目の特徴は、体の変化に適応できないことです。
続かなくなる理由は、人間の体には「ホメオスタシス(恒常性)」と呼ばれる機能があり、変化を避けようとする働きがあるからです。
新しい習慣を始めると、体や脳が「いつもと違う」と感じて抵抗し、元の状態に戻そうとするため、途中で続けるのが難しくなります。
7. 孤軍奮闘してしまう
継続できない人の7つ目の特徴は、孤軍奮闘(一人で頑張りすぎること)してしまうことです。
続かなくなる理由は、周囲に相談できる人がいないと、モチベーションを維持するのが難しくなるからです。
誰にも話せないまま続けていると、不安や迷いが生まれやすくなり、「これでいいのか」と疑問を感じ、途中で諦めてしまうことが多くなります。
| 特徴 | 継続できない理由 | 改善のポイント |
|---|---|---|
| やる気頼み | 気分や体調で変動しやすく、一定のモチベーションを保てない | やる気に頼らず、決まった時間に習慣化する |
| 完璧主義 | 些細なミスで挫折し、やる気を失ってしまう | 80%でOKという許容範囲を設定する |
| 目的の曖昧さ | 明確なゴールがなく、行動の指針が定まらない | 具体的で測定可能な目標を設定する |
| 環境の問題 | 周囲の環境に影響され、意志だけでは継続困難 | 継続しやすい環境を意識的にデザインする |
| 工夫の欠如 | 単調な繰り返しで飽きやすく、モチベーション低下 | 小さな変化や新しい挑戦を取り入れる |
| 生理的抵抗 | 体が変化を嫌うホメオスタシスが働く | 少しずつ段階的に変化を加えていく |
| 孤独な戦い | 相談相手がおらず、不安や迷いが募る | 仲間や指導者のサポートを受ける |
今すぐ始動!継続するための改善法10選
 大事なことなので繰り返し言います。継続できないのは、意志の弱さが原因ではありません。「続く仕組み」が作れていないからです。
大事なことなので繰り返し言います。継続できないのは、意志の弱さが原因ではありません。「続く仕組み」が作れていないからです。
やる気だけに頼らず、無理なく続けるための実践的な改善法を10個ご紹介します。
1. 規則的な習慣にする
継続するための改善法の1つ目は、規則的に行うことです。
続かない理由の多くは、やるべきことのタイミングが決まっていないため、意志や気分に左右されてしまうことにあります。
「寝る前に○○する」「朝起きたら○○する」「12時になったら○○する」と、特定の時間や習慣と結びつけることで、「やるかどうか考える時間」が不要になり、続けやすくなります。
さらに、決まった流れ(ルーティン)を作ることで、行動のハードルが下がり、自然と継続できるようになります。
2. 完璧を求めず、ユルく取り組む
継続するための改善法の2つ目は、完璧を求めず柔軟に取り組むことです。
途中で挫折する原因のひとつは、「毎日完璧にやらなければならない」というプレッシャーです。
「たまにはサボる日があってもいい」「うまくいかないのが普通」と考えることで、精神的な負担が減り、長期的に続けやすくなります。
完璧を目指しすぎると、小さなミスや失敗で一気にやる気を失ってしまうため、肩の力を抜くことが大切です。
3. 簡単なことから始める
継続するための改善法の3つ目は、最初のハードルを低くすることです。挫折する原因のひとつは、最初から難易度の高い目標を設定してしまうことにあります。
たとえば、「運動を始めよう」と決意して、いきなり毎日5キロ走ると、体力的にも精神的にもきつくなり、続きません。
まずは「近所を5分歩く」くらいの簡単なことから始め、成功体験を積み重ねることで、次のステップに進みやすくなります。
4. 飽きを予防する
継続するための改善法の4つ目は、飽きないように工夫することです。
途中でやめてしまう理由の一つに、「やることに慣れてしまい、新鮮味がなくなる」という問題があります。やり方を変えたり、目標を小刻みに設定することで、変化を取り入れながら続けることができます。
たとえば、ブログを書く場合でも、毎回同じスタイルで書くのではなく、視点を変えたり新しいテーマに挑戦することで、飽きることなく継続できます。
5. 目的を常に思い出す
継続するための改善法の5つ目は、目的を明確にし、常に意識することです。
続かなくなる理由のひとつは、「継続すること自体が目的になってしまうこと」です。
たとえば、「貯金をする」という目標も、家を買うためなら続けやすいですが、「ただ貯金を続けること」が目的になると、苦しくなりやめたくなります。
継続の先にある「本来の目的」を忘れないよう、スマホの待ち受けやデスクのメモなど、常に目につく場所に書いておくと効果的です。
6. 続けやすい環境を整える
継続するための改善法の6つ目は、環境を整えることです。
続かない理由のひとつは、「やろうとする環境が整っていないこと」です。
たとえば、勉強を続けたいのに周囲がうるさい環境だと集中できず、結果としてやらなくなってしまいます。
机の上を片付ける、必要な道具をすぐに使えるようにする、作業しやすいスペースを確保するなど、環境を整えることで、効果的に習慣化しやすくなります。
7. 感情に振り回されず淡々と続ける
継続するための改善法の7つ目は、感情に左右されずに行動を続けることです。
挫折する原因のひとつは、「成功すれば気分が上がり、失敗すれば落ち込む」という感情の波に振り回されることです。
感情の浮き沈みが大きいと、「やる気があるときはやるが、気分が沈んでいるときはやめる」という流れになり、続かなくなります。
「結果がどうであれ、やるべきことを淡々とこなす」というマインドを持つことで、安定して継続しやすくなります。
8. データを記録する
継続するための改善法の8つ目は、データを記録することです。
続かない理由のひとつは、「自分がどれくらい進んでいるのか分からないこと」です。
たとえば、定期テストがあることで学習の進捗が分かるように、日々の活動を記録することで、自分の成長を確認できます。
成長が見えると、モチベーションが維持しやすくなり、自然と継続できるようになります。
9. SNSなどで公言する
継続するための改善法の9つ目は、続けていることを公言することです。
途中でやめてしまう理由のひとつは、「やらなくても誰も気にしない環境」です。SNSやブログで「○○を続けます!」と発表すると、他人の目があることで途中でやめづらくなります。
さらに、応援のコメントをもらうことで、やる気が高まり、継続する原動力になります。
10. 指導者をつける
継続するための改善法の10つ目は、指導者をつけることです。続かない理由のひとつは、「自己流で進めているため、正しいやり方が分からないこと」です。
経験者や専門家のアドバイスを受けることで、無駄な試行錯誤を減らし、効率よく習慣化できます。
また、指導者がいることで進捗をチェックされるため、「やらなければならない」という意識が生まれ、続けやすくなります。
継続するための習慣化のコツ10選
 継続の本当のゴールは、「意識しなくても続けられる状態」、つまり “習慣化” することです。
継続の本当のゴールは、「意識しなくても続けられる状態」、つまり “習慣化” することです。
つまり、「頑張らなくても自然にできる状態」にするのが成功の秘訣です。 ここでは、無理なく習慣として定着させるためのコツをご紹介します。
1. 習慣のトリガーを決める
継続するための習慣化のコツの1つ目は、行動を特定のトリガー(きっかけ)と結びつけることです。
習慣が続かない理由のひとつは、「いつやるか」が決まっていないため、つい忘れてしまうこと。
「歯を磨いたら○○をする」「コーヒーを飲んだら○○をする」など、既存の習慣と新しい行動を紐づけることで、意識しなくても自然と行動できるようになります。
2. 1回の負担を最小限にする
継続するための習慣化のコツの2つ目は、1回の行動をとにかく小さくすることです。
習慣が続かない理由のひとつは、「やらなければならないことが大きすぎて、始めるのが億劫になること」です。
「1日1ページだけ読む」「1分だけ運動する」など、ハードルを極限まで下げることで、「やらない」という選択肢を消し、無理なく習慣にできます。
3. 習慣の可視化をする
継続するための習慣化のコツの3つ目は、習慣を目に見える形で記録することです。
習慣が続かない理由のひとつは、どれだけ続けたか実感が湧かず、やる気が下がってしまうことです。
カレンダーにチェックをつけたり、アプリで記録を取ることで、達成感が生まれ、習慣が定着しやすくなります。
4. 失敗してもリセットしない
継続するための習慣化のコツの4つ目は、1回やらなかったからといって、ゼロに戻さないことです。
習慣が続かない理由のひとつは、「1日できなかったら全部無駄になった」と思ってしまうことです。
「1日休んでも問題なし」「週に5回できればOK」など、柔軟な考え方を持つことで、長期的に続けやすくなります。
5. できた自分を毎回認識する
継続するための習慣化のコツの5つ目は、行動をした直後に「できた自分」を意識することです。
習慣が続かない理由のひとつは、「やったことに対する達成感を感じられないこと」です。
行動のあとに「よし、今日もできた」と口に出したり、小さくガッツポーズをするなど、成功体験を意識することで、脳が「この行動は気持ちいい」と認識し、自然と続けたくなります。
ただ、私たちは、次のようなときに自分の成功に気づきにくい傾向があります。
1.簡単にできてしまうことは、「当たり前」だと思って成功とは感じません。
(例:毎日きちんと会社に行けている、家族と良好な関係を保てている)
2.すごい人が周りにいると、自分の成果が小さく感じてしまいます。
(例:隣の席の人が100点を取ると、自分の80点が物足らなく感じる)
3.人の心は失敗を強く覚えてしまう性質があります。これを「ネガティブ・バイアス」と呼びます。そのため、良いことをした記憶が、失敗の記憶に隠れてしまいがちです。
(例:テストで9問正解して1問間違えたとき、その1問の間違いばかり気になってしまう)
繰り返し言いますが、私たちは自分の成功や良いところに気づきにくいものです。
そこで、この問題を解決するために、「気づけなかった成功体験を発見する100の質問集」を作りました。
さらに、自分の中に眠る『成功パターン』を発見し、今後の方向性を決めるためのワークシート付きです。
私がこれまでの14年間で2000人以上の指導実績が実証するものです。有料にするか迷いましたが、悩まれている人が大変多いためひとまず無料で配布することにしました。
ただし、いつまで無料で配布するかわかりません。必要と思う人は入手して保存することをおすすめします。
下記からどうぞ。
6. 「やめない」ことを優先する
継続するための習慣化のコツの6つ目は、毎日同じことをやることよりも、「どんな形でもいいからやめないこと」を優先することです。
習慣が続かない理由のひとつは、「予定どおりにできないと意味がない」と思い込んでしまうことです。
たとえば、毎日30分運動すると決めていたのに、忙しくてできなかった場合、「今日は1分だけストレッチする」といった柔軟な対応をすることで、「やめない」という意識が強まり、長く続けやすくなります。
7. 自分をほめる習慣をつける
継続するための習慣化のコツの7つ目は、小さな達成でも自分をほめることです。
習慣が続かない理由のひとつは、「もっと頑張らないといけない」と思い、自分を認められなくなることです。
「今日もできた!」と自分を肯定することで、成功体験が積み重なり、自然と「続けるのが当たり前」の状態に変わっていきます。
8. 「いつやるか」を決める
継続するための習慣化のコツの8つ目は、「やるかどうか」で迷わず、「いつやるか」を決めることです。
習慣が続かない理由のひとつは、「今日はやろうか、やめようか」と考えてしまうことです。「今日はやる」と決めるのではなく、「朝のコーヒーを飲んだら○○をする」
と、実行のタイミングを固定することで、意識しなくても行動できるようになります。
9. 最初の一歩を「流れ」にする
継続するための習慣化のコツの9つ目は、「何かの流れの中に組み込むこと」です。習慣が続かない理由のひとつは、「新しく行動を始めるには、エネルギーが必要だから」です。
たとえば、「歯を磨いたらスクワットを5回する」「通勤電車に乗ったら英単語を1つ覚える」など、すでにやっている行動の流れに組み込むことで、意識しなくても続けやすくなります。
10. 「できたことリスト」を作る
継続するための習慣化のコツの10つ目は、できたことを振り返る習慣を作ることです。習慣が続かない理由のひとつは、「やったことより、できなかったことに意識が向いてしまうこと」です。
毎日寝る前に「今日できたこと」を書き出すことで、ポジティブな気持ちが強まり、自然と「またやろう」と思えるようになります。
つまずきやすい場面での具体的な対処法
 行動を続けていると、必ず「進めなくなる瞬間」があります。 ここでは、よくある3つのつまずきポイントと、その具体的な対処法を紹介します。
行動を続けていると、必ず「進めなくなる瞬間」があります。 ここでは、よくある3つのつまずきポイントと、その具体的な対処法を紹介します。
1. やる気が出ずに手が止まるとき
つまずきやすい場面での対処法の1つ目は、「やる気が出ずに手が止まるときの対処法」です。
「今日は気分が乗らない」「やる気が湧かないから、また今度やろう」そう思うようなことは誰しも経験があるでしょう。そのようなモチベーションに頼りすぎると、ちょっと気分が落ちたときにすぐ行動が止まってしまいます。
この問題を防ぐには、「ゼロにしない」ルールを決めることが大切です。
- 運動なら「ストレッチだけ」
- 読書なら「1ページだけ」
- 勉強なら「単語1つだけ」
最小限の行動を決めておくことで、「完全にやらない日」を防ぎ、習慣が崩れるのを防げます。また、「始めるまでのハードルを下げる」工夫も有効です。
「ノートを開くだけ」「ジムウェアに着替えるだけ」「PCを立ち上げるだけ」など、小さな行動を積み重ねると、「せっかくだから少しやろう」と思いやすくなります。
「やる気がないなら意味がない」と思うかもしれませんが、実際には「やる気がなくても動けば、やる気があとからついてくる」ことがほとんどです。
2. 忙しくて行動する時間が取れないとき
つまずきやすい場面での対処法の2つ目は、「忙しくて行動する時間が取れないときの工夫」です。
「やりたい気持ちはあるけれど、時間がない」「仕事や家事で手いっぱい」と思っている人も多いはずです。この状況を乗り越えるには、「まとまった時間がないなら、短時間でもいいと考える」 ことが大切です。
- 運動なら「10分だけ」
- 読書なら「移動中に数ページ読む」
- 勉強なら「動画の冒頭5分だけ観る」
「30分確保できなかったらできない」と考えるのではなく、「途中まででもOK」と思えば、やれる可能性が増えます。
また、「スキマ時間を意識して使う」ことも有効です。「SNSをダラダラ見る時間」「なんとなくテレビをつけている時間」「ぼんやり過ごしている時間」など、無意識に使っている時間を見直すと、意外と1日5〜10分の余裕はあるものです。
「本当に時間がない」のではなく、「時間がないと感じているだけ」の場合もあるので、まずは 1日5分でも切り出す習慣を作ることが大切です。
3. 続けているのに成果が出ないと感じるとき
つまずきやすい場面での対処法の3つ目は、「続けているのに成果が出ないと感じるときの対処法」です。
「こんなに頑張っているのに結果が出ない」「成長している実感がない」と感じると、モチベーションが下がり、やめたくなることがあります。
この状況で大切なのは、「成長にはタイムラグがある」と理解すること です。
努力は「投資」と同じで、続けている間は大きな変化が見えにくいもの。しかし、ある時点で「突然できるようになる」ことが多いのです。また、「今までの進歩を振り返る」ことも効果的です。
- 1週間前の自分と比べて、何ができるようになったか?
- 1ヶ月前なら、この努力をどう感じていたか?
こうした振り返りをすると、「意外と進んでいた」と気づくことができ、スランプを抜け出しやすくなります。さらに、「小さな成功体験を作る」 ことも有効です。
例えば、勉強なら「小テストを作ってみる」、運動なら「前回よりも1回多くこなしてみる」など、小さな達成を積み重ねることで、成長を実感しやすくなります。
まとめ:つまずいても、ゼロにしなければいい
つまずいたときに大事なのは、「完全にやめないこと」。 継続が途切れるのは、「才能がないから」でも「向いていないから」でもありません。つまずいたら、そのたびに「続ける方法を少し変えればいい」のです。
「忙しくても、スキマ時間を見つける」
「成果が見えなくても、過去の自分と比較する」
この意識があれば、どんなに小さな一歩でも、確実に前へ進んでいけます。
大切なのは「やる気」ではなく、「やめない仕組みを持つこと」。 自分に合った対処法を取り入れながら、無理なく継続していきましょうね。
| つまずきのポイント | 具体的な対処法 |
|---|---|
| やる気が出ないとき | ・最小限の行動を決める(1ページだけ読む、1分だけ運動する) ・始めるハードルを下げる(準備だけでもOK) ・「できた!」を実感する小さな目標設定 |
| 時間がないとき | ・5分でもできる簡易版を用意 ・移動時間などスキマ時間の活用 ・優先順位を明確にして時間を確保 |
| 成果が見えないとき | ・過去の自分と比較する ・小さな進歩を記録する習慣をつける ・具体的な成功指標を設定する |
継続する力を身につけるための次のステップ
 ここまで紹介した方法を実践することで、確実に継続する力は付いていきます。
ここまで紹介した方法を実践することで、確実に継続する力は付いていきます。
しかし、「自分に合った継続の仕方」を見つけるには、自分自身のことをよく理解する必要があります。
たとえば、
- どんな環境だと集中できるのか
- 何にモチベーションを感じるのか
- 自分の得意な習慣化の方法は何か
こういった自己理解があると、より効果的な継続の仕組みを作れます。そこで、私が10年かけて作成した「自分の見つめ直し完全マニュアル」をご用意しました。
このマニュアルは、これまでの人生を振り返り、自分の特性を体系的に整理して分かりやすく理解することができます。
制作に10年の歳月をかけた逸品。以下、充実の内容です。
- 自分の棚卸しに使える100の質問シート:自分自身を深く理解するための問いかけを提供し、長所や可能性を探るのに役立ちます。
- 自己肯定感を高めるための100の質問シート:自信を持って前向きに生きるための支援をします。
- 今の仕事合う?合わないチェックリスト:現在の職場環境が自分に合っているか評価するのに役立ちます。
- やる気ペンタゴンチャート:モチベーションを高め、行動を促すためのツールです。
- ときめきのツボワークシート:自分の情熱や興味が何にあるのかを探るのに役立ちます。
私の個人セッション(月々3万円)や講座の受講生たちを指導する際に使っているノウハウから厳選しました。配布を開始したその日、300人以上から申し込みがあったものです。
ただし、無料配布をいつまで続けるかわからないです。すいません。必要な人は、今すぐ入手して保存をおすすめします。
下記フォームにお名前とメールを入力するだけで入手できます。
こちらにLINE登録していただくと、自分らしく生きるための耳寄りなお話も公開してます。ブログには書けないここだけの情報も配信しています。

私との直接のやりとりもできますよ
最後に筆者からの大切なメッセージ

継続できないことで、「自分は意志が弱いんじゃないか…」と落ち込んだことがあるかもしれませんね。
でも、これまでお伝えしたように、それは「努力が足りないから」ではなく、「継続の仕組みが合っていないだけ」です。私自身も昔は何をやっても続かず、「向いてないのかもしれない」と諦めかけたことがありました。
でも、自分の特性を知り、それに合った方法を見つけたことで、自然と継続できるようになったのです。「自分に合った継続の仕組み」 は、必ずあります。それは自分の得意なことや、目的のはっきりしたもの、本当に大切にしたいことの中にヒントがあります。
もし、「自分の強みや価値を整理し、それを活かして継続できる方法をもっと知りたい」と思ったら、こちら も参考になると思います。「できる人」と「できない人」の違いは、才能や意志の強さではなく、自分に合ったやり方を知っているかどうか です。
焦らず、少しずつ試しながら、自分に合う方法を見つけていってくださいね。
最後までお読みいただきありがとうございます。
魂の女性成長支援・浅野塾代表 浅野ヨシオ
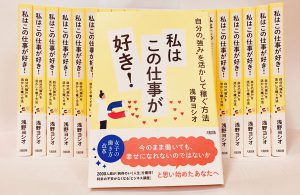

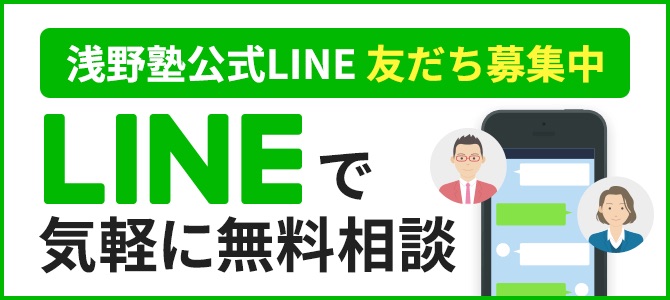

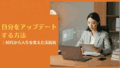
コメント