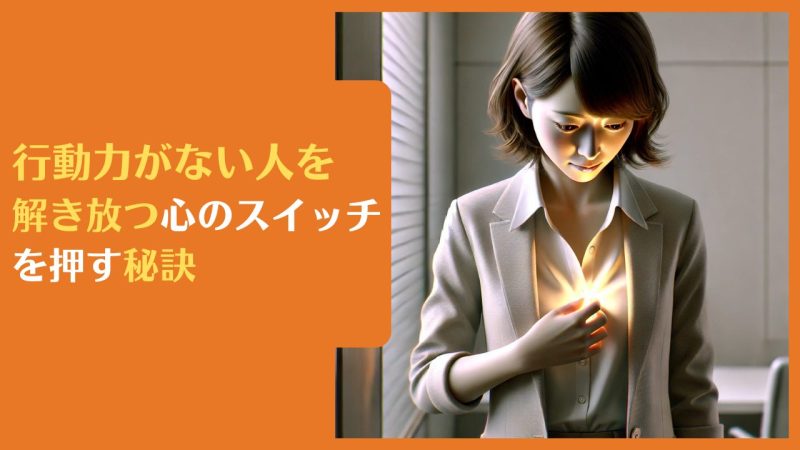

そんな疑問に答えます。
この記事では行動力がない人でも、ゆるゆると動き出してしまうお話。 「失敗するのが不安で怖い」と感じる人にも、ぜひ読んでいただきたい内容です。
行動力は本来、誰にでもある能力。 しかし、多くの人がその能力を十分に理解できずにいます。 実は、行動力がないと感じること自体が短所ではなく、その背後にある理由や不安に気づくことが大切なのです。
本記事では、ほかでは提供されていない独自の視点と情報を盛り込みました。
行動力を引き出すための、誰にでも実践可能な、わかりやすい方法を解説。 この記事を読み終えたとき、無理なく、そして自然に「失敗への恐れ」を和らげ、自分自身の行動力を高めることができるでしょう。
ぜひ最後までお読みくださいね。
追伸:本文の最後に素敵なマニュアルのプレゼントをご用意しています。
- 記事を書いている人の専門性と実績
経歴:
新卒8ヶ月での挫折退職から再出発。26年の会社員経験(10年は複業)を経て起業。現在は個性を活かす道を拓く会社を経営。
専門:
行動力がないと思い込んでいる人を含む、以上2000人超の女性指導実績。本当の強みを発見し、人生を新たな方向へ導くプロ。やりがいのある転職から起業まで、前職や年齢を超えた女性の夢実現に定評。
メディア/著書:
日本経済新聞、日経WOMAN他多数掲載。著書「私はこの仕事が好き!自分の”強み”を活かして稼ぐ方法(大和出版)」
行動をためらう心のブレーキとは何か
 本文の冒頭でお伝えしたとおり、行動力は本来、私たち一人一人が持っている素晴らしい能力(本能)です。
本文の冒頭でお伝えしたとおり、行動力は本来、私たち一人一人が持っている素晴らしい能力(本能)です。
日々のなにげない行為、たとえば食事をすることや水を飲むことも、私たちの行動力の表れの一つ。 私たちは、まるで息をするように自然とさまざまな行動をしています。日常生活の中で、無意識に数え切れないほどの行動。 でも、人間は高度な知能を持っているので、頭であれこれ考え、行動を制限してしまいます。
「失敗したらみっともない」「続かなかったらどうしよう」といった不安や恐れが、行動を躊躇させるのです。 これらは、人間特有の考え方のパターンであり、ほかの動物には見られません。動物たちは、考えるよりも先に行動する本能に従います。彼らは直感と本能に従い、生存に必要な行動をとる。ここには、行動する純粋な力と目的があります。
次から紹介する内容を読み進めると、余計な心配が和らぎ、積極的に行動する心のスイッチが入るでしょう。
無意識の比較が行動を止める?
 そもそも私たちは、なぜ行動力がある・ない、と考えてしまうのでしょう。 その理由はひとつ。 他人と比べてしまうからです。
そもそも私たちは、なぜ行動力がある・ない、と考えてしまうのでしょう。 その理由はひとつ。 他人と比べてしまうからです。
バリバリ行動している人が目に入らなければ、自分が「行動力がない」と気づけないことも。 もしも、行動力がある人を見て落ち込むのであれば、克服を考えるよりその相手としばらく距離を置くのが良い方法です。
これは決して後ろ向きな改善方法ではありません。行動力を生む立派な対処法。 自分が今すべきことに意識を集中させるための”環境づくり”なので、ご安心くださいね。
行動しないのは自分を守る本能かも
 少し補足します。 「行動力がない」「行動できない」と自ら感じるのは、心にブレーキがかかっているとき。 思うような結果が出るかどうかわらないときに、不安になるのは自然なことです。
少し補足します。 「行動力がない」「行動できない」と自ら感じるのは、心にブレーキがかかっているとき。 思うような結果が出るかどうかわらないときに、不安になるのは自然なことです。
不安は心に緊張を与え、危険を避けるために必要な能力(本能)ですからね。 行動を躊躇しているときに、
- 本当はやりたくない
- やらないとみっともないと思う
- 行動の目的がよくわからない
いずれかに当てはまらないか考えてみましょう。 心のブレーキがかかっていると、本当は行動する必要がない(必要性を感じていない)のかもしれません。
【重要】行動力がないのは短所ではない
さらに深堀りした解説をします。 行動力がないのは短所と言い切れません。前述しましたが、危険を避けて自分を守る本能が働きますから。

ここにご注意ください↓
「やらなきゃ」「やらねば」と思い浮かぶ義務的なものに、行動が鈍くなるのはあたり前です。行動力がないと考える前に、本心を探ってみましょう。
行動力を引き出す心のスイッチの仕組み
 私たちの心には、行動をためらう「ブレーキ」と、行動をうながす「アクセル」があります。
私たちの心には、行動をためらう「ブレーキ」と、行動をうながす「アクセル」があります。
その具体的なスイッチの見つけ方、押し方をご紹介していきます。
行動ブレーキの4つのタイプ診断
 ここからは、なぜ行動にブレーキがかかってしまうのか、その主な原因を4つのタイプに分けて解説します。 自分がどのタイプに近いか知ることで、より具体的な「心のスイッチ」を見つけやすくなるでしょう。
ここからは、なぜ行動にブレーキがかかってしまうのか、その主な原因を4つのタイプに分けて解説します。 自分がどのタイプに近いか知ることで、より具体的な「心のスイッチ」を見つけやすくなるでしょう。
タイプ1:失敗がこわいタイプ
 何かを始めようとするとき、「うまくいかなかったらどうしよう」「失敗して恥ずかしい思いをしたくない」という気持ちが先に立ち、行動をためらってしまうタイプです。
何かを始めようとするとき、「うまくいかなかったらどうしよう」「失敗して恥ずかしい思いをしたくない」という気持ちが先に立ち、行動をためらってしまうタイプです。
タイプ2:周りの目が気になるタイプ
 「他の人にどう思われるか」「否定されたり、批判されたりしたらイヤだな」という不安が強く、自分の意見や気持ちを抑えてしまいがちなタイプ。
「他の人にどう思われるか」「否定されたり、批判されたりしたらイヤだな」という不安が強く、自分の意見や気持ちを抑えてしまいがちなタイプ。
タイプ3:行動迷子タイプ

「何から手をつければいいのか分からない」「選択肢が多すぎて選べない」など、進むべき方向や具体的な手順が見えず、混乱して動けなくなってしまうタイプです。
タイプ4:自信がもてないタイプ
 「どうせ自分には無理だ」「自分にはそんな価値がない」といった否定的な自己認識が強く、挑戦する前から諦めてしまいやすいタイプ。
「どうせ自分には無理だ」「自分にはそんな価値がない」といった否定的な自己認識が強く、挑戦する前から諦めてしまいやすいタイプ。
タイプ別:「こわさ」を力に変える心のスイッチ
 それでは、それぞれのタイプ別に、行動へのこわさを和らげ、一歩を踏み出すための心のスイッチを入れるステップを詳しく見ていきましょう。
それでは、それぞれのタイプ別に、行動へのこわさを和らげ、一歩を踏み出すための心のスイッチを入れるステップを詳しく見ていきましょう。
「失敗がこわいタイプ」の方へ:5つの心のスイッチ・ステップ

心のスイッチ・ステップ1:ご自身の「こわさ」を言葉にしてみる
失敗がこわいと一言でいっても、その中身は人によりさまざま。 多くの方がおそれているのは、「失敗という出来事そのもの」だけではないのです。 むしろ、失敗することで、自分の評価が下がってしまうことをおそれているケースが、少なくないように思います。
では、ご自身の失敗とは、具体的にどんな状況を指すのでしょう。そして、その奥で本当に何を一番おそれているのか。 少し掘り下げて見つめてみましょう。 次の問いかけに、心の中でゆっくりと答えてみてください。紙に書き出すのも、もちろん良い方法です。
- もし失敗したとき、一番イヤだと感じるのはどんなことでしょう?
- (周りの人にがっかりされることでしょうか?)
- (努力や時間が無駄になると感じることでしょうか?)
- (自分はダメな人間だと感じてしまうことでしょうか?)
- (ご自身の評価が下がったと感じることでしょうか?)
- その「一番イヤなこと」が起こると、どんな気持ちになりそうですか?
- (恥ずかしい、情けない、悲しい、腹が立つ、落ち込む、など)
- 似たようなイヤな気持ちを、これまでに経験したことはありますか?
- (それはどんなときだったでしょうか?)
これらの問いかけに答えるうち、漠然とこわいと感じていたものの正体が、見えてくることでしょう。 「ああ、失敗そのものよりも、結果として〇〇と思われるのが特にこわかったのだな」というように。
自分のこわさの輪郭が見えてくると、いくらか冷静になれたり、次の一手を考えやすくなったりするものです。 これが、行動するための大切な「心のスイッチ」の第一歩となります。
心のスイッチ・ステップ2:失敗の「こわさ」を小さくする工夫
ご自身の「こわさ」の正体が少し見えてきたでしょうか。 次に大切なのは、その「こわさ」を必要以上に大きくしないための工夫です。
そして、ここで一つ、とても大切な心構え。 それは、「最初はうまくいかなくて当たり前」という感覚からスタートすること。 これは決して後ろ向きな考え方ではありません。むしろ、心が軽くなる前向きな捉え方といえるでしょう。
そもそも「失敗」とは、行動を止めてしまったときの結果を指すもの。 つまり、行動しつづけている限り、それは結果が出るまでの途中経過でしかありません。
この心構えを持つことで、一つ一つの試みをより気軽に行えるようになります。 では、その上で、失敗のダメージを最小限にする具体的な三つの工夫をみていきましょう。
工夫1:行動を「赤ちゃんステップ」まで分解する
大きな目標や未知の挑戦は、それだけで圧倒されてしまうものです。 「失敗したらすべてが無駄になる」と感じやすいかもしれません。
そこで、最初の一歩を驚くほど小さく分解してみるのをおすすめします。 たとえば、新しいスキルを身につけたいなら、「毎日30分勉強する」ではなく、「参考書を1ページだけ開いてみる」から始めるのです。
工夫2:「お試し期間」を設けてみる
何かに挑戦するとき、「これで必ず成功させなければ」と気負いすぎると、失敗したときの反動が大きくなります。 そうではなく、「まずは3日間だけ試してみよう」「この部分だけ実験してみよう」というように、期間や範囲を限定したお試しと位置づけてみましょう。 お試し期間中の出来事は、すべてデータ収集と捉えます。 うまくいってもいかなくても、そこから得られる情報が次の判断に役立つ。 これは失敗ではなく、検証結果が出たと考えることができます。
工夫3:「もしも」のときの安全網を用意しておく
それでも心配な場合は、「もしうまくいかなかったら、こうする」という代替案や撤退ラインをあらかじめ考えておくのも有効策。 たとえば、「この方法で集客を試してみて、もし1ヶ月で反応がなければ、別の方法に切り替える」というように。 最悪の事態を想定し、そのときの対応を決めておくだけで、心の負担は軽くなります。 それは、やみくもに突き進むのではなく、リスクを管理する良い方法といえるでしょう。
心のスイッチ・ステップ3:こわさと「仲間」になって一歩進む
ステップ1でご自身の「こわさ」の輪郭が見え、ステップ2でその影響を小さくする工夫を知りました。 それでも、「やっぱりまだこわい…」と感じるかもしれません。 それは、とても自然なこと。特に新しいことに挑戦するとき、こわさを感じるのは当たり前です。
実は、その「こわさ」は決して悪いものではありません。こわさは、大切なことを教えてくれる味方 こわさを感じるからこそ、私たちは慎重になります。
準備をしっかりしようと考えます。 つまり、こわさは行動の精度を高め、大きな失敗を防いでくれる、頼れる「仲間」のような存在でもあるのですね。 ですから、「こわさを克服しよう」「消し去ろう」と無理に戦う必要はありません。
むしろ、こわさを無理に消してしまうと、かえって不用意な失敗を招くことすらあるかもしれません。 「心のスイッチ」の本当の役割は、こわさを消すことではないのです。
こわいという感情に無理に逆らわず、「こわいね、でも大丈夫だよ」と自分に寄り添いながら、小さな一歩を踏み出すことを選ぶためのもの。 そのための具体的な心の持ち方を三つ、ご紹介します。
1.こわさを感じている自分を、まず受け入れる
「こわい」と感じる自分を、ダメだなとか弱いなと否定する必要はありません。 「ああ、今、自分はこわいと感じているんだな」と、ただその感情を客観的に認めてあげましょう。
感情に良いも悪いもありません。どんな感情も、ご自身の大切な一部です。 こわさを感じている自分を優しく受け入れることが、こわさと上手に付き合う第一歩。
2.意識を「こわさ」から「ほんの小さな行動」へそらす
こわさを感じていると、どうしても意識が「こわいこと」そのものに集中しがち。 そうすると、ますますこわさが大きく感じられてしまいます。 そこで、「心のスイッチ」を使って、意識のチャンネルを少し切り替えてみましょう。
「こわいな」と感じつつも、「でも、今この瞬間にできる、ほんの小さなことは何だろう?」と、ステップ2で考えた「赤ちゃんステップ」のような、ごくごく簡単な行動に意識を向けるのです。
たとえば、「資料を開くだけ」「一行だけ書く」など、本当にささやかなことで構いません。 行動の大きさと、こわさの大きさは必ずしも比例しない。小さな行動なら、こわくても意外とできてしまうものです。
3.行動できた自分を、結果とは別にほめる
その小さな一歩を踏み出せたら、どんな結果であれ、「よく行動できたね」と自分自身をほめてあげてください。 大切なのは、「こわさを感じながらも行動を選べた」という事実。 それは、こわさという仲間と一緒に、新しい領域に足を踏み入れた証です。
この「こわくても、できた」という経験の積み重ねが、少しずつ自信を育て、次の行動への抵抗感を和らげてくれます。 「失敗がこわい」と感じやすい方が、その繊細な感受性を活かしつつ、しなやかに行動を選びとるために。 「心のスイッチ」が、こわさとの新しい関係を築くお手伝いとなれば幸いです。
心のスイッチ・ステップ4:完璧さより「まず動いてみる」意識へ
「完璧にしたい」「中途半端はイヤだ」。 そんな思いが、最初の一歩を重くしていませんか。 「失敗がこわい」という気持ちの裏にある完璧主義は、時として行動の大きな壁になります。
この壁を乗り越えるきっかけが、「とりあえずやってみる」という意識。 一番難しい最初の動き出しも、この意識で軽くなるかもしれません。 動き出せば不安は二の次になり、止まっていた石が転がり出すように、自然と道が開けることもあります。
では、この「とりあえずやってみる」という最初の一歩を支える、具体的な二つの考え方を「心のスイッチ」としてみていきましょう。
1.「完璧主義」から「まず終わらせる」へシフトする
「まずは終わらせることを大切にする」のがこの考え方です。 完璧な仕上がりを目指すあまり、いつまでも完成せずに手が止まってしまうより、たとえ70点でも「最後までやり遂げた」という事実を重視。
2.「実験してみる」気持ちで試してみる
一つ一つの行動を「成功か失敗か」で判断するのではなく、「試してみてデータを集める実験」と捉える考え方。 科学者が仮説を検証するために実験を繰り返すように、ご自身の行動も「こうしたらどうなるだろう?」という好奇心で試してみます。
ステップ2の「お試し期間」も、この実験する気持ちの良い実践方法です。 実験ですから、うまくいかないことも当然あります。大切なのは、その結果から何を学び、次にどう活かすか。 この視点を持つと、失敗をおそれる気持ちが和らぎ、もっと気軽に様々なことを試せるようになるでしょう。
完璧主義が悪いわけでは決してありません。質の高さを追求する心は素晴らしいもの。 しかし、それが行動のブレーキになっていると感じるなら、「とりあえずやってみる」という最初のきっかけを大切にし、「まずは終わらせてみる」「実験してみる」という「心のスイッチ」を、ぜひ試してみてください。 肩の力が少し抜けて、行動がずっと楽になるかもしれません。
心のスイッチ・ステップ5:「できた自分」を積み重ねて自信を育む
これまでのステップで、こわさと向き合い、小さな一歩を踏み出す工夫をみてきました。 たとえどんなに小さな行動でも、実際にやってみた後には、大切なプロセスが待っています。 それは、「行動できた自分」をきちんと認め、その「小さな成功体験」を積み重ねていくこと。
「失敗がこわい」と感じる方は、ご自身に厳しく、できたことよりもできなかったことに目が向きやすい傾向があるかもしれません。 だからこそ、意識して「できたこと」に光を当て、自信を育んでいきましょう。
1.「小さな成功」の基準を自分に優しくする
「成功体験」というと、何か大きな成果をイメージするかもしれません。 しかし、ここでいう「小さな成功」とは、もっと日常的な、ささやかなものです。
たとえば、ステップ2の「赤ちゃんステップ」を一つでも試せた。 ステップ3のように、こわさを感じながらも、ほんの少しだけ行動に移せた。
ステップ4のように、完璧でなくても「とりあえずやってみた」と行動を終えられた。 これらは全て、立派な「小さな成功」。大切なのは、行動を起こせたという事実そのものです。
結果の大小や、他人からの評価は一旦脇に置きましょう。
2.「できたこと探し」を習慣にする
一日の終わりに、今日「できたこと」や「やってみたこと」を三つ、思い出して書き出してみるのも良い方法。 どんなに些細なことでも構いません。
「朝、いつもより5分早く起きられた」「気になっていたメールを一件返信できた」など。 初めは難しく感じるかもしれませんが、続けていくうちに、ご自身の小さな頑張りを見つけるのが上手になります。
これは、自己肯定感を高める上で、とても効果的な習慣です。
3.自分をほめる言葉をかける
「小さな成功」を見つけたら、心の中で、あるいは実際に声に出して、自分自身を具体的にほめてあげましょう。 「よくやったね」「えらいぞ、自分」「こわかったけど、一歩進めたね」など、温かい言葉をかけるのです。
まるで、親しい友人を励ますように、ご自身にも優しく接してみてください。 この「自分ほめ」が、次の行動へのエネルギーとなり、こわさを乗り越える力を少しずつ育んでくれます。 「失敗がこわい」という気持ちは、すぐには消えないかもしれません。
しかし、日々の「小さな成功体験」と「自分ほめ」を積み重ねることで、こわくても、自分はできるかもしれないという感覚が確実に育っていきます。 これが、こわさと上手に付き合いながら、着実に行動を続けていくための、大切な「心のスイッチ」となるでしょう。
「周りの目が気になるタイプ」の方へ:5つの心のスイッチ・ステップ

心のスイッチ・ステップ1:「自分のものさし」と「他人のものさし」に気づく
周りの人にどう見られているか、いつも気になってしまう。 行動するとき、自分の気持ちよりも先に「みんなはどう思うかな?」と考えてしまう。 そんな経験はありませんか。 それは、ご自身の心のアンテナが、周りの人たちからの評価に敏感になっているサインかもしれません。
ここでまず、自分の行動や考え方の基準となる「ものさし」について、少し意識を向けてみましょう。 私たちは、無意識のうちに二つの「ものさし」を使い分けていることがあります。
一つは、社会の常識や周りの人の意見、期待などを基準にする「他人のものさし」(他人軸ともいいます)。 もう一つは、ご自身の「こうしたい」「これが好きだ」という純粋な気持ちや価値観を基準にする「自分のものさし」(自分軸ともいいます)。
「周りの目が気になる」と感じやすい方は、この「他人のものさし」を優先して使いがち。 そして、いざ「自分のものさし」で何かを感じたり、望んだりすると、こんな心配がよぎるかもしれません。
「こんなことを望むなんて、甘えていると思われないだろうか」 「好きなようにやりたいなんて、わがままじゃないだろうか」と。
たとえば、「自分のペースで、心から好きな仕事に取り組みたい」という願い。 これは、ご自身の心からの素直な気持ち、「自分のものさし」から生まれた大切な望みです。
しかし、「他人のものさし」で見ると、「そんなのは現実的じゃない」「もっと周りに合わせるべきだ」といった声が聞こえてきそうですよね。
大切なのは、どちらが良い・悪いで判断するのではなく、「今、自分はどちらのものさしを使っているかな?」と気づくこと。
そして、「自分のものさし」から生まれる願いや気持ちも、決して「甘え」や「わがまま」といった一言で片付けてしまう必要はない、と知ることです。 それは、ご自身が本当に望んでいることのヒントかもしれません。 以下の問いかけを通じて、自分の「ものさし」について考えてみましょう。
- 最近、何かを「やりたい」または「やりたくない」と感じたとき、その理由は主にどちらから来ていましたか?
- (A)周りの人が期待するから/みんながそうしているから/そうすべきだと言われているから
- (B)自分が心からそうしたい(したくない)と感じるから/それが自分にとって心地よい(不快だ)から
- もし、周りの目を全く気にしなくてよいとしたら、本当はどうしたいですか?
- 「自分のものさし」で考えると「こうしたい」と思っても、「他人のものさし」を考えるとためらってしまうことは何ですか? そのとき、どんな言葉が心に浮かびますか?
このステップは、まずご自身の心の状態に気づくためのもの。 すぐに何かを変えようとしなくても大丈夫。
「ああ、自分は今、他人のものさしを気にしているんだな」と気づけること、そして「自分のものさしも大切にしていいんだな」と感じられることが、大きな一歩となります。
心のスイッチ・ステップ2:「誰の人生を生きるか」を見つめ直す
ステップ1で、ご自身の「ものさし」と「他人のものさし」があることに気づきました。 では、なぜ「他人のものさし」をそれほど気にしてしまうのでしょうか。 そして、それが自分の行動や感情にどんな影響を与えているのでしょう。 ここで、少し立ち止まって考えてみてほしいことがあります。
周りの目を気にして、周りの人たちが「良い」とするものを選択し、それに基づいて行動する。 それは、もしかすると「自分の人生」ではなく、「他人の人生」を生きることに繋がっているのかもしれません。 人はそれぞれ、大切にするもの(価値観)が異なります。
ですから、他の人の意見や主張が、必ずしもご自身に合っているとは限りません。 それなのに、周りが思う「正しさ」に自分を合わせようとし続けることは、本当の感情を後回しにしていることになります。 これでは、他人からの期待や世間の常識という名の正しさの奴隷として生きることになりかねない。
たとえば、本当は絵を描く仕事に惹かれているのに、「大きな会社で安定して働くのが正しい道だ」という周りの声や常識を優先し、その結果、日々の仕事に心が満たされず、ため息をついてしまう。そんな方もいるかもしれませんね。
これは、ご自身の「好き」という気持ちよりも、「周りから見た正しさ」を選んでしまったケースといえるでしょう。 一度きりの自分の人生、本当に「他人の期待に応えるため」だけでよいのでしょうか。
この問いかけが、他人の評価との向き合い方を変える、大切な「心のスイッチ」となります。 この大きな問いかけを心に置いた上で、次に、他人の声と上手に距離を置き、自分の心を守るための具体的な考え方を見ていきましょう。
1.意見は「その人のもの」、自分の価値とは別と知る
誰かが何かを評価したり、意見を述べたりするとき、それはあくまで「その人個人のフィルターを通した感想」の一つ。 味の好みや天気の感じ方が人それぞれ違うように、物事の捉え方も千差万別。
その意見が、ご自身の人間性全てを評価するものではありません。 「あの人は、そう感じたのだな」と、事実と意見を分けて受け止める練習をしてみましょう。 これにより、一つ一つの意見に過剰に心を揺さぶられることが減っていきます。
2.心に入れる言葉を「選ぶ」意識を持つ
全ての言葉を無防備に受け入れる必要はありません。 その言葉が、ご自身の成長や安心につながる「栄養」となるか、それとも心を消耗させるだけのものか、見極める意識を持ちましょう。 たとえば、こんな視点で考えてみます。
- その言葉は、愛情や思いやりから発せられているだろうか?
- その意見は、具体的な行動のヒントになるだろうか?
- 表面的な批判ではなく、本質的な問題点を指摘してくれているだろうか?
もし「これは今の自分には必要ないな」と感じる言葉であれば、心の中でそっと受け流す意識も大切。 自分の心を守るために、どんな言葉を大切にするかを選ぶのは、ご自身の権利なのです。
このステップは、他人の意見を全て無視するためではありません。本当に大切な声に耳を傾けつつ、不必要な評価からは距離を置く。 そうして初めて、自分の人生を生きる感覚を、取り戻していけるはずです。
心のスイッチ・ステップ3:小さな「自分らしさ」を安心して表現する練習
ステップ1で「自分のものさし」に気づき、ステップ2で「他人の評価」との向き合い方を考えました。 次はいよいよ、ご自身の「ものさし」に基づいた小さな一歩を踏み出す練習ですが、ここが一番ドキドキするところかもしれませんね。
「でも、それができないから困っているんだ…」という声が聞こえてきそう。 大丈夫です。ここでは、決していきなり大きな挑戦を求めるわけではありません。
驚くほど小さな、それでいて効果的な「自分表現」の練習方法を、「心のスイッチ」としてご紹介します。 大切なのは、行動のハードルを極限まで低く設定し、「これならできるかも」と感じられることから始めること。
練習1:「心の声」をキャッチする練習
まず、何かを表現する前に、ご自身の心の中で「本当はどう感じているかな?」「本当はどうしたいかな?」と、静かに耳を傾ける習慣をつけましょう。
周りの声にかき消されがちな、自分のささやかな本音をキャッチすることが第一歩。
たとえば、ランチのメニューを選ぶとき、一瞬「本当はこっちがいいな」と思った気持ちを、気のせいだと打ち消さず、まずは心の中で認めてあげます。
練習2:超・低リスクな場面で「小さな好み」を伝えてみる
いきなり意見を主張したり、「NO」を伝えたりするのは難しいものです。 ですから、まずは失敗しても全く問題のない、超・低リスクな場面を選びましょう。 そして、ごくささいな「自分の好み」を言葉にしてみる練習です。
たとえば、気心の知れた家族や友人に、「今日の夕飯、〇〇が食べたいな」と伝えてみる。 カフェで注文するとき、「砂糖は少なめでお願いします」と、ほんの少しだけ自分の希望を添えてみる。 「どちらの色がいいですか?」と聞かれたとき、一瞬迷っても「私はこちらの色が好きです」と、小さな好みを選んでみる。
「こんな簡単なこと?」と感じるかもしれませんね。
もしそう感じたなら、それは素晴らしいこと。 その場合は、ご自身にとって「少し挑戦だけれど安心できる」自己表現を見つけて試しましょう。 一方で、「これくらいのことでも、実はドキドキする…」という方もいるはずです。
そういう方にとっては、このささいに見える一歩こそが大切。 肝心なのは、ご自身の「今の場所」から、最も優しいステップを見つけることです。 そして、相手を説得することではなく、「自分の気持ちを言葉にできた」という経験そのものを大切にしましょう。
練習3:「NO」の代わりに「少し考える時間をもらえますか?」から始める
頼み事をされたとき、すぐに「NO」と言うのが難しければ、まずは「少し考えさせてください」「後でお返事してもいいですか?」と、即答を避けて時間をもらうことから始めてみましょう。
この一言が言えるだけで、心の負担はかなり軽くなります。 そして、時間をおいて冷静に考えた結果、「やっぱり難しいな」と感じたら、その気持ちを正直に、でも柔らかく伝える練習をします。 その際も、長々と理由を説明する必要はありません。
練習4:行動後の「気になる気持ち」との付き合い方を変える
小さな自己表現をした後、「相手はどう思ったかな」「変に思われなかったかな」と、どうしても反応が気になってしまうのは自然なこと。 その気持ちを無理に消そうとする必要はありません。大切なのは、その「気になる気持ち」に長時間とらわれないようにすることです。
たとえば、小さな自己表現をしたら、すぐに別の楽しいことや集中できる作業に意識を切り替える。 ステップ2で考えたように、「他人の評価は、その人の一面的な感想に過ぎない」と心の中で繰り返してみる。 「自分の気持ちを伝えられた」という行動そのものに意識を向け、その小さな選択を自分で認めてあげる。
これらの練習は、一度でうまくいく必要はありません。 何度も繰り返すうちに、少しずつ「自分の気持ちを伝えても大丈夫なんだ」「反応を気にしすぎなくても平気だった」という安心感が育っていきます。 焦らず、ご自身のペースで、本当に小さな一歩から試してみてください。
心のスイッチ・ステップ4:心地よい繋がりを選び「自分軸」を育てる
ステップ3までで、小さな自己表現の練習を始めました。 しかし、どんな相手に、どんな距離感でご自身を表現していくかは、とても大切なポイント。 「周りの目が気になる」と感じやすい方は、無理に多くの人と上手くやろうとしたり、気を使う相手と長時間過ごしたりして、かえって心を消耗させてしまうことがあります。
ここでは、ご自身の「自分軸」を安心して育てるための、人との繋がり方に関する「心のスイッチ」をご紹介。
1.「一緒にいて疲れる人」を、まず認識する
まず、どんな人と一緒にいるときに自分が緊張したり、相手の反応が妙に気になったり、後でどっと疲れが出たりするのか、正直に感じてみましょう。 「みんなと仲良くしなければ」という思い込みは一旦横に置き、ご自身の心が「この人とは少し距離をおきたいかも」と感じるサインを見逃さないことが大切。
2.無理に関わろうとせず、「選ぶ」意識を持つ
意外に思われるかもしれませんが、「周りの目が気になる」と感じる方こそ、全ての人と深く関わろうとしない方が、心が楽になることが多いのです。
一緒にいてストレスを感じる相手とは、必要最低限のお付き合いに留めることを考えてみましょう。 また、同じ人と長時間過ごすのが負担なら、意識的に関わる時間を短くする工夫も有効です。
たとえば、お誘いがあっても「少しだけなら」と時間を区切ったり、別の機会を提案したりするのです。 無理に付き合い続けることは、ご自身のエネルギーをすり減らすだけかもしれません。
3.今の「心地よさ」で繋がる人たちを大切にする
では、どんな人たちとの時間を大切にすればよいのでしょうか。 それは、今の自分が本当に興味があることや、価値を感じるもの。それらで自然と繋がれる人たち。
趣味の集まり、学びの場、あるいは価値観を共有できる友人など、一緒にいて心がリラックスできたり、前向きな気持ちになれたりする相手との時間を優先しましょう。
このような関わりの中では、安心して「自分のものさし」を使いやすくなります。
4.人間関係は「変化していい」と知る
私たちの興味や価値観は、年齢を重ねたり、様々な経験をしたりする中で、自然と変化していくもの。 それに伴って、心地よいと感じる人や、大切にしたい関係性が変わっていくのも、また自然なことだと捉えてみましょう。
「昔からの付き合いだから」「一度仲良くなったから」と、今の自分に合わなくなった関係を無理に維持しようとしなくてもよいのです。
その時々のご自身の心の声に正直に、人間関係も新陳代謝していくような、しなやかな感覚を持つ方が、ずっと実践的で、心が健やかでいられます。
このステップは、人間関係を断ち切ることを勧めているわけではありません。 ご自身が本当に安心でき、自分らしくいられる繋がりを大切にし、そうでない関係とは上手に距離を置く。
その主体的な選択が、「周りの目が気になる」という状態から抜け出し、「自分軸」で生きるための土台を育んでくれます。
心のスイッチ・ステップ5:行動の先に「自分への信頼」を築く
これまでのステップで、ご自身の「ものさし」を大切にし、周りの声と上手に付き合いながら、小さな一歩を踏み出す練習を重ねてきました。
ここでは最後に、それらの経験を通じて「自分自身への確かな信頼」を築き上げ、周りの目に揺らぎすぎない、しなやかな心を育てるための「心のスイッチ」についてお伝えします。
1.「自分の人生の舵は、自分で取る」と決める
周りの人が、ご自身の人生の最後まで面倒を見てくれるわけではありません。 親でも、パートナーでも、友人でもなく、自分の人生の責任を本当に負えるのは、最終的にはご自身だけ。
この事実を静かに受け止めることは、他人の評価に一喜一憂する状態から抜け出し、「自分の足で立つ」ための原点となります。 「誰かの期待に応えるため」ではなく、「自分が納得できる人生を歩むため」に。そう心に決めることが、何よりも強い「心のスイッチ」となるでしょう。
2.「後悔しない」ために、行動を止めない
「あのとき、こうしておけばよかった…」そんな後悔を少しでも減らすために大切なのは、たとえその判断が良いか悪いか分からなくても、とにかく前に進み続けること。 もちろん、不安やこわさを感じるでしょう。しかし、その感情と向き合い、付き合いながらでも、ほんの1mmでもいいから行動を続ける。 その「行動し続けている」という事実そのものが、少しずつ「自分はこれでいいのだ」という感覚を育ててくれます。 行動する回数が増えれば増えるほど、ご自身の判断の正確性も自然と増していくはず。
3.「行動した自分」こそが、信頼の源泉
では、どうすれば自分自身を信じられるようになるのでしょうか。 それは、特別な才能や大きな成功体験だけから生まれるものではありません。
不安やこわさを感じながらも、それに押しつぶされずに、たとえ小さな一歩でも「行動した」という経験の積み重ね。 それこそが、「自分は大丈夫だ」「自分はやっていける」という、揺るぎない自信と信頼の源泉となるのです。
ステップ3で試した小さな自己表現や、ステップ4で選んだ心地よい繋がりの中での振る舞い。 それら一つ一つが、「行動できた自分」という実績。 この実績を丁寧に拾い集め、心に刻んでいくことが、何よりも大切です。 周りの目が気になる気持ちが、完全になくなることはないかもしれません。
しかし、これらの「心のスイッチ」を意識し、日々の小さな行動を積み重ねることで、自分の感覚を信じ、ご自身の足で人生を歩む強さが、きっと育っていくはずです。
「行動迷子タイプ」の方へ:5つの心のスイッチ・ステップ

心のスイッチ・ステップ1:心の中の「小さな光」を見つける
「何がしたいのか分からない」「どこへ向かえばいいのだろう…」 たくさんの情報や選択肢を前に、あるいは逆に、何も思い浮かばずに、まるで広い海で方角を見失ったように感じてしまうことはありませんか。
そんなとき、無理に壮大な目的地を定めようとしなくても大丈夫。 まずは、ご自身の心の中に、ほんのりとした明かりを灯す「小さな光」を見つけることから始めてみましょう。
この「小さな光」とは、完璧な計画や壮大な目標のことではありません。 「なんだか少し気になるな」「こっちの方向へ進んでみたい気がする」といった、ごくささやかな興味の芽や、ぼんやりとした方向感覚のようなもの。 その小さな光を見つけるための、いくつかのヒントをご紹介します。
1.心の奥に眠る「ほんとうの願い」に耳を澄ます
普段、周りの期待や「こうあるべき」という考えに隠れてしまいがちな、ご自身の心の奥底にある素直な欲求、「わがまま」とも呼べるような純粋な願いに気づいてみましょう。
それは、「もっとゆっくり過ごしたい」かもしれませんし、「誰にも邪魔されずに好きなことに没頭したい」かもしれません。 一見すると社会的な目標とはかけ離れていても、それが自分の心を動かす大切なエネルギー源になることがあります。 「もし何の制約もなかったら、一番何をしたい?」と自分に問いかけてみてください。
2.日常の中の「小さな好奇心」を追いかける
「これは何だろう?」「少しだけやってみたいな」と、ふと心が動いた瞬間。 どんなに些細なことでも、その「小さな好奇心」は、進むべき方向を指し示す大切なサイン。 気になる本の一節、誰かの話、街で見かけたもの。見過ごせずにメモしておきましょう。
3.「不快」や「違和感」の「反対側」をのぞいてみる
「今、何がイヤだと感じているか」「どんな状況がしっくりこないか」をはっきりさせることもヒントになります。 その不快感の裏返しが、ご自身の望む状態を示していることが多いから。
たとえば、「人に気を使いすぎて疲れる」なら、その反対には「もっと自分のペースで過ごしたい」という願いがあるかもしれません。
4.過去の「夢中になったこと」を思い出す
時間を忘れて何かに夢中になったり、心から「楽しい!」と感じたりした経験。 そのときの感情や、何に惹かれたのかを思い出してみるのも良いでしょう。 過去の輝いていた瞬間の中に、今の自分を導くヒントが隠れていることがあります。
このステップで見つけるのは、壮大な目標である必要はありません。 「なんとなく気になる」「少しだけ気分が上向く」といった、ささやかな心の動き、それが最初の「小さな光」。 その小さなサインを信じて、まずはほんの少しだけ試してみること。それが、迷子の状態から抜け出す確かな一歩となります。
心のスイッチ・ステップ2:「小さな光」を頼りに、まず一歩だけ踏み出す
ステップ1で、心の中に「小さな光」を見つけましたね。 しかし、その光がどんなに小さく、ぼんやりとしていても、次の一歩をためらってしまうかもしれません。 「本当にこの方向でいいのだろうか?」「もっと確かなものが見つかるまで待つべきでは?」と。
ここで大切な「心のスイッチ」があります。それは、「完璧な確信を得てから動こうとすること」が、実はずっと行動を妨げる「ワナ」であることに気づくこと。 絶対的な正解や保証を待っていると、いつまでたっても最初の一歩は踏み出せません。
むしろ、その「小さな光」や「なんとなくの感覚」を信じて、まず一歩踏み出してみること。 それが、迷いの霧を晴らす最も確実な方法なのです。
なんとなくの感覚は、潜在意識からのサインかも
「理由はうまく説明できないけれど、なんとなくこちらに惹かれる」 「特に強い動機はないけれど、これは少し続けてみてもいい気がする」 ステップ1で見つけた「小さな光」は、しばしばこのような言葉にならない感覚を伴います。
実は、こうした「なんとなくの感覚」の中には、ご自身の経験や知識が蓄積された潜在意識からの、大切なメッセージや根拠が隠れていることがあります。 普段、頭で考えているだけでは見つからないような、本当に進みたい方向を、その「なんとなく」が教えてくれているのかもしれません。
だからこそ、その直感を信じてみる価値があるのです。 では、その「小さな光」を頼りに、具体的な一歩を踏み出すための工夫をみていきましょう。
1.「小さな光」から「ほんの小さな行動」を一つだけ見つける
ステップ1で見つけた「小さな光」(興味、関心、過去の経験、心の奥の願いなど)に関連して、今日中にでもできる、簡単な行動を一つだけ具体的にしてみましょう。
「気になる本があったら、目次だけ見てみる」「興味のある分野の入門記事を一つだけ読んでみる」「過去に楽しかったことを、もう一度少しだけ試してみる」 大切なのは、考えすぎず、ごく単純で、すぐに取りかかれることを選ぶこと。
2.「お試し」の気持ちで、その一歩を実行する
その小さな行動を、「壮大な計画の第一歩」と気負うのではなく、「この光の方向で合っているか、ちょっと試してみよう」くらいの軽い気持ちで実行します。 結果がどうであれ、それは「実験」であり、貴重なデータ収集。 成功や失敗という二択で判断する必要は全くありません。
3.一歩動いた後の「心の声」に丁寧に耳を澄ます
その小さな行動を終えた後、どんな気持ちになったでしょうか。 少しワクワクしましたか? 思ったより気が進みませんでしたか? あるいは、何か新しい発見が・・・。 その行動を通じて感じたこと、考えたこと、それが次の「小さな光」や、進むべき方向の調整に繋がる大切な手がかりとなります。
この感覚を丁寧に拾い集めることが、迷いを抜け出すために、次にご自身が進むべき方向を示すものとなるのです。 「完璧な確信」を待つのではなく、心の中の「小さな光」と「なんとなくの感覚」を信じて、まず一歩。 その一歩が、必ず次の景色を見せてくれるはずです。
心のスイッチ・ステップ3:行動と結果を「見積り」、粘り強く進む
ステップ2で、心の中の「小さな光」を頼りに、ほんの小さな一歩を踏み出しましたね。 しかし、その一歩だけですぐに大きな変化を感じられず、「やっぱりダメかも…」と心が折れそうになることは、本当によくあること。多くの場合、私たちが想像している以上に、目に見える成果が出るまでには時間がかかるものです。
特に始めたばかりのころは、その感覚が分からないため、少し進んでも変化がないと、そこで行動が止まってしまいがち。 そこで大切なのが、最初のうちは「行動と結果の見積り合わせ」をするような感覚で進むという「心のスイッチ」。
これは、焦らず、がっかりせず、粘り強く行動を続けるための知恵となります。
1.最初の数歩は「どれくらいで、どう変わる?」の観察期間
まず理解しておきたいのは、踏み出した最初の数歩は、「どれくらいの行動をすると、どんな変化が(あるいは、変化が起こらないのか)が起こるのか」を体感し、推し量るための「観察期間」ということ。
大きな結果を期待するのではなく、「このくらいやってみたら、何かわかるかな?」という気持ちで、行動とその手応えを冷静に見つめてみましょう。
この「見積り合わせ」の期間を持つことで、やみくもな期待からくる早期の挫折を防ぐことができます。
2.「小さな変化」にも、積み重ねと工夫が必要と知る
「見積り合わせ」をしてみると、多くの場合、「ほんの少し良い変化」を起こすためにも、意外と多くの行動の反復や、やり方の改善が必要だということが見えてきます。
たとえば、「毎日ブログを書いても、すぐには読者が増えないんだな」「この勉強法だと、1週間で覚えられるのはこの範囲か」というように。 この現実的な感覚を掴むことが、実はとても大切。
「すぐに結果が出ないのは当たり前。工夫しながら続けることが大事なんだ」と理解できれば、焦りが減り、落ち着いて取り組めるようになります。
3.理解した上で「粘る」力が、道を拓く
「結果が出るまでには時間がかかり、反復と改善が必要だ」ということを、頭だけでなく体感として理解できると、そこから本当の「粘り強さ」が生まれます。
それは、ただ闇雲に我慢することとは違う。 見通しを持った上で、「よし、もう少し続けてみよう」「次はこう工夫してみよう」と、前向きに工夫しながら努力を続ける力です。
ステップ1で見つけた「小さな光」を頼りに、ステップ2で踏み出した一歩。 その一歩から得た「見積り」を元に、この「粘る力」を発揮して行動を続けることで、必ず道は拓けていきます。 焦らず、ご自身のペースで、昨日よりほんの1mmでも前に進んでいることを感じながら、続けていきましょう。
心のスイッチ・ステップ4:感情の波を抑え、しなやかに進路を調整する
ステップ3で、小さな一歩を踏み出し、その結果から「次の1mm」を見つけるヒントを得ました。 しかし、実際に進み始めると、予想外の出来事が起きたり、思ったような手応えが得られなかったりして、心が大きく揺れ動くこともあるでしょう。
ここでは、そんなときでも冷静に進路を調整し、しなやかに前進し続けるための「心のスイッチ」をご紹介。
1.まず大切な気構え:結果に一喜一憂せず、「淡々」と向き合う
行動している最中は、感情の波をできるだけ小さく保つことを意識してみましょう。 少しうまくいったからといって有頂天になったり、逆になかなか進まないからといって深く落ち込んだり。 そうした感情の大きな揺れは、冷静な判断や次の行動を妨げることがあります。
一つ一つの行動の結果は、「何が起こるかな?」と観察するような気持ちで、淡々と受け止めるのです。 そして、その結果を踏まえて「では、次はどうしようか?」と、これまた淡々と次の修正点や改善策を考える。 この「淡々と受け止め、淡々と修正する」という姿勢が、軌道修正をスムーズにするための基本となります。
2.「完璧な道筋は最初からない」と心得える
多くの場合、物事を始める前に完璧な計画や、間違いのない一直線の道筋が見えていることの方が稀。 「やってみないと分からない」ことだらけなのが普通だと心得ておきましょう。 この前提に立てば、計画通りに進まないことや、途中で迷うこと自体が、自然なプロセスの一部として受け入れやすくなります。
3.どんな結果も「次への貴重な情報」と捉える
進んでみて「何か違うな」「うまくいかないな」と感じることは、決して「失敗」ではありません。 それは、「この方法は合わないようだ」「ここを改善する必要がある」ということが具体的に分かった、という貴重な「情報」を得たということ。
逆に、少しうまくいったとしても、「なぜうまくいったのか」「もっと良くするにはどうすればいいか」を考える。
つまり、どちらに転んでも、そこから次への行動を改善・修正するためのヒントが得られるのです。 この「常に修正は必要」という感覚を持つと、どんな結果も前向きな力に変えられます。
4.プロセス全体から学び、成長を楽しむ
明確なゴールに一直線でたどり着くことだけが価値なのではありません。 試行錯誤したり、遠回りしたり、時には立ち止まって考えたりする、そのプロセス全体にこそ、たくさんの発見や学び、そしてご自身の成長の機会が詰まっています。
結果だけでなく、その過程で何を感じ、何を考え、何ができるようになったのか。 そうしたプロセスに目を向けることで、一見すると「迷っている」ように見える時間も、実は豊かな経験として積み重なっていくのです。
このステップの「心のスイッチ」は、不確実な状況を恐れるのではなく、それを「学びと成長の機会」と捉え、感情に振り回されずに柔軟に対応していく力を育てること。
心のスイッチ・ステップ5:「迷い」を成長に変え、進む力を育む
これまでのステップで、小さな光を見つけ、一歩を踏み出し、結果を見積もり、進路を調整するという、いわば「手探りの冒険」を続けてきましたね。
この最後のステップでは、その冒険を通じて得たものを確かな自信に変え、これからも「迷いながら進む自分」を支えるための「心のスイッチ」をご紹介します。
1.「迷うこと」は、新しい発見のチャンスと知る
「また道に迷ってしまった…」そう感じることもあるかもしれません。
しかし、迷うということは、決して悪いことではない。 むしろ、新しい道や考え方、あるいはご自身も気づかなかった可能性を発見する絶好のチャンスなのです。
一本道だけを進んでいたら見えなかった景色が、迷うことで初めて見えてくることもあります。 「迷っている今この瞬間も、自分は何かを学んでいるんだ」と、前向きに捉えてみましょう。
2.日々の「小さな進歩」を意識して見つける習慣
行動迷子タイプの方は、目に見える大きな結果が出ないと、「何も進んでいない」と感じてしまいがち。 そこで、日々の本当にささやかな「進歩」や「できたこと」を、意識して『見つけ出す』習慣をつけましょう。
たとえば、昨日よりほんの少しだけ、行動への抵抗感が減った。新しい情報を一つ見つけられた。 迷ったけれど、また次の一歩を考えようとしている自分がいる。
これらは全て、大切な進歩です。 日記やメモに書き出すのも良い方法。この「見つける」という能動的な行為が、ご自身の成長を具体的に実感させ、次への意欲を育てます。
3.「自分で考え、行動できた」経験こそが財産
結果がどうであれ、「誰かの指示ではなく、自分で考え、自分で選んで行動できた」という経験は、何ものにも代えがたい財産となります。 その一つ一つの経験が、「自分は自分の力で進んでいけるんだ」という、内側からの自信の土台を築いてくれます。
「あの時、迷いながらも自分で決めて動いたな」という記憶を、大切に積み重ねていきましょう。
4.これからも「迷える自分」を信頼する
この先も、また道に迷うことはあるでしょう。 でも、今のご自身はもう、以前のご自身とは違います。 心の中に「小さな光」を見つけ、最初の一歩を踏み出し、結果から学び、軌道修正し、そしてそのプロセスで成長できることを、もう知っているはず。
「たとえまた迷っても、自分ならまた新しい道を見つけ出せる」 そうご自身を信頼する心構えこそが、行動迷子タイプの方が不確実な世の中を歩んでいく上で、最も力強い「心のスイッチ」となるでしょう。
「自信がもてないタイプ」の方へ:5つの心のスイッチ・ステップ

心のスイッチ・ステップ1:「自信がないとダメ」という思い込みに気づく
「どうせ自分には無理だ…」 「もっと自信があれば、きっと挑戦できるのに…」 心の中で、そんな声が聞こえてくることはありませんか。 「自信がもてない」と感じていると、行動する前から諦めてしまったり、一歩を踏み出すことがとても重く感じられたりしますよね。
でも、ここで一度立ち止まって考えてみてほしいのです。 「そもそも、行動するために『自信』は絶対に必要なのでしょうか?」 もしかしたら、「自信がないけれど、だからといって、それが行動できない絶対的な理由になるのだろうか?」と、少し肩の力を抜いてみる。
いっそ、「自信がないのは今の自分。それが何か?」くらいの気持ちで、自信の有無を一旦脇に置いてみるのも、一つの大切な考え方かもしれません。
実は、多くの方が「自信がつくのを待ってから行動しよう」と考えがちですが、それがかえって行動を遠ざけてしまう「心のワナ」になっていることが。
なぜなら、「自信」というものには、明確な基準や数値があるわけではないからです。 どれだけ成果を上げても、「もっと上がいるから」と満足できなかったり、逆に小さな変化でも「できた!」と喜べる人もいます。
つまり、「うまくいったかどうか」の感じ方は、ご自身の心の状態や評価の仕方に大きく左右されるのですね。 ですから、「自信の有無」を行動するかどうかの判断基準にしない。 これが、このタイプの方がまず手にしたい「心のスイッチ」です。
その上で、ご自身の行動を止めているかもしれない、頭の中の「ダメ出しの声」の存在に気づいてみましょう。
- どんな時に「自分はダメだ」「どうせ無理だ」という声が聞こえてきますか?
- (例:新しいことを始めようとするとき、誰かと自分を比べたとき、少しでもうまくいかないことがあったときなど)
- その「ダメ出しの声」は、具体的にどんな言葉でささやいてきますか?
- (例:「また失敗するよ」「才能がないんだから」「周りはもっとうまくやっている」など)

その声は、本当に「絶対的な真実」を語っているのでしょうか?それとも、ただの「繰り返される思考のクセ」や「過去の誰かの言葉」かもしれませんか?
このステップでは、まず「自信がないから行動できない」のではなく、「自信がなくても行動していいんだ」という新しい視点を持つこと。
そして、行動を妨げている「ダメ出しの声」の正体を見つめ、それとご自身とを少し切り離して眺めてみることを目指します。 その声に気づき、距離を置くことが、自信の有無に関わらず一歩を踏み出すための大切な準備となるのです。
心のスイッチ・ステップ2:見過ごしている「自分の良さ」に光を当てる
ステップ1で、「自信の有無を行動の基準にしない」という新しい視点と、頭の中の「ダメ出しの声」に気づくことの大切さを確認しました。
次に行うのは、その「ダメ出しの声」にかき消されて、普段は見過ごしてしまっているご自身の「良さ」や「できていること」に、意識的に光を当てる練習。なぜ「自分の良さ」に気づきにくいのか 多くの場合、私たちが「できること」や「自分の強み」として認識するのは、何か特別な努力をしたり、困難を乗り越えたりした「手応えのある」事柄。
しかし、無意識に、当たり前のようにできてしまうこと、つまりご自身にとっては何の苦労も感じないことは、「できて当然」と捉え、自分の能力や強みとして数えていないことがほとんどなのです。
たとえば、靴のひもを結べることを、わざわざ「自分のできること」として挙げる人は少ないでしょう。でも、それも立派な能力の一つ。 ご自身の「強み」も同様で、あまりにも自然にできてしまうために、自分では「強み」だと気づいていないケースが非常に多いのです。
ここでは、そんな隠れた「自分の良さ」を見つけ出すための三つのヒントをご紹介します。
1.「当たり前にできていること」を丁寧に見つける
まずは、日常生活の中で「当たり前」にやっていること、自然にこなしていることを、意識して拾い上げてみましょう。 「朝、時間通りに起きる」「食事の準備をする」「誰かの話を聞く」など、どんな些細なことでも構いません。
これらは全て、ご自身が持つ能力や習慣の結果。「ダメ出しの声」が「そんなの当然だ」と言ってきたら、「それでも、ちゃんとできている自分は確かだ」と、事実を客観的に認めてあげましょう。
2.「なぜか気になること」から強みを探る
ご自身の強みは、意外なところにも隠れています。
たとえば、周りの人の行動を見て、少しイライラしたり、「なぜ、この人はこれができないのだろう?」と感じたりすることはありませんか。 そう感じるということは、ご自身にとってはそれが比較的簡単にできる、得意なことである可能性が高い。
日々の生活の中で、ほんの小さな良い変化や、周りの人からの(たとえお世辞だとしても)肯定的な反応はありませんか。 それらも、ご自身の何か良い影響力を示しているのかもしれません。 こうした「なぜか気になる」という心の動きは、自分の隠れた能力や強みを教えてくれる大切なサインです。
3.「すごい強み」より「ちょっとした良さ」の組み合わせを意識する
「自分には、人に誇れるような『ぶっちぎりの強み』なんてない…」と思うかもしれません。
しかし、ほとんどの人の独自の良さ(オンリーワンの強み)というのは、何か一つの飛び抜けた能力ではなく、「これは、人より少し得意かもしれない」「これは、少しだけ丁寧にできる」といった、複数の「ちょっとした良さ」の組み合わせでできているもの。
たとえば、「人の話を丁寧に聞ける」と「分かりやすく説明するのが少し得意」という二つが組み合わされば、それは素晴らしいコミュニケーション能力という「強み」になります。
ご自身の「ちょっとした良さ」をいくつか見つけて、それが合わさったときの独自の価値を考えてみましょう。
このステップは、自分に対する見方を変え、「自分にも良いところがある」「自分も意外と色々できている」という事実を、一つ一つ丁寧に確認していく作業。
「心のスイッチ」を入れ、意識的にご自身の「プラスの側面」を探し、認めていくことで、自信のなさからくる行動へのブレーキが少しずつ和らいでいくはずです。
心のスイッチ・ステップ3:『自信がなくても、まずやってみる』小さな実験を繰り返す
ステップ1と2を通じて、読者の方は「自信がなくても行動していい」という新しい視点と、ご自身の見過ごしていたプラス面への気づきを得ました。
しかし、いざ行動しようとすると、長年の「自分にはできない」という感覚が顔を出し、再び足がすくんでしまうかもしれません。
そこでステップ3では、その「自信のなさ」を抱えたままでも、具体的な行動を小さく始められるような「実験的アプローチ」をご提案。
1.「自信の有無」と「行動の可否」を切り離して考える
「自信がないからできない」のではなく、「自信がないけれど、この小さなことなら試せるかもしれない」という思考に転換する。
2.「実験」と位置づけ、結果への期待値を下げる
これから行う小さな行動を「成功か失敗か」で捉えるのではなく、「試してみて、何が起こるか観察する実験」と位置づける。 実験なので、どんな結果も「データ」として価値がある。
3.超・具体的な「最初の小さな一歩」を設定する
何か気になること、あるいは少しでも「やった方がいいかな」と思うことについて、「5分だけ調べてみる」「最初の1行だけ書いてみる」「誰かに挨拶だけしてみる」など、行動のハードルを極限まで下げた「赤ちゃんステップ」を設定。
4.行動中は「結果」よりも「やっていること自体」に集中する
「うまくできるだろうか」「失敗したらどうしよう」という思考から意識をそらし、目の前の「やっている作業」そのものに集中する時間を作る。
5.「実験」後の振り返りは、評価ではなく「観察記録」として
「うまくいった/いかなかった」という評価ではなく、「やってみたらこう感じた」「こんなことが分かった」という客観的な観察記録として捉える。
それが次の小さな実験のヒントになる。 このステップは、読者の方が「自信がない自分」を否定せず、その状態のままでも行動を試し、その行動から学びを得ていくという、新しい成功体験のサイクルを作り出すことを目指します。
心のスイッチ・ステップ4:自分への「ダメ出し」と「できた探し」のバランスを取る
ステップ3で、「自信がなくても、まずやってみる」小さな実験を始めましたね。 その小さな一歩を踏み出した自分を、客観的に見つめ、肯定的に捉えていくことが、このステップ4のテーマ。
自分の欠点やできなかったことには非常に敏感で、次から次へと見つけ出すのが得意。 その一方で、うまくいったことや、ささやかな成功、日々できていることには驚くほど「鈍感」で、ほとんど意識に上らないか、すぐに忘れてしまうのです。
これでは、いくら行動を重ねても、「自分はダメだ」という感覚ばかりが強まってしまいますよね。 大切なのは、このアンバランスを意識的に修正し、「ダメ出し」と同じくらい、あるいはそれ以上に、「できたこと探し」にも敏感になること。つまり「バランス」です。 ここでは、そのための具体的な「心のスイッチ」をご紹介。
1.比べる相手は「他人」ではなく「過去の自分」だけ
自信がないときは、つい周りの輝いて見える人と自分を比べてしまい、「それに比べて自分は…」と落ち込みがち。
しかし、他の人とご自身とでは、持っているものも、経験も、置かれた状況も全く違います。 比べること自体にあまり意味はありません。
もし比べるのであれば、その相手は「過去の自分」。 昨日よりほんの少しでも気分が前向きになった、先週はできなかった小さなことが今日はできた、一ヶ月前よりも行動への抵抗感が減ったなど。
ご自身のペースでの「小さな進歩」に目を向け、それをきちんと認めてあげましょう。
2.頭の中の「ダメ出しの声」を「応援の声」に切り替える練習
ステップ1で気づいた「ダメ出しの声」。それが聞こえてきたら、意識的にストップをかけ、それをご自身を励まし、応援する言葉に置き換える練習をしてみましょう。
たとえば、「やっぱり自分はダメだ」という声が聞こえたら、「いや、今日はここまでできたじゃないか」「少しでも試そうとした自分はえらいよ」「次はこうしたらもっと良くなるかもね」と、優しい言葉をかけてあげるのです。
最初はぎこちなくても、繰り返すうちに、自然と自分を応援できるようになっていきます。
3.「できたこと・良かったこと」日記をつける
どんなに小さなことでも構いません。その日に「できたこと」「良かったこと」「少しでも成長を感じたこと」を、毎日数分でいいので書き出してみる習慣をつけましょう。
「朝、決めた時間に起きられた」「気乗りしない作業を、5分だけ手をつけることができた」「人からの小さな親切に気づけた」など、日常のささいな出来事の中に「できた自分」「良かった状況」を見つけ、記録することで、「うまくいったことへの鈍感さ」を改善し、客観的に自分のプラス面を認識する助けになります。
4.自分自身への「ねぎらい」と「感謝」を言葉にする
小さなことでも行動できた自分、一日を頑張った自分に対して、心の中で「お疲れ様」「よくやったね」「ありがとう」と、ねぎらいや感謝の言葉をかけてあげましょう。
これは、ご自身を大切に扱い、自己肯定感を育む上でとても大切な習慣。「ダメ出し」ばかりしていた自分に、意識して優しい言葉をかけることで、心のバランスが整ってきます。
このステップは、ご自身に対する見方、評価の仕方の「バランス」を取り戻すためのもの。 「ダメ出し」の達人から、「自分の良さや頑張りを見つける達人」へと、少しずつシフトしていきましょう。
心のスイッチ・ステップ5:長所も短所も「まるっと」受け入れ、自分を活かす
ステップ4までで、ご自身のプラス面を見つけ、過去の自分と比べながら優しい言葉で成長を認める練習をしてきました。
この最後のステップでは、自信の有無に振り回されない、もっと深く、揺るぎない自己肯定感を育むための「心のスイッチ」をご紹介。
「ないものねだり」から「あるもの活かし」へ
多くの場合、「自信がもてない」と感じている方は、ご自身に「ないもの」や「足りない部分」に意識が向きがち。 「もっと〇〇があれば自信が持てるのに…」と。
しかし、その「ないものねだり」の状態では、いつまでも満たされず、本当の意味での自信には繋がりにくいものです。
ここで大切なのは、ご自身の長所も短所も、良いところもそうでないと感じるところも、全てをひっくるめて「これが今の自分だ」と、まるっと受け入れること。
この「まるっと受け入れる」という覚悟ができて初めて、本当の意味で自分を活かす道が見えてきます。 これができないと、いつまでも自分以外の誰かになろうとして、自信に繋がる行動は起こしにくいのです。
「短所」を受け入れると、新しい「強み」が見えてくる
ひとつ、例え話をさせてください。バスケットボール選手になりたいけれど、身長が低いことに悩んでいる人がいたとします。
もし、この人が「自分は背が低いからダメだ」と、その事実を受け入れられず、背の高い選手と同じようにゴール下で勝負しようと練習し続けたら、どうなるでしょうか。
おそらく、なかなか結果は出ず、ますます自信を失ってしまうでしょう。それは、「背が低い」という変えられない事実(短所)から目をそむけているから。
しかし、もしこの人が「自分は背が低い。これはバスケットボール選手としては確かに不利な点だ」と、その事実を一度しっかりと受け入れたらどうでしょう。
すると、「では、背が低くても活躍できる道はないだろうか?」と、別の可能性に目が向くはず。
「背の高い選手にはないスピードを磨こう」「相手を翻弄するトリッキーなパスやドリブルを徹底的に練習しよう」と。 つまり、一見デメリットに思える「短所」を受け入れることで初めて、それを補って余りある、自分だけの新しい「強み」を開発する道が開けるのです。
「ありのままの自分」で行動を選ぶ
これは、バスケットボールに限った話ではありません。
ご自身の「短所」だと感じている部分も、見方を変えれば、あるいはそれを受け入れた上で別の何かを磨けば、それが独自の魅力や強みになる可能性を秘めています。
大切なのは、完璧ではない「ありのままの自分」を否定せず、その自分で「今できること」「やってみたいこと」を選び、行動していくこと。
行動の結果がどうであれ、その経験がまた新たな自分を教えてくれます。 「心のスイッチ」は、自分にないものを追い求めるのではなく、今の自分をまるっと受け入れ、その自分だからこそできることを見つけ、行動していくことを選ぶ手助け。
自信は、後からついてくるおまけのようなものかもしれません。 まずは、「この自分でいく」と決めること。それが、何よりも力強い一歩となるでしょう。
行動への抵抗感を軽くする工夫

まずは「これならできる」ことから試す
結論からいいます。
行動の目的をはっきりさせ、本当に「やる意味がある」と感じたことだけを始めてみましょう。
繰り返しになりますが、ご自身が「やる意味がある」と感じたことだけ。 とにかく、実行に移すための心の負担を軽くするのがコツ。 絶対にやり遂げられる、と思えるくらいまで難易度を下げてみてください。 たとえば、転職を考えたとします。
いきなり転職エージェントへ登録するのは、少し気後れするかもしれません。 そういうときは、まず「転職したい理由を書き出す」ことから始めます。 または「今の仕事や会社の問題点を整理する」のもよいでしょう。 あるいは「転職せずに済む方法はないか、考えてみる」など。 これくらいの小さなことからなら、行動への抵抗感はぐっと下がるはず。
このように、行動への心のハードルをとことん下げることが、次の一歩をうながす大切なポイントといえます。 そして、ハードルを下げて行動に移してみると、本当に必要な情報が集まってくることに気づくでしょう。
この場合の必要な情報とは、たとえば記事の前半でお伝えした「行動する前に考えるべき4つのポイント」のような、ご自身の行動の軸となるもの。
頭で考えているだけでは分からなかったことが、少し動いてみることで見えてきます。 「この行動には、どんな意味があるのだろう」という答えも、その情報の一つ。
行動に移せない多くの場合は、情報が足りないか、頭の中が整理できていないことが原因かもしれません。
行動の目的を明確にする4つの問い
 「行動力がない」と感じるのは、その行動が今のご自身に不要だったり、目的が曖昧で心がブレーキをかけていたりするからかもしれません。 やみくもに動く前に、一度ご自身の心に尋ねてみましょう。 行動する前に考えてほしい、4つの問いかけをご紹介します。 ご自身の正直な「心の声」に、耳を傾けてみてください。
「行動力がない」と感じるのは、その行動が今のご自身に不要だったり、目的が曖昧で心がブレーキをかけていたりするからかもしれません。 やみくもに動く前に、一度ご自身の心に尋ねてみましょう。 行動する前に考えてほしい、4つの問いかけをご紹介します。 ご自身の正直な「心の声」に、耳を傾けてみてください。
- その行動は、本当に今の自分に必要だろうか?
- (心の声の例1:「うん、これを経験することが、今の自分の成長にきっと繋がるはずだ」)
- (心の声の例2:「うーん、周りは勧めるけれど、今の自分には他に優先したいことがあるような…」)
- 誰か他の人の意見や期待に、流されてはいないだろうか?
- (心の声の例1:「これは、周りが何と言おうと、自分が心からやりたいことだ」)
- (心の声の例2:「みんなが良いと言うから考えたけど、自分の本心とは少し違う気がする…」)
- その行動をする、ほんとうの目的は何だろうか?
- (心の声の例1:「これを達成することで、自分も周りも幸せになるイメージが湧く」)
- (心の声の例2:「目的を考えてみたけど、ぼんやりしていて、なぜやりたいのか自分でもよく分からない…」)
- もし期待した結果にならなくても、そこから何か少しでも得られるもの(たとえば経験や情報)はあるだろうか?
- (心の声の例1:「たとえ失敗しても、この経験自体が貴重な財産になると思う」)
- (心の声の例2:「もしうまくいかなかったら、時間も労力も全て無駄になってしまいそうでこわい…」)
これらの問いに、ご自身の心を照らしてみましょう。
もし答えにスッキリしない点(たとえば、上記の「心の声の例2」のような感覚)があれば、それは要注意。 本心に沿わない行動や、大きな負担を伴うサインかもしれません。
その場合は、無理に行動しなくてよいのです。 行動の目的が明確になり、心から「これはやる意味がある」「たとえ期待通りでなくても得るものがある」と感じられてこそ、本来の力が湧き出てくるもの。
うまくいかない経験も「次への糧さがし」と捉える
 誰だって、物事がうまくいかないのはイヤなものです。 しかし、何か新しい行動を始めるとき、最初からゴールまでの明確なステップが全て見えていることばかりではありませんよね。
誰だって、物事がうまくいかないのはイヤなものです。 しかし、何か新しい行動を始めるとき、最初からゴールまでの明確なステップが全て見えていることばかりではありませんよね。
多くの場合、私たちは一歩進んでは手応えを確認し、また次の一歩を考える、まるで暗い道を手探りで登っていくような作業を繰り返します。
この「手探りの道のり」こそが、実は「次への糧さがし」という、とても大切なプロセス。 うまくいかない経験も、その「糧」を見つけ出すための貴重な機会と捉える「心のスイッチ」をご紹介します。
「この経験から、何を持ち帰ろう?」と問いかける
期待通りに進まらなかったとき、大切なのは「この経験から何が得られたか?」「次に活かせるものは何か?」と、意識的に「糧」を探す視点。 それはまるで、山登りの途中で、次のルートのヒントになるような小さな発見や、体力を回復させる木の実を見つけるようなものです。
具体的には、以下のような点を振り返り、書き出してみるのが「糧さがし」のコツ。
- 「ああ、このやり方では、ここが足りなかったのだな」と、課題や改善点が具体的に見えた。(→次の行動の精度を上げる糧)
- 「この道は行き止まりだと分かった。では、別の道を探そう」と、新しい選択肢や方向転換の必要性に気づけた。(→より良い道を選ぶための糧)
- 「結果はともかく、この行動を通じて〇〇という体験はできた」と、新しい経験やスキルが少しでも積み上がった。(→自分自身の成長の糧)
- 「この挑戦がきっかけで、〇〇さんと話す機会が生まれた」と、思いがけない人との繋がりや協力関係ができた。(→未来の可能性を広げる糧)
このように、行動したからこそ得られたプラスの要素を、一つ一つ丁寧に「棚卸し」するのです。
そのためには、「たとえ期待通りでなくても、この経験から何か一つでも価値あるものを見つけ出すぞ」という、いわば「タダでは起きない」という積極的な心構えが、力強い「糧さがし」を後押しします。
うまくいかない経験は、その瞬間は気持ちが沈むかもしれません。 しかし、この「次への糧さがし」という視点を持つことで、全ての経験が未来の自分を豊かにし、着実に前へ進むための大切な「栄養」に変わっていくはず。
自己肯定感を高め、行動をうながす習慣
 なかなか行動に移せない背景には、ご自身の価値を低く見てしまう「自己肯定感の低さ」が隠れていることが。 自己肯定感が低いと、自信が持てず、何事にも消極的になりがちです。
なかなか行動に移せない背景には、ご自身の価値を低く見てしまう「自己肯定感の低さ」が隠れていることが。 自己肯定感が低いと、自信が持てず、何事にも消極的になりがちです。
しかし、自己肯定感は、日々の習慣によって少しずつ育んでいくことができるもの。 ここでは、過去の経験に光を当て、行動へのブレーキを和らげ、前向きな気持ちを支える三つの習慣をご紹介します。
1.過去の体験から「うまくいったこと」を多角的に掘り起こす習慣
まずは、ご自身の人生の様々な場面から、「うまくいったな」「これは達成できたな」と感じる体験を、大小問わず意識的に掘り起こしてみましょう。
大きな成果だけが「成功」ではありません。ご自身が「これは自分なりに頑張った」「これで少し状況が良くなった」と感じられるなら、それは立派な「うまくいったこと」。
たとえば:仕事で、難しい課題を乗り越えたり、目標を達成したりしたこと。 学業で、粘り強く勉強して試験に合格したり、何かを習得したりしたこと。
人間関係で、誰かと良い関係を築けたり、誰かの助けになれたりしたこと。 趣味や日常生活で、何かを成し遂げたり、続けていたりすること。
ポイントは、結果の大小だけでなく、そのときの状況、ご自身の行動や気持ちなども一緒に思い出してみること。 記憶を辿り、できるだけ多くの「うまくいったこと」の材料を集めてみましょう。
2.掘り起こした体験から「自分だけの成功パターン」を見つけ出す習慣
次に、集めた「うまくいったこと」の体験をじっくりと見つめ直し、そこに共通する「自分ならではの成功パターン」を探し出します。 「成功パターン」とは、ご自身が物事をうまく進めやすいときの、考え方、行動の仕方、環境などの特徴のこと。
たとえば、こんな問いかけを自分にしてみましょう:
- うまくいったとき、自分はどんな気持ちで取り組んでいたか?(例:楽しんでいた、集中していた、少し緊張感があったなど)
- どんな準備や段取りをしていたか?
- 誰かの助けを借りたか?それはどんな助けだったか?
- どんな環境や状況が、自分にとってプラスに働いたか?
- 困難に直面したとき、どうやって乗り越えようとしたか?
これらの問いに答えていく中で、「自分は、〇〇な状況で、△△というやり方をすると、力を発揮しやすいようだ」といった、ご自身だけのパターンが見えてくるはず。
この「自分だけの成功パターン」を理解することが、今後の行動を選択する上での強力な「指針」となります。
3.「なぜ?」を繰り返し、自分と深く対話する
自己肯定感を育み、「自分だけの成功パターン」をより深く理解するには、ご自身の内面と向き合い、本当の気持ちや価値観を明確にすることも大切。
日常の出来事や感じたことに対して、「なぜそう感じたのだろう?」「本当はどうしたかったのだろう?」と、自分に問いかける時間を持ってみましょう。
すぐに答えが出なくても構いません。自分に問いかけ続けること自体が、自己理解を深め、ぶれない自分軸を育むことに繋がります。 特に、過去の成功した記憶がなかなか思い出せない、あるいは失敗体験の印象が強く残っていて、なかなか前向きになれないという場合もあるでしょう。
このような、ご自身の思考のクセ(ネガティブ・バイアス)を乗り越えるには、やはり自分自身に対するより深い問いかけが効果的。
- そこで、「自己肯定感を高める100の質問集」をご用意しました。
この質問集は、ご自身との対話をこれまでにないレベルで深めるお手伝いをいたします。 どうしようか迷いましたが、悩まれている方が大変多いため、当面の間は無料で配布することにいたしました。
但し、いつまで無料で配布するかは分かりません。ご必要と思われる方は、今すぐ入手して保存されることをおすすめいたします。
下記からどうぞ。
これらの習慣は、一朝一夕に大きな変化をもたらすものではないかもしれません。
しかし、毎日少しずつ続けることで、ご自身の心の中に「自分はこれでいいんだ」「自分は大丈夫だ」という温かい感覚が、ゆっくりと、でも確実に育っていくはず。
それが、新しい一歩を踏み出す上での、何よりの力となるでしょう。
まとめ:今日からできる小さな変化
 ここまで、行動できない、怖いと感じる心を軽くし、ご自身の力で一歩を踏み出すための「心のスイッチ」について、様々な角度からお伝えしてきました。
ここまで、行動できない、怖いと感じる心を軽くし、ご自身の力で一歩を踏み出すための「心のスイッチ」について、様々な角度からお伝えしてきました。
ご自身のタイプに気づき、具体的なステップや共通のヒントを読んでいただく中で、何か心に響くもの、試してみたいと感じるものは見つかったでしょうか。
ここで、行動そのものの「意味」について、大切なことをお伝えしたいと思います。 「行動すること自体には意味がない」という考え方もありますが、私は少し違う意見を持っています。
むしろ、どんな小さな行動にも、必ず何らかの意味や価値が潜んでいるのではないか。 そして、最も重要なのは、行動した「後」で、「この行動は、自分にとってどんな意味があったのだろう?」と、ご自身でその意味を見つけ出し、納得することだと考えます。
この「行動の意味づけ」を意識することで、たとえ期待通りの結果が出なくても、その経験から何かを学び、それを糧として「よし、次へ進もう」と、前向きな気持ちで納得感を持って歩み続けることができます。
不思議なことに、そうした姿勢が、結果的に次の行動へのハードルを自然と下げてくれることも多いのです。 この記事でお伝えしたたくさんのヒントの中から、今の自分に一番しっくりくるもの、一番「これならできるかも」と思えるものを、まずは一つだけ選んでみてください。 それは、
- ご自身の「こわさ」のタイプを意識してみることかもしれません。
- 「赤ちゃんステップ」で、行動のハードルを思い切り下げてみることかもしれません。
- 頭の中の「ダメ出しの声」に気づき、優しい言葉をかけてみることかもしれません。
- あるいは、今日一日の中で「小さな良かったこと」を三つ見つけてみることかもしれません。
どんなに小さなことでも構いません。 大切なのは、今日、何か一つでも「新しい視点」に気づき、「ほんの少しでも試してみよう」という気持ちになること。
そして、試した後に「この行動には、どんな意味があったかな?」と優しく振り返ってみること。 その小さな変化と振り返りの習慣こそが、これまでの行動パターンを抜け出し、ご自身らしい一歩を踏み出すための、最も力強い「心のスイッチ」となるはずです。
この記事が、読者の方々にとって、心が軽くなり、するすると自然に行動できるようになるための一助となれば、これほどうれしいことはありません。
自分の見つめ直し完全マニュアル【無料】

行動力を高めるためには、ご自身を深く知ることが不可欠。 自分自身の内面を深く掘り下げると、何が私たちを動かし、何にブレーキをかけているのかを理解できます。
これらの要素を理解することで、私たちは自分に合った目標を設定し、それを達成するための適切な戦略を立てることができるのです。
今回ご紹介する 「自分の見つめ直し完全マニュアル」は、この大切な自己理解をうながすために、特別に作られたもの。
ご自身を深く掘り下げ、その本質を理解すると、行動を起こすための明確な道筋が見えてきます。 制作に10年の歳月をかけた逸品です。充実した内容は以下の通り。
- 自分の棚卸しに使える100の質問シート:自分自身を深く理解するための問いかけを提供し、長所や可能性を探るのに役立ちます。
- 自己肯定感を高めるための100の質問シート:自信を持って前向きに生きるための支援をします。
- 今の仕事合う?合わないチェックリスト:現在の職場環境が自分に合っているか評価するのに役立ちます。
- やる気ペンタゴンチャート:モチベーションを高め、行動を促すためのツールです。
- ときめきのツボワークシート:自分の情熱や興味が何にあるのかを探るのに役立ちます。
私の個人セッション(月々3万円)や講座の受講生たちを指導する際に使っているノウハウから厳選しました。配布を開始したその日、300人以上から申し込みがあったものです。
ただし、無料配布をいつまで続けるかわからないです。すいません。必要な人は、今すぐ入手して保存をおすすめします。
下記フォームにお名前とメールを入力するだけで入手できます。
こちらにLINE登録していただくと、自分らしく生きるための耳寄りなお話も公開してます。ブログには書けないここだけの情報も配信しています。

私との直接のやりとりもできますよ
最後に筆者からの大切なメッセージ

この記事を最後までお読みいただき、本当にありがとうございました。 ここまで、行動へのためらいや「こわさ」と向き合うための、様々な「心のスイッチ」や考え方についてお伝えしてきました。 いろいろなヒントがありましたが、最もお伝えしたい大切なことは、変化のきっかけは、常に「ご自身の内側」にあるということ。
完璧な答えや、誰かからの絶対的な保証を待つ必要はありません。 行動できない、怖いと感じる。それは、人間であれば誰にでも起こりうる自然な心の動き。 しかし、その感情にどう向き合い、どんな意味を見いだし、そしてどんな一歩をご自身で選び取っていくか。 その「選択する力」は、いつでもご自身の中に備わっています。
たとえ小さな選択であっても、その一つ一つの積み重ねが、昨日とは違う明日を創り、ご自身の人生をより豊かに、そして自分らしいものへと導いていくのだと、私は心から信じています。 この文章が、ほんの少しでもお役に立ち、読者の方の内なる力が、今日この瞬間から、より自由に解き放たれることを願ってやみません。
以上となります。
この記事を通じて、するする行動できるようになることを祈っています! ではまた。
魂の女性成長支援・浅野塾代表 浅野ヨシオ

浅野ヨシオ:
女性成長支援コンサルタント。
魂の女性成長支援・浅野塾 代表。
2007年よりビジネスパーソンや出版希望者を対象とした、自分の強みを発見し唯一無二のブランドを作る講師として活動。ハイキャリアの女性たちでも自分の能力がわからず強い自信を持てずにいることを知る。
2011年、女性成長支援の講座を起ち上げ、幼少期から現在までの人生史を平均200時間以上かけて深掘りする指導に定評がある。
通算15年2000人超の女性専門指導の経験により、心を縛る足かせをはずし、自分にとっての幸せを追求する自己実現プログラムを多数構築する。
著書に「私はこの仕事が好き!自分の強みを活かして稼ぐ方法(大和出版)」がある。
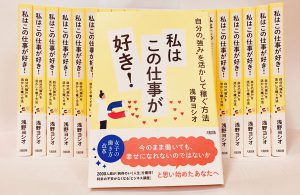
◎メディア実績:日本経済新聞/日経WOMAN/PRESIDENTほか多数
◎講演実績:横浜市経済観光局/多摩大学/NPO法人Woman’sサポート/自由大学/青森商工会連合会/天狼院書店/(株)スクー/ほか多数

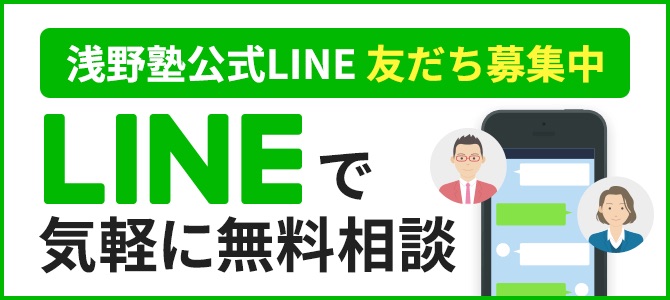


コメント