

一度はそんな理想を思い描いたことがあるのではないでしょうか。
情熱を注げることで生計を立てられれば、毎日は充実するはずですよね。
その一方で「好きなことは仕事にしないほうがいい」という反対意見もよく耳にします。
「収入が不安定になり生活が苦しくなるかも」
「そんなに甘い世界じゃないよ」
そんな声に一歩を踏み出せずにいる人も少なくありません。
この記事では、まず「好きなことを仕事にする」際に直面しがちな7つのデメリットを、体験談を交えながら解説します。
でも、ただ不安をあおるための記事ではありません。
それらのデメリットを乗り越え、後悔しないための事前対策まで、しっかりと紹介します。
この記事を読み終える頃には、「好き」を仕事にする光と影の両面が分かり、ご自身がどう向き合うべきか、その道筋が見えてくるはずです。
追伸:本文の最後に素敵なマニュアルのプレゼントをご用意しています。
- 記事を書いている人の専門性と実績
経歴:
新卒8ヶ月での挫折退職から再出発。26年の会社員経験(10年は複業)を経て起業。現在は個性を活かす道を拓く会社を経営。
専門:
好きなことを仕事にしたい人を含む、2000人超の女性指導実績。本当の強みを発見し、人生を新たな方向へ導くプロ。やりがいのある転職から起業まで、前職や年齢を超えた女性の夢実現に定評。
メディア/著書:
日本経済新聞、日経WOMAN他多数掲載。著書「私はこの仕事が好き!自分の”強み”を活かして稼ぐ方法(大和出版)」
好きなことを仕事にするデメリット7選
 好きなことを仕事にすると、どのような影の部分があるのでしょうか。
好きなことを仕事にすると、どのような影の部分があるのでしょうか。
その不安を言語化し、正しく向き合うことが後悔しないための第一歩です。
代表的な7つのデメリットを紹介しますね。
収入が不安定になるまたは減少する
 好きなことを仕事にする1つ目のデメリットは、必ずしも収入が安定するとは限らず、場合によっては経済的に苦しくなる可能性があることです。
好きなことを仕事にする1つ目のデメリットは、必ずしも収入が安定するとは限らず、場合によっては経済的に苦しくなる可能性があることです。
会社員であれば、毎月決まった日に一定の給料が振り込まれますよね。
しかし、フリーランスや起業という形で「好き」を仕事にした場合、その保証はどこにもありません。
【私の経験談】
私の運営する浅野塾を立ち上げる前、3年ほど業務委託という形で某企業の運営する講師の仕事をしていました。
週末だけ稼働する4ヶ月ほどの講座です。会場費や教材費は自己負担で、とてもやりがいを感じていた一方で、実質的な利益はわずか7万円から10万円ほど。
当時は会社員としての本業があったため生活に困ることはありませんでした。
でも、「教えるのが楽しいから」という理由でもし会社を辞めていたら生活は成り立たなかったでしょうね。
収入不安定の現実
自分の働きが直接収入に結びつくのは、確かに大きなやりがいの一つです。
その一方で、お客様からの依頼がなければ収入はゼロという厳しい現実も常に隣り合わせなのです。
情熱だけでは暮らしは成り立ちません。この現実をまっすぐに見ておくことが、後悔しないための第一歩です。
「好き」が精神的な「義務」に変わる
 好きなことを仕事にする2つ目のデメリットは、情熱をもって続けていたことが「やらなければならない」という精神的な義務に変わりやすい点です。
好きなことを仕事にする2つ目のデメリットは、情熱をもって続けていたことが「やらなければならない」という精神的な義務に変わりやすい点です。
-
私の知人の話が、この典型的な例です。
彼はゲームが大好きで、ゲームのプログラミング会社に就職しました。
しかし、実際の仕事は、ただ楽しいゲームを作ることではなかったのです。
プログラムのミスを細かくチェックしたり、厳しい納期に縛られたり、お客様の要望に応えたりと、精神的なプレッシャーの多い仕事でした。
作業の過程で、確認のために何度も同じゲームをプレイするうちに、もうプライベートでゲームをする気にはならなくなった、と話していました。
このように、純粋な遊びが「こなすべき仕事」に変わると、最初のときめきは失われがちです。
この「義務感」への変化こそ、多くの人が幻滅を感じる原因になりがちです。
好きだったことを本当に嫌いになる可能性
 好きなことを仕事にする3つ目のデメリットは、義務感やストレスが積み重なり、情熱そのものを失うリスクがあることです。
好きなことを仕事にする3つ目のデメリットは、義務感やストレスが積み重なり、情熱そのものを失うリスクがあることです。
先ほどお話しした「義務感」や日々のプレッシャーは、少しずつ心を摩耗させてしまいます。
すると、寝る間も惜しんで没頭できたことに心が動かなくなる。
あれほど楽しかったはずなのに、今はパソコンを開くのも作業場に向かうのも億劫に感じる。
そして、ある日ふと気づきます。
「なんで自分はこの仕事をしているんだっけ…」
これは、決して特別な話ではありません。
好きだったからこそ、理想と現実のギャップに人一倍苦しむことになる。
場合によっては愛情が憎しみに近い感情に変わることさえあります。
好きを仕事にした人にとって、これ以上悲しい結末はないかもしれませんね。
顧客の理想と自分の理想にズレが生じる
 好きなことを仕事にする4つ目のデメリットは、自分が「本当に良い」と信じて提供したいものと、お客様が求めるものとの間にギャップが生まれやすい点にあります。
好きなことを仕事にする4つ目のデメリットは、自分が「本当に良い」と信じて提供したいものと、お客様が求めるものとの間にギャップが生まれやすい点にあります。
旅行が好きだから、という理由で旅行代理店に就職する人は多いそうです。
しかし、そういった人たちの離職率は高いといいます。
なぜなら、仕事で求められるのは「自分が旅を楽しむこと」ではなく、「お客様に旅を楽しんでいただくこと」だからです。
自分が好きな場所や体験(自分の理想)と、お客様の予算や興味の中で求める満足(顧客の理想)は、必ずしも一致しません。
旅行の企画や添乗員の仕事は、お客様を喜ばせることにこそ、やりがいを感じる人に向いているのです。
このように、「好き」の方向が自分に向いているか、それとも他者に向いているか。 このズレに気づかずに仕事を始めると、「こんなはずではなかった」という壁にぶつかってしまうのです。
プライベートとの境界線があいまいになる
 好きなことを仕事にする5つ目のデメリットは、仕事とプライベートの境界線が溶けて、心身のバランスを崩しがちになることです。
好きなことを仕事にする5つ目のデメリットは、仕事とプライベートの境界線が溶けて、心身のバランスを崩しがちになることです。
当時、オートバイが好きでツーリングサークルに所属する傍ら、バイク便のアルバイトをしていたことがあります。
仕事となると、天気や気分に関係なく、一日中バイクに乗って時間に追われます。
すると、あれほど好きだったはずのオートバイに、プライベートで乗る気力がなくなってしまったのです。
仕事で「好き」を消費し尽くしてしまうと、純粋な趣味として楽しむエネルギーが心に残りません。
その結果、大切な息抜きの時間や、人生の遊びが失われる危険性があるのです。
お金をもらうことへの恐怖や罪悪感
 好きなことを仕事にする6つ目のデメリットは、趣味の延長意識から抜け出せず、プロとしてお金を受け取ることに抵抗を感じてしまうことです。
好きなことを仕事にする6つ目のデメリットは、趣味の延長意識から抜け出せず、プロとしてお金を受け取ることに抵抗を感じてしまうことです。
彼女は好きだった美容でサロンを開いた経験がありました。そのとき「お客様からお金をいただくのが怖い」と感じたそうです。
お金を受け取ることは、同時に「プロとしての責任」を背負うこと。
「もし期待に応えられなかったらどうしよう」 「趣味レベルだったのに、一気にプロの品質を求められる」 その恐怖に、心がすくんでしまった。
好きという純粋な気持ちが強い人ほど、「まだお金をもらえるレベルじゃない」と自分を安売りしたり、価格の設定に躊躇したりしてしまいます。
この心理的なブレーキは、事業を続ける上で、想像以上の壁になるのです。
ちなみに、彼女のサロンは1年半ほどで閉じたそうです。
「お金のブロック」は、好きなことを仕事にしたい人の多くがぶつかる根深い問題といえるでしょう。
こだわりすぎて採算が合わなくなる
 好きなことを仕事にする7つ目のデメリットは、好きだからこそ完璧を求めすぎて、ビジネスの採算が合わなくなるリスクです。
好きなことを仕事にする7つ目のデメリットは、好きだからこそ完璧を求めすぎて、ビジネスの採算が合わなくなるリスクです。
好きなことには、つい時間もお金もかけたくなりますよね。
「お客様に最高のものを届けたい」という気持ちは尊いものです。
しかし、そのこだわりが行きすぎると、自分の首を絞めることになります。
「あと少しだけ」と一つの作業に時間をかけすぎて、時間あたりの収益が極端に低くなってしまう。
最高の素材や道具を使わないと気が済まず、経費ばかりがかさんで利益がほとんど残らない。
このような状態では、どんなに素晴らしいものを作っても、事業として続けていくことはむずかしいです。
自己満足とビジネスの境界線が引けず、「作品」はできても「商品」として成り立たない。
これは、クリエイターや職人気質の人に陥りやすい落とし穴といえるでしょう。
情熱と採算のバランスをどう取るか。 これは、好きを仕事にし続ける上で、避けては通れない課題です。
デメリットを乗り越えるための3つの視点
 ここまで7つのデメリットを見て、少し不安な気持ちになったかもしれませんね。
ここまで7つのデメリットを見て、少し不安な気持ちになったかもしれませんね。
ここでは、デメリットを乗り越えるための3つの視点をご紹介します。
デメリットは成長痛のサインと心得る
 一つ目の視点は、これまで見てきたデメリットは、プロとして成長するための成長痛と捉え直すことです。
一つ目の視点は、これまで見てきたデメリットは、プロとして成長するための成長痛と捉え直すことです。
趣味から仕事へステップアップする過程では、必ず壁にぶつかるものです。
たとえば、お金をもらう恐怖は、プロとしての責任感が芽生えた証拠です。
また、顧客との理想のズレは、独りよがりな趣味の世界から卒業し、市場を学べる重要な課題といえます。
これらの痛みを乗り越えることでしか得られないスキルや自信があります。
ですから、デメリットを恐れるのではなく、自分が前に進もうとしている証拠と捉えましょう。
それは、本物のプロになるために乗り越えていくための大切なハードルなのです。
好きと得意は違うと知ること
 2つ目の視点は、「好きなこと」と「得意なこと」を区別し、さらに好きの種類を深く理解することです。
2つ目の視点は、「好きなこと」と「得意なこと」を区別し、さらに好きの種類を深く理解することです。
仕事として求められるのは、後者の「生み出すのが好き」という情熱であり、これは「得意」と非常に近い関係にあります。
以前も書きましたが、旅行代理店の話がこの好例です。
「旅行に行くのが好き(体験好き)」と、「お客様を喜ばせる旅行を企画するのが好き(提供好き)」は、全く別の感情であり、求められる資質も異なります。
自分の「好き」は、果たしてどちらの種類なのか。
この点を冷静に分析することで、ミスマッチを防ぐ心の土台が整います。
すべてを完璧にこなす必要はないと知る
 3つ目の視点は、「すべてを一人で完璧にこなさなければ」という思い込みを手放すことです。
3つ目の視点は、「すべてを一人で完璧にこなさなければ」という思い込みを手放すことです。
好きなことを仕事にすると、デザインや制作といった得意な作業だけでなく、経理や営業、事務作業など、苦手なこともたくさん出てきます。
それら全てを一人で完璧にやろうとするとエネルギーが尽きて、一番大切にしたいはずの創作活動に集中できなくなってしまいます。
大切なのは、自分の得意な「核」となる部分に集中すること。
そして、苦手なことは、それが得意な他の人の力を借りたり、便利なツールを使ったりして補うことです。
自分の強みを理解し、弱さを認め、それを補う仕組みを作る。
それが、好きなことを長く続けていくための、賢い方法なのです。
好きを仕事に!後悔しないための対策
 「好き」を仕事にするには、ただ情熱があるだけでは不十分です。
「好き」を仕事にするには、ただ情熱があるだけでは不十分です。
ここでは、後悔する確率をぐっと下げ、成功へとつなげるための具体的な事前対策を5つ紹介します。 一つずつ、見ていきましょう。
自分だけの強みを明確にする
 好きを仕事にするときに後悔しないための1つ目の対策は、ご自身の「自分らしさ」を深く掘り下げ、それを唯一無二の強みとして言語化することです。
好きを仕事にするときに後悔しないための1つ目の対策は、ご自身の「自分らしさ」を深く掘り下げ、それを唯一無二の強みとして言語化することです。
「絵を描くのが好き」という情熱はもちろん大切ですが、それだけでは多くの人の中に埋もれてしまいます。
この自分だけの価値をどう見つけ出すか。その具体的な方法は、以下の記事で詳しく解説しています。
関連記事:自分らしさは自分だけの強み【オンリーワンの見つけ方】自己最高の売り・魅力になります
収益化の仕組みを事前設計する
 好きを仕事にするときに後悔しないための2つ目の対策は、感情論ではなく、ビジネスの構造として「どうすれば収益が生まれるか」を設計しておくことです。
好きを仕事にするときに後悔しないための2つ目の対策は、感情論ではなく、ビジネスの構造として「どうすれば収益が生まれるか」を設計しておくことです。
「頑張ればいつか報われる」という根性論だけで突き進むのは危険です。
このお金の流れを事前に考えておくことで、単なる趣味の延長ではなく、継続できる事業としての土台ができます。
業界の平均年収を必ず調査する
 好きを仕事にするときに後悔しないための3つ目の対策は、その業界の現実的な収入レベルを必ず調査しておくことです。
好きを仕事にするときに後悔しないための3つ目の対策は、その業界の現実的な収入レベルを必ず調査しておくことです。
特に、どこかの組織に所属する場合は要注意です。
たとえば、接客業や介護職は、平均年収が低めの業界・業種です。
単に接客が好きだからと飲食の業界を選ぶと、苦しくなる可能性があります。
情熱と現実のギャップに後から苦しまないためにも、希望する働き方で、自分が納得できる収入が得られるのか、客観的なデータで確認しておくことが重要です。
「◯◯業 平均年収」キーワードで検索すればすぐにわかります。
副業から小さくスタートする
 好きを仕事にするときに後悔しないための4つ目の対策は、副業など、できるだけ小さな規模でスタートしてみることです。
好きを仕事にするときに後悔しないための4つ目の対策は、副業など、できるだけ小さな規模でスタートしてみることです。
小さく始めることには、多くのメリットがあります。
市場に本当にニーズがあるのか、お客様はどんな反応をしてくれるのか、そして何より、自分自身が仕事として楽しめるのか。
少ないリスクでこれらを検証し、確かな手応えをつかんでから、本格的に舵を切っても遅くはありません。
「商売=悪」の思い込みを手放す
 好きを仕事にするときに後悔しないための5つ目の対策は、お金に対する「商売=悪」といった思い込みを手放すことです。
好きを仕事にするときに後悔しないための5つ目の対策は、お金に対する「商売=悪」といった思い込みを手放すことです。
特に「好き」を仕事にする人は、「お金をもらうこと」に罪悪感を抱きがちです。
以下の関連記事で詳しく解説していますが、お金は「感謝のバロメーター」と捉えることができます。
自信を持って対価を受け取ることは、自分の仕事に誇りを持つことです。
相手の感謝を正面から受け止める誠実な行為といえるでしょう。
関連記事:お金をもらう罪悪感を感じることなく積極的に受け取る方法【お金は感謝のバロメーター】
好きなことを仕事にする具体的な方法
 「実際にどうやって仕事にしていけばいいのか」 その具体的な方法や、選択肢について、さらに詳しく知りたい方もいるかもしれませんね。
「実際にどうやって仕事にしていけばいいのか」 その具体的な方法や、選択肢について、さらに詳しく知りたい方もいるかもしれませんね。
その具体的な方法については、当ブログの以下の記事で、たくさんの秘訣や実践的なアドバイスを交えて解説しています。
ご自身の状況に合わせて、参考にしてみてください。
関連記事:好きなことを仕事にする方法|趣味を収入に変える秘訣14選
関連記事:好きなことを仕事にするのは難しい?興味ない職業よりいい選択!失敗しないための実践的アドバイス
好きなことを仕事にするのに向いている人
 補足になります。
補足になります。
どのような人がこの道で成功しやすいのか、好きなことを仕事にするのに向いている人の特徴を見ていきましょう。
困難も成長の糧だと捉えられる人
 好きを仕事にするのに向いている人の1番目は、立ちはだかる困難を「成長の糧」だと捉えられることです。
好きを仕事にするのに向いている人の1番目は、立ちはだかる困難を「成長の糧」だと捉えられることです。
好きなことを仕事にする道は、楽しいことばかりではありません。
次々と壁が立ちはだかります。
そんなときに、「どうすれば乗り越えられる?」と課題解決を楽しめる人は、しなやかに成長していくことができるでしょう。
客観的な視点で自分を見つめられる人
 好きを仕事にするのに向いている人の2番目は、自分の情熱から一歩引いて、客観的な視点を持てることです。
好きを仕事にするのに向いている人の2番目は、自分の情熱から一歩引いて、客観的な視点を持てることです。
「好き」という気持ちが強いと、つい主観的になりがちです。
しかし、ビジネスとして成功するためには、自分の強みや市場のニーズを冷静に分析する視点が必要になります。
自分がどう思うかではなく、顧客がどう思うかを第一に考えられる人です。
学び続ける意欲と行動力がある人
 好きを仕事にするのに向いている人の3番目は、好きな分野だけでなく、ビジネスについても学ぶ行動力があることです。
好きを仕事にするのに向いている人の3番目は、好きな分野だけでなく、ビジネスについても学ぶ行動力があることです。
マーケティング、経理、営業など、知らないことがあるのは当然。
得意・不得意に関わらずそれを埋める行動を自ら起こせる人は向いています。
好きなことを仕事にするのに向いていない人
 一方で、好きという気持ちだけでは乗り越えるのが難しいタイプの方もいます。
一方で、好きという気持ちだけでは乗り越えるのが難しいタイプの方もいます。
もし当てはまると感じても、落ち込む必要はありません。
自分を理解し、仕事以外の形で「好き」と関わる道を探すきっかけにしてくださいね。
「好き=楽な仕事」だと考えている人
 好きを仕事にするのに向いていない人の1番目は、「好きだから楽に違いない」というイメージを抱いている人です。
好きを仕事にするのに向いていない人の1番目は、「好きだから楽に違いない」というイメージを抱いている人です。
むしろ、好きだからこそこだわりが生まれ、生半可な仕事はできない厳しい側面があります。
仕事に「楽」を求める人には、残念ながら向いていない道かもしれません。
理想が高すぎて現実を受け入れられない人
 好きを仕事にするのに向いていない人の2番目は、自分の理想やこだわりが強すぎて、現実的な落としどころを見つけられない人です。
好きを仕事にするのに向いていない人の2番目は、自分の理想やこだわりが強すぎて、現実的な落としどころを見つけられない人です。
お客様の要望や予算の都合で、自分の理想を曲げなければならない場面は出てきます。
そのときに、柔軟に対応できないと、誰からも受け入れられず、孤立してしまうのです。
他者からのフィードバックを嫌う人
 好きを仕事にするのに向いていない人の3番目は、お客様からの厳しいフィードバックを「自分への攻撃」と捉え、耳を塞いでしまう人です。
好きを仕事にするのに向いていない人の3番目は、お客様からの厳しいフィードバックを「自分への攻撃」と捉え、耳を塞いでしまう人です。
仕事として価値を提供するかぎり、他者からの評価は避けられません。
それを真摯に受け止め、改善につなげる素直さが不可欠です。
まとめ:デメリットを理解して賢く挑戦しよう
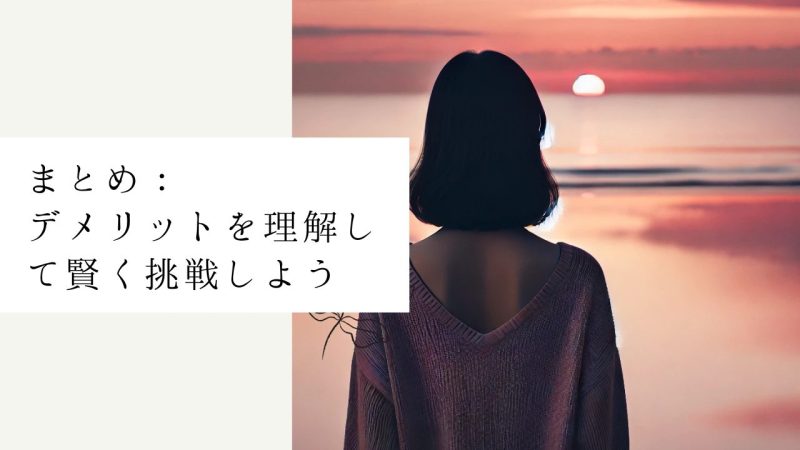 多くの人が憧れる「好き」の仕事化ですが、そこには収入や人間関係、精神的な葛藤など、さまざまな壁が立ちはだかります。
多くの人が憧れる「好き」の仕事化ですが、そこには収入や人間関係、精神的な葛藤など、さまざまな壁が立ちはだかります。
自分一人で考えを深めるのは難しい、と感じることもあるでしょう。
もしも、ご自身の強みや向いている方向性をさらに深く知りたいという場合は、「自分力活用講座」でお手伝いできることがあるかもしれません。
ご興味があれば以下をご覧ください。
参考:自分力活用講座
【無料】自分の見つめ直しマニュアル
 「好き」を仕事にするかどうかは、究極的には、どちらが正しいという問題ではありません。
「好き」を仕事にするかどうかは、究極的には、どちらが正しいという問題ではありません。
大切なのは、ご自身が納得し、幸せを感じられる働き方、そして生き方を見つけることです。
「自分の本当の強みは?」
「心から大切にしたい価値観は?」
「どんなときに自分は輝ける?」
こうした問いと向き合うことで、はじめて、自分だけの答えが見えてきます。
でも、多くの人は、その具体的な方法が分からずに、一人で悩んでしまいます。
これまで10年以上の歳月をかけ、多くの受講生と向き合う中で体系化したノウハウを、「自分の見つめ直し完全マニュアル」としてまとめました。
以下、充実の内容です。
- 自分の棚卸しに使える100の質問シート:自分自身を深く理解するための問いかけを提供し、長所や可能性を探るのに役立ちます。
- 自己肯定感を高めるための100の質問シート:自信を持って前向きに生きるための支援をします。
- 今の仕事合う?合わないチェックリスト:現在の職場環境が自分に合っているか評価するのに役立ちます。
- やる気ペンタゴンチャート:モチベーションを高め、行動を促すためのツールです。
- ときめきのツボワークシート:自分の情熱や興味が何にあるのかを探るのに役立ちます。
私の個人セッション(月々3万円)や講座の受講生たちを指導する際に使っているノウハウから厳選しました。配布を開始したその日、300人以上から申し込みがあったものです。
ただし、無料配布をいつまで続けるかわからないです。すいません。必要な人は、今すぐ入手して保存をおすすめします。
下記フォームにお名前とメールを入力するだけで入手できます。
こちらにLINE登録していただくと、自分らしく生きるための耳寄りなお話も公開してます。ブログには書けないここだけの情報も配信しています。

私との直接のやりとりもできますよ
最後に筆者からの大切なメッセージ

「好き」を仕事にする道は、決して一つではありません。
大切なのは、世間の声に惑わされず、ご自身の心が本当に喜ぶ選択をすること。
この記事が、そのための小さなヒントになれば、これ以上の喜びはありません。
お読みになった方々の未来が明るくなることを心から願っています。
魂の女性成長支援・浅野塾代表 浅野ヨシオ

浅野ヨシオ:
女性成長支援コンサルタント。
魂の女性成長支援・浅野塾 代表。
2007年よりビジネスパーソンや出版希望者を対象とした、自分の強みを発見し唯一無二のブランドを作る講師として活動。ハイキャリアの女性たちでも自分の能力がわからず強い自信を持てずにいることを知る。
2011年、女性成長支援の講座を起ち上げ、幼少期から現在までの人生史を平均200時間以上かけて深掘りする指導に定評がある。
通算15年2000人超の女性専門指導の経験により、心を縛る足かせをはずし、自分にとっての幸せを追求する自己実現プログラムを多数構築する。
著書に「私はこの仕事が好き!自分の強みを活かして稼ぐ方法(大和出版)」がある。
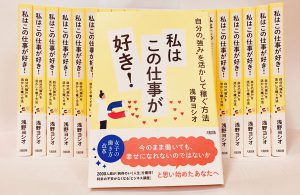
◎メディア実績:日本経済新聞/日経WOMAN/PRESIDENTほか多数
◎講演実績:横浜市経済観光局/多摩大学/NPO法人Woman’sサポート/自由大学/青森商工会連合会/天狼院書店/(株)スクー/ほか多数
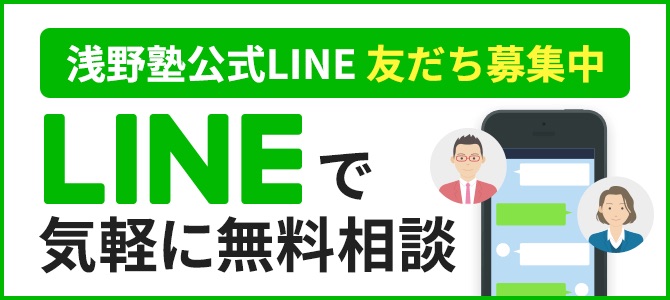


コメント