「なぜ自分はこんなに敏感なんだろう」
他人の些細な言葉に傷ついたり、周りの空気を読みすぎて疲れたり。 感受性が強いことで、生きづらさを感じている人も少なくありませんね。
この記事では、2000人以上のキャリア指導経験から、感受性が強い原因を解説します。 あわせて、その繊細さを「才能」として人生に活かす実践法もお伝えしますね。
原因を知ることは、自分を肯定する第一歩です。 最後までお読みくださいね。
追伸:本文の最後に素敵なマニュアルのプレゼントをご用意しています。
- 記事を書いている人の専門性と実績
経歴:
新卒8ヶ月での挫折退職から再出発。26年の会社員経験(10年は複業)を経て起業。現在は個性を活かす道を拓く会社を経営。
専門:
感受性が強い人を含む、2000人超の女性指導実績。本当の強みを発見し、人生を新たな方向へ導く自己分析のプロ。やりがいのある転職から起業まで、前職や年齢を超えた女性の夢実現に定評。
メディア/著書:
日本経済新聞、日経WOMAN他多数掲載。著書「私はこの仕事が好き!自分の”強み”を活かして稼ぐ方法(大和出版)」
感受性が強いとは?意味と特徴
 感受性が強いとは、外からの刺激や他人の感情、その場の雰囲気などを、人よりも深く細やかに感じとる特性のことです。
感受性が強いとは、外からの刺激や他人の感情、その場の雰囲気などを、人よりも深く細やかに感じとる特性のことです。
決してネガティブな意味ではなく、むしろ物事を感じとる力が鋭い状態といえます。
たとえば、映画や音楽に深く感動して涙が出たり、相手の表情のわずかな変化から気持ちを察したりできるでしょう。
一方で、その鋭さゆえに、人混みや大きな音、相手のささいな一言に人一倍疲れを感じやすい側面も持っています。
生きづらさを感じることもあるかもしれませんが、それは短所ではなく、あくまで特性の一つなだけです。
感受性が強い5つの原因【遺伝?環境?】
その背景には、生まれつきの気質や育った環境など、いくつかの要因が関係しています。主な5つの原因を解説しますね。
原因①遺伝的な気質【生まれつき】
感受性が強い原因の1つ目は、生まれ持った遺伝的な気質です。
これは「感覚処理感受性(SPS)」と呼ばれる特性です。科学的な研究でも注目されています。
外部からの刺激を処理する脳の働きが敏感に反応し、他の人が気づかないような細かな点にも気づきやすくなります。
たとえば、音や光、においなどの刺激に敏感だったり、人の感情の変化を察知しやすかったりします。
これは生まれ持ったものです。
この特性は生まれつき備わっているもので、世界の人口の約5人に1人(約20%)が持っているといわれています。
もし子どものころから「自分はまわりと少し違うかも」と感じていたなら、この気質が関係しているのかもしれませんね。
原因②幼少期の環境【3つのパターン】
感受性が強い原因の2つ目は、幼少期の環境です。
持って生まれた気質に、育った環境が影響して、繊細さが強まることがあります。
私の指導経験では、主に3つのパターンが見られました。
たとえば、テストで95点を取っても「よくできたね」ではなく、「どうして残りの5点を間違えたの?」と指摘されるようなケースです。
結果ばかりを評価されることで、「失敗してはいけない」と自分を追い込み、他人の反応や小さなミスに過敏になっていきます。
双子や年子、1歳違いのきょうだいなど、年齢が近いと特に比較の対象になりやすいですね。
「お姉ちゃんは優秀なのに」と比べられたり、逆に長男が特別扱いされるなど、誰かと比較される中で努力しても認められにくい経験をした人も多いでしょう。
その結果、常に他人の評価を気にするようになり、周りの目に敏感になります。
親の気分や態度が日によって変わる家庭では、子どもはいつも親の顔色をうかがい、機嫌を損ねないように行動します。
その過程で、相手の感情のわずかな変化を察知する力が過剰に発達し、感受性が強くなっていきます。
原因③脳の特性【扁桃体の反応性】
感受性が強い原因の3つ目は、脳の特性です。
脳の中には「扁桃体(へんとうたい)」と呼ばれる、不安や恐れを感じ取るアンテナのような部分があります。
感受性が強い人は、このアンテナが生まれつき活発に働く傾向があります。
他の人が気づかない小さな変化や危険にも反応しやすく、危険を早く察知できる一方で、不安を感じやすく疲れやすい面もあります。
原因④芸術・文化への深い接触
感受性が強い原因の4つ目は、芸術や文化に深く触れたことです。
これは、生まれつきではなく、育つうちに「感性が磨かれた」パターン。 きれいな絵や音楽、本などに小さいころから触れてきたなどですね。
そうすると、物事の細かな違いや、表現の奥にある気持ちを感じとる力が育ちます。
小説の登場人物に「わかるなぁ」と共感する。 景色の美しさに「すごい…」と心から感動する。
こうした経験の積み重ねが、豊かな感受性や共感力を育てる土台になるのです。
原因⑤複合要因【個人差がある】
感受性が強い原因の5つ目は、これまでの原因が混ざりあっていることです。
多くの場合、生まれつきの気質を土台に、育った環境や脳の特性、これまでの経験などが重なり合って影響しています。
どの要素がどのくらい強く働くかは、人それぞれ異なります。
だからこそ、「自分にはこういう背景があるのかもしれない」と知ることが、理解への第一歩になるのです。
【感受性が強い原因 まとめ】
- 生まれつきの気質(遺伝)
- 完璧さを求められた環境
- きょうだいとの比較
- 脳の特性(アンテナが敏感)
- 芸術などに触れた経験
- これらが複雑に影響しあっている
原因を知ることは、自分を理解する大切なステップ。 「自分にはこんな背景があるのかも」と知るだけで、心が少し軽くなったかもしれませんね。
さて、感受性が強いとよく聞かれるのが「HSP」という言葉です。
「自分はHSPなのかな?」と気になる人も多いでしょう。 次のセクションでは、このHSPとの関係について見ていきましょう。
感受性が強いとHSP【その違いとは】
 感受性が強いと、HSP(エイチエスピー)は、よく似た言葉として使われますね。
感受性が強いと、HSP(エイチエスピー)は、よく似た言葉として使われますね。
結論からいうと、この2つはイコール(=)ではありません。
感受性が強いというのは、前にもお伝えした通り、刺激や感情を深く細やかに感じとる特性を指す、広い意味での言葉です。
一方、HSP(Highly Sensitive Person)は、生まれつき刺激にとても敏感で、繊細な気質を持つ人を指す言葉です。
これは、アメリカの心理学者アーロン博士が使い始めた呼び名。 博士によれば、約5人に1人がこのHSPにあてはまるといわれていますね。
つまり、感受性が強いという大きなグループの中に、HSPという特定の人たちが含まれるイメージですね。
ただ、どちらも繊細な特性であることに変わりはありません。
感受性が強い人の7つの特徴
ここでは、多くの感受性が強い人に見られる、代表的な特徴を紹介しますね。
特徴①他人の感情に敏感で疲れやすい
感受性が強い人の1つ目の特徴は、他人の感情に敏感なことです。
相手の表情や声のトーン、ささいな態度の変化。 そこから「今、機嫌が悪いのかな」と、気持ちを察するのが得意です。
これは素晴らしい才能ですね。
しかし同時に、相手のイヤな感情まで自分のことのように受けとめがち。
そのため、人間関係で気疲れしやすい側面があります。
特徴②物事を深く考えすぎる傾向がある
感受性が強い人の2つ目の特徴は、物事を深く考えすぎることです。
たとえば、人から言われた何気ない一言。 後から何度も思い出しては、「あの言葉は何を意味していたのかしら」とグルグル考えてしまいます。
一つの情報を深く掘り下げ、さまざま考えられるのは長所です。
しかし、それが原因で行動に移せなくなったり、不安が大きくなったりもします。
特徴③五感が鋭く刺激を受けやすい
感受性が強い人の3つ目の特徴は、五感が鋭いことです。
五感とは、視覚、聴覚、嗅覚、味覚、触覚のこと。
たとえば、他の人が気にならないような小さな物音や、かすかなにおいにもよく気づきます。
まぶしい光や、服のタグが肌に当たるチクチク感が苦手な人も多いですね。
こうした刺激を強く受けとめるため、人混みなどではぐったり疲れてしまいます。
特徴④共感力が高く感情移入しやすい
感受性が強い人の4つ目の特徴は、共感力がとても高いことです。
友人から相談を受けると、まるで自分の悩みのように共感します。
映画やドラマの登場人物に、強く感情移入して涙することも多い。
相手の痛みを理解できる優しさを持っています。
一方で、相手の感情との境界線があいまいになりやすく、他人の問題まで背負い込んでしまうこともあります。
特徴⑤直感が鋭く本質を見抜く
感受性が強い人の5つ目の特徴は、直感が鋭いことです。
言葉になっていない情報や、その場の雰囲気。 そうした「なんとなく」の感覚をキャッチする力に優れています。
「この話は、何かウラがありそうだ」
「この人は信頼できそうだ」
といった感覚が、後で当たっていた経験も多いはずです。
物事の表面的な部分だけでなく、その奥にある本質を見抜く力があります。
特徴⑥誠実で責任感が強い
感受性が強い人の6つ目の特徴は、とても誠実で責任感が強いことです。
物事を深く考える特性(特徴②)とも関連します。 自分が引き受けた仕事や役割は、手を抜かずに完璧にこなそうとしますね。
周りの期待にも応えようと、一生懸命に努力する。
周りからは信頼されますが、自分に厳しくなりすぎて、一人で抱え込みやすい面もあります。
特徴⑦芸術的な感性に優れている
感受性が強い人の7つ目の特徴は、芸術的な感性に優れていることです。
これは、原因④(芸術・文化への深い接触)ともつながっていますね。
美しい音楽や絵画、自然の風景などに、深く心を動かされます。
他の人が見過ごしてしまいがちな、道端に咲いているタンポポのように、日常の中の小さな美しさにも気づけます。
自分自身で何かを生み出したり、表現したりすることに喜びを感じる人も多いです。
感受性の強さを人生に活かす5つの実践法
 感受性が強いことには、疲れやすい側面もあります。 それ以上に素晴らしい才能がたくさんありましたね。
感受性が強いことには、疲れやすい側面もあります。 それ以上に素晴らしい才能がたくさんありましたね。
大切なのは、その繊細さを「抑える」ことではありません。 才能として人生に活かしていくことです。
ここでは、私の15年間に渡る指導経験から見つけた、5つの実践法を紹介します。
方法①「感情」と「事実」を切り離す
感受性の強さを活かす1つ目の実践法は、自分の「感情(解釈)」と「事実」を切り離すことです。
感受性が強い人は、自分の感覚をとても重視します。 その結果、思い込みが強くなる傾向があります。
たとえば、誰かのささいな言動で「あの人は私を嫌っている」と強く感じたとします。 その感覚があまりにリアルなため、それが「事実」のように思えてしまいます。
しかし、彼らを見てきて感じるのは、「自己評価は、意外とあてにならない」ということです。
まずはこの「自分の感覚=絶対の事実ではない」と知ることが、最も重要なマインドセットですね。
- 実践法としては、モヤモヤしたら紙に書き出してみるのが効果的です。
左側に起きた事実、右側に感じた解釈を書くのです。
・事実:Aさんに挨拶したが、返事がなかった。
・解釈:私は嫌われているのかもしれない。
このように書き分けると、事実と解釈を別物だと認識できます。
解釈には個人差があります。ポジティブな人は前向きな解釈をするでしょうし、ネガティブな人はその逆の解釈をするでしょう。
感受性が強い人は、ついネガティブな解釈を選びがちです。 しかし、事実は「挨拶に返事がなかった」だけ。
・(事実)Aさんは、ただ忙しくて聞こえなかっただけかも
・(事実)Aさんは、考え事をしていて気づかなかったかも
このように、自分がした解釈とは「別の可能性」がたくさん見えてきます。 それこそが、客観的な視点を取り戻すための大切な訓練になります。
方法②「直感」と「不安」を区別する
感受性の強さを活かす2つ目の実践法は、「直感」と「不安」を区別することです。
感受性が強い人は、「なんとなく合わない」「こっちが良さそう」という感覚が鋭い傾向があります。
それは、物事の本質を感じ取る才能でもあります。
ただし、その“感覚”がいつも正しいとは限りません。 中には「直感」ではなく、過去の経験からくる“不安”が反応している場合もあります。
たとえば、子どものころから完璧さを求められて育った人は、新しいことに挑戦しようとするとき、 「失敗したらどうしよう」と強く不安を感じやすくなります。
その不安を「この仕事は向いていない気がする」と“直感”と勘違いしてしまうことがあるのです。
- 実践のステップ
- 気持ちが動いた瞬間をメモする
「この仕事は良さそう」「あの人はちょっと苦手」など、感じたままを書き残します。 - 1か月後・3か月後に振り返る
そのときの判断がどうだったかを見返してみましょう。
繰り返していくうちに、
「このザワザワは不安だったんだ」
「このワクワクは本物の直感だった」
と、自分の“感覚のパターン”がわかるようになります。
直感と不安を区別できるようになると、迷いが減り、自分の感覚を信じて行動できるようになります。
それは、感受性が強い人にとって大きな強みになります。
方法③「なぜ?」で感情の根っこを掘る
感受性の強さを活かす3つ目の実践法は、感情の根っこにある価値観を言葉にすることです。
感受性が強い人は、他人の言動や出来事に人一倍心が動きます。 イラッとしたり、悲しくなったり、逆にとても嬉しくなったり。
その強い感情こそが、何を大事にしているのか(価値観)を見つける最大のヒントです。
しかし、ただ感情に振り回されているだけでは疲れてしまいます。 その感情が「なぜ」起きたのか、根っこを掘ることが大切です。
- 実践のステップ
- 感情が動いた出来事を書き出す
例:「あの人の言い方にイラッとした」 - 「なぜ?」を5回くり返して掘り下げる
(なぜ①)見下された気がしたから
(なぜ②)対等に話してほしかったから
(なぜ③)お互いを尊重することが大事だと思うから
(なぜ④)自分も相手も安心して意見を言い合いたいから
(なぜ⑤)本音でつながれる関係を大切にしたいから - 価値観(根っこ)を言葉にする
→ 結論:「自分は“お互いを尊重すること”を大切にしているんだな」
このように感情の「根っこ」を掘ることで、 「尊重」「自由」「安心」「誠実」といった自分の価値観の言葉が見えてきます。
価値観が明確になると、 自分に合う環境や仕事、人間関係を選びやすくなります。 つまり、感情のゆらぎを自己理解のツールに変えられるのです。
方法④ 才能を「客観的な強み」で定義する
感受性の強さを活かす4つ目の実践法は、才能を客観的な強みとして定義し直すことです。
感受性が強い人は、周りから「考えすぎ」「繊細すぎる」と言われ、自分でもそれを短所だと思い込んでしまいがちです。
しかし、「自己評価はあてにならない」というマインドセットが大切です。
自分が短所だと思っている特性こそ、見方を変えれば他の人にはない大きな強みになることがあります。
- 実践のステップ
- 短所だと感じていることを書き出す
物事を深く考えすぎる
共感しすぎて疲れる
刺激に敏感で人混みが苦手 - 「強み」として言い換える
「多角的に検討できる」
⇒「リスク管理能力が高い」
「相手のニーズを深く理解できる」
⇒「傾聴力が高い」
「小さな変化や異常にすぐ気づける」
⇒「集中力が高い」
この言い換えリストは、転職活動の自己PRなど、客観的な評価が求められる場面でも役立ちます。自分の才能を「強みの言葉」で定義できるようになると、自信を持ってそれを活かす一歩が踏み出せます。
方法⑤ 「感性」をポジティブに使う訓練
感受性の強さを活かす5つ目の実践法は、「感性」を意識的にポジティブに使うことです。
感受性が強い人は五感が鋭いぶん、騒音・他人の機嫌・嫌なニュースなど、イヤな刺激にも影響を受けやすいものです。
放っておくと、繊細なアンテナがネガティブな情報ばかりを拾い、心が疲れてしまいます。
だからこそ、その鋭い感性を「良い情報」に向けて使う訓練が大切です。
- 実践のステップ
- 寝る前にノートを開く
- その日の「良かったこと」や「心が動いたこと」を3つ書き出す
(例)
・今日のコーヒーの香りがとても良かった
・夕焼けの色がきれいだった
感受性が強い人に向いてる仕事6選
 感受性の強さを才能として活かすには、どのような仕事が良いのでしょうか。 7つの特徴や活かし方を踏まえ、特におすすめの仕事を6つ紹介しますね。
感受性の強さを才能として活かすには、どのような仕事が良いのでしょうか。 7つの特徴や活かし方を踏まえ、特におすすめの仕事を6つ紹介しますね。
仕事①クリエイティブ職(デザイナー・ライターなど)
感受性が強い人に向いてる仕事の1つ目は、クリエイティブな職種です。
たとえば、デザイナー、ライター、動画編集者、音楽家などですね。
感受性が強い人は、芸術的な感性に優れています。 道端のタンポポにも美しさを見いだせるその繊細な視点。 それは、人の心を動かす作品を生み出すための、かけがえのない才能です。
また、五感の鋭さも、色彩や音、言葉の細かな違いを表現する力として活きてきます。 なんとなくの感覚を形にする仕事は、まさに天職といえるかもしれませんね。
仕事②人をサポートする仕事(カウンセラーなど)
感受性が強い人に向いてる仕事の2つ目は、人をサポートする仕事です。
たとえば、カウンセラーやコーチ、カスタマーサポート、医療・福祉関係などです。
感受性が強い人は、他人の感情に敏感で、共感力がとても高い。 相手の表情や声のトーンから、言葉にならない悩みやニーズを察知できます。
その察する力は、相手に深く寄り添い、安心感を与える上で何より大切な才能です。
相手の痛みを理解できる優しさが、そのまま仕事になる分野ですね。
仕事③分析・研究職(アナリスト・研究者など)
感受性が強い人に向いてる仕事の3つ目は、分析や研究に関わる職種です。
データアナリスト、マーケター、研究者、校正者などです。
感受性が強い人は、物事を深く考えすぎる傾向があります。 これは、情報を多角的に検討し、本質を見抜く力ですよ。
他の人が見過ごすような、データや文章の小さな違いにも気づけます。
一つのことを深く掘り下げ、その中にある法則や意味を見つけ出す仕事は、その才能を存分に活かせるでしょう。
仕事④専門職・技術職(エンジニア・職人など)
感受性が強い人に向いてる仕事の4つ目は、専門的な技術を扱う職種です。
エンジニアやプログラマー、伝統工芸などの職人、整備士などです。
これらの仕事は、高い集中力と正確性が求められます。 感受性が強い人は、誠実で責任感が強く、手を抜かずに完璧を目指します。
また、五感の鋭さが、コードのわずかなミスや、製品の手触り、機械の異音といった細部へのこだわりに活きます。
コツコツと自分の技術を磨き、質の高い成果を生み出す分野に向いています。
仕事⑤自然や動物に関わる仕事(花屋・トリマーなど)
感受性が強い人に向いてる仕事の5つ目は、自然や動物に関わる仕事です。
たとえば、花屋(フローリスト)、ガーデナー、トリマー、動物の飼育員などです。 芸術的な感性や、タンポポにも気づく繊細な視点。 これらは、植物の美しさを引き出したり、言葉を話せない動物の様子の変化を察知したりする力につながります。
五感の鋭さも、植物の香りや動物の気配を感じとる上で役立ちます。
人間関係のストレスが少なく、自分の感性を素直に活かせる環境です。
仕事⑥静かな環境での事務職(経理・バックオフィス)
感受性が強い人に向いてる仕事の6つ目は、静かな環境で働ける事務職です。
たとえば、経理、総務、人事などのバックオフィス業務です。
感受性が強い人は、五感が鋭いぶん、刺激に弱い面があります。
騒がしいオフィスや、不特定多数の人と接する環境は、疲れやすいでしょう。
一方、経理や総務の仕事は、数字やルールを正確に扱う必要があります。
責任感が強く誠実な特性を活かし、静かな環境でコツコツと取り組めるため、安心して力を発揮しやすいです。
このように仕事としてまとめると、感受性の強さは立派な強みであることがわかりますよね。
逆に、感受性が強い人が避けたほうがよいのは、刺激が強すぎる環境です。
たとえば、ノルマが厳しく競争が激しい職場、騒音が大きい場所、頻繁なマルチタスクが求められる仕事などです。
自分の特性と合わない環境では、才能を活かすどころか、疲れてしまいます。
感受性が強い人のストレス対処法6つ
才能を活かすためにも、自分を守るストレス対処法を知っておくことは、とても大切です。
ここでは、すぐに実践できる6つの対処法を紹介しますね。
対処法①刺激を物理的にシャットアウトする
感受性が強い人の1つ目のストレス対処法は、刺激を物理的にシャットアウトすることです。
五感が鋭いため、普通の人なら気にならない音や光も、大きなストレスになります。
「我慢する」のではなく、「防ぐ」ことを考えましょう。
たとえば、仕事に集中したいときは、ノイズキャンセリング機能付きのイヤホンや耳栓を使います。
人混みに行くときは、サングラスや帽子で視界に入る情報を減らす。
服のタグがチクチクするなら、迷わず切ってしまう。
このように、物理的に刺激を減らすだけで、疲れ方はまったく違ってきます。
対処法②一人の時間を意図的に確保する
感受性が強い人の2つ目のストレス対処法は、一人の時間を意図的に確保することです。
感受性が強い人は、他人と一緒にいると、無意識に相手の感情や場の空気を読み続けてしまいます。
どれだけ楽しい時間でも、気づかないうちにエネルギーを消耗している。意識して「一人になる時間」を作りましょう。
たとえば、お昼休みは一人で静かに過ごす。
仕事が終わったら、15分だけカフェに寄ってから帰る。
一日の終わりに、誰とも話さずボーっとする時間を持つ。
このように、刺激をリセットし、自分だけの感覚を取り戻す時間がとにかく必要不可欠です。
対処法③「事実」と「感情」を書き出す
感受性が強い人の3つ目のストレス対処法は、「事実」と「感情」を書き出すことです。
「あの人に嫌なことを言われた」とグルグル考えてしまうとき。
それは「事実」以上に「感情(解釈)」に振り回されている状態です。
モヤモヤしたら、紙に「起きた事実」と「感じた感情」を書き出してみましょう。
「(事実)〇〇と言われた」
「(感情)悲しかった。悔しかった」
書き出すだけで客観的になれ、感情の渦から抜け出しやすくなります。
対処法④ネガティブな情報源から離れる
感受性が強い人の4つ目のストレス対処法は、ネガティブな情報源から意識的に離れることです。
共感力が高いため、ニュースやSNSで目にする悲しい出来事や、他人の攻撃的な言葉に、必要以上に心を痛めてしまいます。
それらの情報が、自分のエネルギーを奪っていくのです。
心が疲れていると感じたら、意識的にニュースサイトやSNSを見る時間を減らしましょう。
フォローする人を見直すのも良いですね。
自分にとって心地よい情報、安心できる情報を選ぶことも、大切な自分を守る技術です。
対処法⑤「まあいっか」を口グセにする
感受性が強い人の5つ目のストレス対処法は、「まあいっか」を口グセにすることです。
感受性が強い人は、責任感が強く、完璧を目指しがちです。
「こうあるべきだ」という理想が高く、小さなミスや他人の期待に応えられない自分を責めてしまいます。
そんなときは、「まあいっか」と声に出してみましょう。完璧でなくても大丈夫だ、と自分を許してあげるのです。
100点満点を目指すのをやめて、80点くらいでOKにする。
これは、甘えやサボりではないのでご安心ください。
その「ゆるさ」が、心の余裕につながります。やる気のスイッチが入り、結果的にこれまでより良い結果に結びつきますよ。
対処法⑥五感を満たすリラックス法を持つ
感受性が強い人の6つ目のストレス対処法は、五感を満たすリラックス法を持つことです。
五感が鋭いということは、イヤな刺激に弱い半面、「心地よい刺激」からも大きな癒やしを得られるということです。
これは素晴らしい才能です。
たとえば、
- 肌触りの良い毛布にくるまる(触覚)
- 好きなアロマの香りをかぐ(嗅覚)
- 心地よい音楽を聴く(聴覚)
- お気に入りのハーブティーを飲む(味覚)
- きれいな景色や絵画を見る(視覚)
このように、自分の五感が「喜ぶ」時間を作ることで、効果的にストレスをケアできます。
感受性をさらに高める具体的な方法
 これまでは、感受性の強さによる疲れへの対処法が中心でしたね。
これまでは、感受性の強さによる疲れへの対処法が中心でしたね。
しかし、感受性は才能です。 最後は、その才能をさらに伸ばし、人生を豊かにするための具体的な方法を3つ紹介します。
方法①芸術に触れて「解釈」を言葉にする
感受性を高める1つ目の方法は、芸術に触れて「解釈」を言葉にすることです。
きれいな絵や音楽、文学に触れると、心が動かされますよね。
ただ「感動した」で終わらせず、「なぜ感動したのか」を深く掘り下げることが、感性をさらに磨くことにつながります。
自分の感情の動きが、よりハッキリと理解できるようになるでしょう。
- 実践のステップ
- 絵や音楽、映画などに触れ、「心が動いた」ものを選ぶ
- 「なぜ、自分はこれに感動したんだろう?」と問いかける
- 「この青色が寂しそうに見えたからだ」
- 「この歌詞が、昔の自分と重なるからだ」
このように、自分が感じた解釈を言葉にする訓練は、感性をさらに鋭く、深くしてくれます。
方法②自然の中で五感を研ぎ澄ます
感受性を高める2つ目の方法は、自然の中で五感を研ぎ澄ますことです。
五感が鋭いことは、街中では「刺激が多くて疲れる」という弱点になりがちです。
しかし、自然の中では、その鋭い五感が「才能」として輝きます。 普段は閉じがちな感覚のアンテナを、安全な場所で思い切り開いてみましょう。
- 実践のステップ
- 公園や森など、静かな自然のある場所に行く
- 目を閉じて、聞こえてくる音(風の音、鳥の声)だけに集中する
- 次に、匂い(土の匂い、花の香り)だけに集中する
- 葉っぱの手触りや、木肌のゴツゴツ感を確かめる
このように五感をフルに使う体験は、感性を豊かにし、ストレス解消にもつながります。
方法③他者の視点を「体験」してみる
感受性を高める3つ目の方法は、他者の視点を「体験」してみることです。
感受性が強い人は、高い共感力を持っています。 その才能を「相手の気持ちがわかってツラい」で終わらせるのは、もったいないことです。
一歩進んで、「もし自分がその人だったら、どう考え、どう行動するか」を想像してみましょう。
- 実践のステップ
- 尊敬する人や、逆に「理解できない」と感じる人を選ぶ
- その人になりきって、「なぜあの人は、あのときああ言ったんだろう?」と考えてみる
- その人の半生や考え方がわかる本(伝記など)を読んでみる
これは、自分の世界を広げ、感受性を「共感」から「深い理解力」へと高めてくれる訓練です。
自分の見つめ直し完全マニュアル【無料】
 ここまで、感受性が強い原因から、特徴、活かし方、対処法までを詳しく見てきました。 感受性が「短所」ではなく、人生を豊かにする素晴らしい「才能」であることを、ご理解いただけたのではないでしょうか。
ここまで、感受性が強い原因から、特徴、活かし方、対処法までを詳しく見てきました。 感受性が「短所」ではなく、人生を豊かにする素晴らしい「才能」であることを、ご理解いただけたのではないでしょうか。
記事では、その才能を活かすための実践法や、価値観の見つけ方を紹介しました。 しかし、「一人でやるのは難しそうだ」 「自分の価値観が、本当にこれで合っているか不安だ」 と感じる人もいるかもしれません。
もしも、本気で自分の感受性と向き合い、それを「最強の強み」に変えて、自分らしいキャリアや人生を見つけたいと考えるなら。
2000人以上の指導経験で培ったノウハウを詰め込んだ「自分の見つめ直し完全マニュアル」を、今なら無料でお渡ししています。
このマニュアルは、これまでの人生を振り返り、自分の特性を体系的に整理して分かりやすく理解することができます。
制作に10年の歳月をかけた逸品。以下、充実の内容です。
- 自分の棚卸しに使える100の質問シート:自分自身を深く理解するための問いかけを提供し、長所や可能性を探るのに役立ちます。
- 自己肯定感を高めるための100の質問シート:自信を持って前向きに生きるための支援をします。
- 今の仕事合う?合わないチェックリスト:現在の職場環境が自分に合っているか評価するのに役立ちます。
- やる気ペンタゴンチャート:モチベーションを高め、行動を促すためのツールです。
- ときめきのツボワークシート:自分の情熱や興味が何にあるのかを探るのに役立ちます。
私の個人セッション(月々3万円)や講座の受講生たちを指導する際に使っているノウハウから厳選しました。配布を開始したその日、300人以上から申し込みがあったものです。
ただし、無料配布をいつまで続けるかわからないです。すいません。必要な人は、今すぐ入手して保存をおすすめします。
下記フォームにお名前とメールを入力するだけで入手できます。
さらに、マニュアルだけでは不安な方や、私の指導を直接体験してみたいという方のために、個別の講座もご用意しています。
記事やマニュアルでは伝えきれない、一人ひとりの状況に合わせた深い自己分析と、キャリアへの活かし方を一緒に見つけていきましょう。
ご興味のある方は、以下のページから詳細をご確認ください。
こちらにLINE登録していただくと、自分らしく生きるための耳寄りなお話も公開してます。ブログには書けないここだけの情報も配信しています。

私との直接のやりとりもできますよ

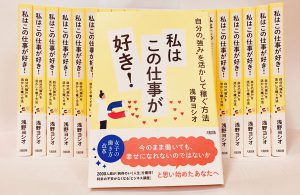




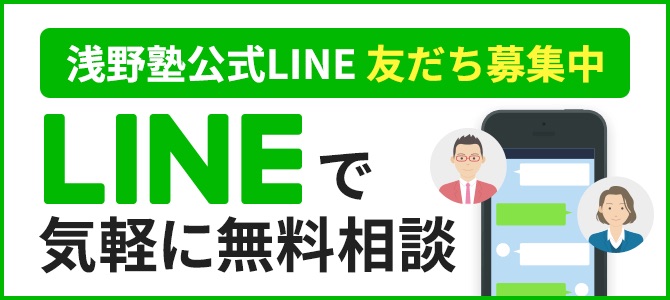


コメント